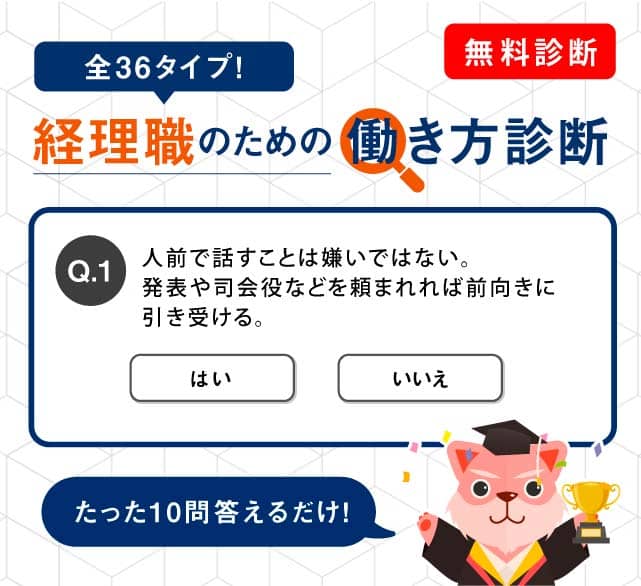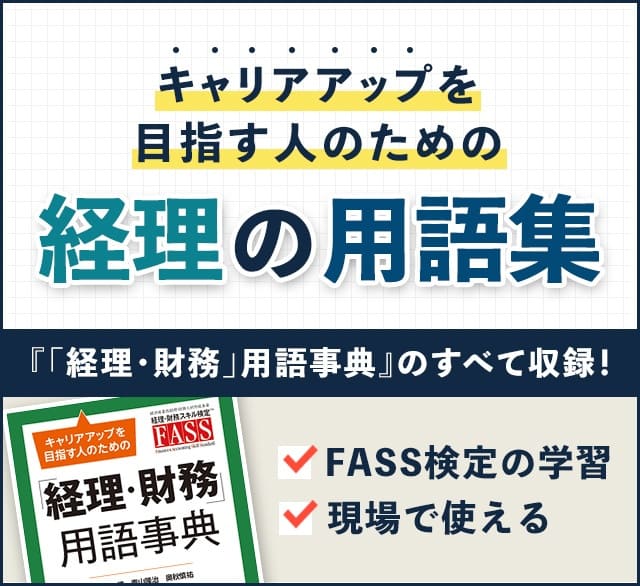■簡易課税制度とは
インボイス制度が始まる前は、基準期間(通常、個人事業主であれば2年前、法人であれば前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下であるなどの要件に当てはまれば、消費税を納めなくてよい「免税事業者」となっていました。
しかし、
2023年10月より始まったインボイス制度により適格請求書発行事業者に登録した場合は、基準期間の課税売上高にかかわらず自動的に「課税事業者」となり、消費税の納付額を計算して申告することが必要になりました
。
消費税の計算方法は2つあり、原則的な方法(原則課税)ともうひとつ、「簡易課税制度」があります。令和8年まではインボイス制度による経過措置(2割特例)が使えますが、その後は簡易課税制度による申告を行う事業者が増えてくるでしょう。
今回の記事では
、①簡易課税制度の基礎知識
と
②インボイス制度に伴う経過措置
について、できるだけわかりやすく説明させていただきます。
なお、
この記事の中では「適格請求書発行事業者に登録したことで免税事業者から課税事業者になった事業者」のことを「登録課税事業者」と呼ぶことにします(制度開始前に登録申請し、令和5年10月1日に登録を受けた事業者を含む)
。
簡易課税制度のことを知って、消費税に対する不安を少しでも取っ払っていきましょう!
■原則課税と簡易課税、どちらがお得?
(1)消費税の申告期限
消費税の課税事業者は、申告期限までに消費税の申告・納付をしなくてはなりません。消費税の申告期限は、個人事業主であれば翌年3月31日、法人であれば法人税と同じく決算月の2か月後です。
ところで、個人事業主の方が通常「確定申告」と呼んでいるのは所得税の申告のことです。
令和5年分の所得税の確定申告は令和6年3月15日が申告期限ですので、消費税申告が必要な個人事業主の方は、所得税と一緒に消費税の申告も済ませてしまいましょう。
(2)原則課税と簡易課税、2割特例
すでに申し上げたとおり、
消費税の計算方法には、原則課税と簡易課税の2つがあります
。原則課税の計算方法は、シンプルにすると以下のようになります。納税額はプラスになれば納付、マイナスになれば還付となります。
課税売上げに係る消費税 - 課税仕入れに係る消費税 = 納税額
この式の「課税仕入れに係る消費税」を控除する部分を、仕入税額控除といいます。
仕入税額控除をするためには、経費の支払いや資産購入時の消費税区分をちゃんと判別し、課税仕入れを把握しなくてはなりません。さらにインボイス制度により、支払い先がインボイス(適格請求書)を発行しているかどうかで仕入税額控除の金額が変わることとなり、さらに複雑になってしまいました…。
この複雑な仕入税額控除を簡略化してくれるのが、「簡易課税制度」です。
簡易課税では、課税売上げに係る消費税額に、事業の種類に応じた「みなし仕入率」を乗じた金額を「課税仕入れに係る消費税」とみなして、以下のように計算します。
課税売上げに係る消費税 - 課税売上げに係る消費税×みなし仕入率 = 納税額
みなし仕入率は下記の図表1のように、6種類の事業区分ごとに設定されています。
図表1 みなし仕入率
|
事業区分
|
みなし仕入率
|
該当する事業
|
納税額の計算方法
|
|
第1種事業
|
90%
|
卸売業
|
課税売上げに係る消費税×10%
|
|
第2種事業
|
80%
|
小売業
|
課税売上げに係る消費税×20%
|
|
第3種事業
|
70%
|
建設業、製造業、農業・林業・漁業、電気・ガス・水道業
|
課税売上げに係る消費税×30%
|
|
第4種事業
|
60%
|
その他の事業(飲食店業など)
|
課税売上げに係る消費税×40%
|
|
第5種事業
|
50%
|
サービス業(飲食店業のぞく)、金融・保険業、運輸通信業
|
課税売上げに係る消費税×50%
|
|
第6種事業
|
40%
|
不動産業
|
課税売上げに係る消費税×60%
|
どの事業区分に当たるかもっと詳しく知りたい方は、下記リンク先をご参照ください。
また、事業区分が複数ある場合は少し計算が複雑になります。たとえば飲食店業の場合、店内飲食は第4種事業となりますが、テイクアウトについては製造業と同じ第3種事業となります。
事業区分が2つ以上あり、1種類の事業が課税売上高の75%以上を占めている場合には、その事業のみなし仕入率を使ってよい、という特例もあります。くわしい計算方法については、下記リンク先をご参照ください。
簡易課税を適用すれば、課税仕入れの判別や支払い先のインボイス確認について考慮しなくてよいので、申告の負担がぐっと軽くなるでしょう。また、給与支払い(不課税)が多いなど、経費に占める課税仕入れが少ない事業者は、原則課税より簡易課税の方が納税額が少なくなります。
ただし、原則課税では消費税が還付されることがあるのに対し、簡易課税ではその計算構造上、還付になることはありません。課税仕入れが多い場合・・たとえば
多額の設備投資をした場合などは、原則課税で消費税が還付されるなら、そちらの方がお得
といえるでしょう。
また、
登録課税事業者のために、制度開始から3年は「2割特例」が設けられました
。2割特例が適用できるか確認したい方は、下記リンク先をご参照ください。
2割特例は、以下のように2割(20%)を用いた簡易な計算式になります。
ところで上記の2割特例の計算式は、みなし仕入率80%である第2種事業の簡易課税の計算式とまったく同じです。そのため、これより高いみなし仕入率90%である
第1種事業(卸売業)は、2割特例より簡易課税で計算する方が納税額が少なくなりますので、簡易課税を適用できるようにしておくとよいでしょう
。
図表2 原則課税、簡易課税、2割特例の計算方法

■簡易課税に必要な手続きは?
簡易課税を適用するには、一定の条件をクリアしておかなくてはなりません。また、いったん簡易課税を適用すると、2年は原則課税に戻せません。ここでは、簡易課税を適用するにあたり、重要なポイントを見ていきましょう。
以下「課税期間」というワードを使いますが、個人事業主であれば1/1~12/31の期間、法人であれば通常は事業年度と同じ期間、と思ってください。
(1)簡易課税の適用条件
簡易課税を適用するには、主に下記の2つの条件を満たしていることが必要です。
【簡易課税の適用条件】
① 基準期間(通常、個人事業者は2年前、法人は前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下である
② 「簡易課税制度選択届出書」を提出期限までに提出している
※その他、高額特定資産や調整対象固定資産の課税仕入れをした場合は上記条件を満たしても簡易課税を適用できない場合があります。これは少し複雑な制度のため、単体で100万以上の課税仕入れをする場合等は税理士に相談してみましょう。
(2)簡易課税制度選択届出書の提出期限
簡易課税の適用条件②「簡易課税制度選択届出書」についておさえておきましょう。
まず
原則として、簡易課税制度選択届出書の提出期限は「適用を受けようとする課税期間の初日の前日」
です。簡易課税を適用したい課税期間が始まってから提出しても、その課税期間には簡易課税は適用できず原則課税で計算し、翌課税期間から簡易課税で計算することになります。
しかし、
登録課税事業者については、制度開始後6年間(令和5年10月1日~令和11年9月30日を含む課税期間)に登録を受けた場合、提出した課税期間から簡易課税を適用できます
。
インボイス制度でやむなく課税事業者となった方は、簡易課税を適用したい課税期間中に届出を出せば間に合います。ここで注意すべきなのは、たとえば
個人事業主の場合、適用したい年の12月中に提出すれば間に合いますが、確定申告する3月に提出すると簡易課税を適用できるのは翌年になってしまいます
。
提出期限は1日でも遅れると適用できませんので、うっかり出し忘れた…!なんてことのないように気をつけましょう。また、
届出は必ず控えを取っておくようにしましょう
。
(3)簡易課税の2年しばり
簡易課税は事務負担を軽減してくれる魅力的な制度ですが、
いったん簡易課税の適用を開始すれば、その後も簡易課税を適用し続ける
ことになります(基準期間の課税売上高が5,000万円を超える課税期間は原則課税となります)。
原則課税に戻したい場合は、「簡易課税制度選択
不適用
届出書」を出す必要がありますが、簡易課税の適用を開始してから2年目以降でなければ提出できません。また、「簡易課税制度選択
不適用
届出書」を提出した場合、原則課税に戻るのは提出した課税期間の翌課税期間となります。
ようするに、
簡易課税は適用開始後、最低2年は適用しなければならず、すぐに原則課税には戻れません。これが「2年しばり」です
。原則課税で計算してみたら消費税が安くなったけど、簡易課税の届出を出しちゃった…ということがないようにしたいですね。
(4)2割特例の事前届出は不要
登録課税事業者は、令和8年までは「原則課税か2割特例」、「簡易課税か2割特例」を課税期間ごとに選ぶことができます。
2割特例については、事前届出は不要
です。また、簡易課税を適用できる課税期間に2割特例を使う場合でも、簡易課税制度選択
不適用
届出書を提出しておく必要はありません。
■簡易課税のメリット、デメリット
ここまでのおさらいとして、簡易課税のメリット、デメリットをみておきましょう。
(1)簡易課税のメリット
-
支払い先のインボイス確認をしなくてよいため、事務負担がかなり軽減される
-
課税仕入れが少ない事業者は、原則課税より納税額が少なくなる
-
卸売業(第1種)は、2割特例より簡易課税がお得
(2)簡易課税のデメリット
-
事前届出が必要で、提出期限までに届け出ておかないと適用できない
-
最低2年は適用しなければならない(やめる場合も届出が必要)
-
多額の設備投資をした場合等、還付が受けられる場合は原則課税の方がお得
■今後のスケジュール
最後に、インボイス制度開始後のスケジュールを確認しておきましょう。インボイス制度の経過措置として、
2割特例の対象期間は制度開始後3年間(令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間)です
。しかし、対象期間内であっても、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると2割特例は使えません。
課税売上高が1,000万円を超えるようであれば、原則課税と簡易課税、どちらを選ぶべきか早めに考えておいた方がよいでしょう。
図表3 今後のスケジュール

■まとめ
簡易課税制度というけれど、全然「簡易」じゃないじゃない!…という声があちこちから聞こえてきそうです。しかし、インボイスの登録をすれば、消費税の申告は不可避です。
インボイス制度を機に課税事業者となり、初めてご自身で申告する方は、まず2割特例により申告をしてみて、そのあと簡易課税について考えてみるのがよいでしょう。また、原則課税と簡易課税、どちらがお得になるかちゃんと知りたいという方は、会計事務所に相談してみることをオススメします。
この記事が、消費税の申告についてもっと知りたいと思う方に、少しでもお役に立てることを祈っております。
関連リンク