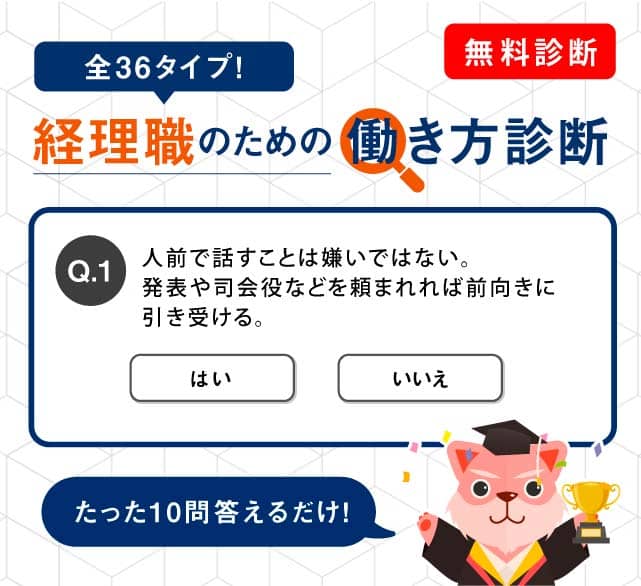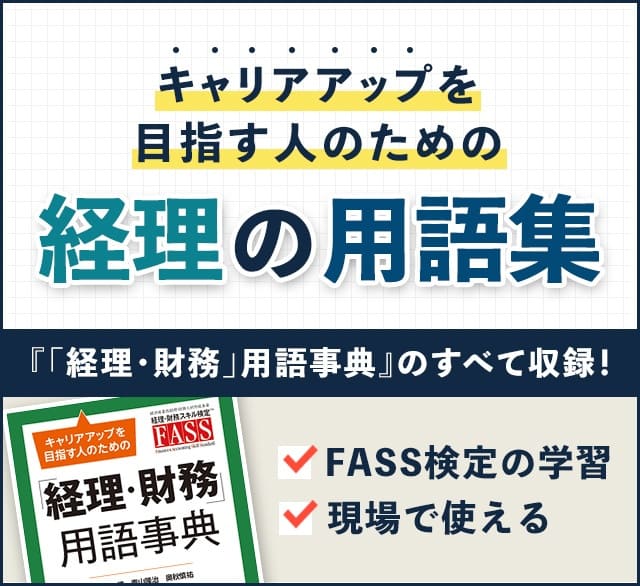1.高度成長期における商品販売
高度経済成長に沸く戦後の経済の中で、最も日本の経済成長を支えた産業は製造業でした。戦後の焼け野原から始まった経済復興は、人々の生活が徐々に豊かになるにつれ、ぜいたく品と言われた家電が一般家庭にも徐々に取り入れられるようになり、そのピークは1964年に開催された東京オリンピックであったといわれています。
この時代、カラーテレビ放送が始まり、「オリンピックをカラーのきれいな画面で見たい」そんな欲求から多くの人がテレビを買い求めたといいます。
2.「ジャスト・イン・タイム方式」と大量生産
今でこそその勢いに陰りが見える日本の製造業ですが、60年代~80年代にかけて繊維、鉄鋼、ハイテク家電の輸出高が上昇し、ついには対米貿易黒字を生み出すまでとなりました。
特にトヨタを代表する日本製の車は性能が高く安いことから、世界中に輸出されるようになりました。大量生産時代の突入です。
限られた人員や資源を有効活用し、売上を上げるには生産高の調整が鍵となります。一般的に大量生産の場合、受注から納品までのリードタイムが長くなると、機会損失を産むことになります。だからといって、やみくもに在庫保有高を増やすことは資金繰りの悪化
(第3回CCC参照)
を招きます。そこで、トヨタでは、各工程で必要な材料を必要な時に必要な分だけ供給することができる
「ジャスト・イン・タイム生産方式」
と呼ばれる生産方法を確立しました。
この方法は、「系列」の各部材供給会社がトヨタ本社からの受注調整に対応することで賄っていました。このように、各メーカーが在庫供給先の関連企業までも抱えることで生産調整を行い、大量生産時代を支えていたのです。
3.バブル崩壊とロングテール
90年代に入り、バブル経済が崩壊すると「物が売れない時代」がやってきました。
これまでの多量生産を続けていけば、大量の商品在庫の処分費用が嵩み、利益を圧迫することになります。系列を抱えた生産体制は、工場の稼働時間の減少を支えるだけの価格維持が必要です。しかし、物が売れなくなれば、価格が下がり、系列会社への発注調整を支えるだけの体力がなくなります。
そこで新興企業から
「ロングテール」
という考え方が生まれます。
すなわち、一過性のトレンドで大量に売り切るのではなく、長くニーズをもたらす商品を長期間に渡って売り続けるという戦略です。

この戦略で、日本国内で最も成功した企業がユニクロです。
トレンドに左右されがちなアパレル業界で、素材にこだわったベーシックな商品のみに絞り販売しました。大量生産で生産コストを抑えても販売期間を長期化することで在庫ロスをなくし、在庫コストを抑えることで安く販売することができるのです。
4.IT戦略と商品販売
それでは、現代の商品販売はどのように変化しているのでしょうか?
現代の商品販売を語る上で最もキーとなるのは「Amazon」の存在です。これまで、商品販売は商品在庫を多量に準備できる資本力があり成立するビジネスでした。
しかし、多様性が求められる現代においては、販売商品においても『みんなが持っているもの』ではなく、『自分だけが持っているもの』が求められる時代となったのです。そのため、
商品を持つ誰もが少量の在庫商品から商品販売を行え、かつ、その少量の商品へのニーズと販売者を、システムにより結びつけることでビジネスとして成立させることを可能
としたのです。
このような時代背景にあたり、着目されたのが
不良在庫の存在
です。メーカーが特定時期に販売できず、不良在庫として切り捨てていた商品の中に特定の「誰か」の宝物が眠っている可能性があるということなのです。Amazonの存在は、この「誰か」の宝物探しをビジネスとして成立させる画期的なサービスであったのです。
5.在庫管理の重要性
このように、これまでの商品販売の歴史は
「在庫との戦い」
の歴史であったといえます。
利益の最大化においては、「適正な価格」で「適正な数」の商品を販売することが重要ですが、そのうえでこれまで以上に在庫管理の重要性は増しています。
店舗での販売だけでなく、多種多様なECサイトや通信販売など、販売チャネルはこれまで以上に存在し、距離に関係なく多くの人にリーチできる可能性が広がっており、24時間販売することも可能です。そのため、在庫数量を把握できていないことは、多くの機会損失につながるのです。
また、過剰在庫はキャッシュフローのマイナス要因です。そのため、何が売れる商品なのかを見極め管理することが重要なのです。
6.在庫管理のミライ
(1)在庫管理の今
これまで、在庫管理はデータベース等で個別管理され、出入庫による受け払いは手作業により確認を行ったうえでその内容をデータ入力して処理してきました。
小売業などの大型の店舗ではPOSレジの導入により、バーコードで出入庫が管理できるシステムが確立されており、そのデータがそのまま会計データに反映されています。
しかし、IT化が進む中でも実地棚卸だけはいまだに人が目で見て個数を数えることが現実に行われています。これは、会計監査においても同様で、サンプルとして何点か数えてみて棚卸の正確性の判断を行っているのが現状なのです。
(2)在庫管理の未来
POSシステムの登場により、出入庫管理はかなり楽になりました。しかし、実地棚卸はどうでしょうか?ここでいくつかの例を見ていきましょう。
一つの答えとして、ドローンの活用が挙げられます。
大手物流会社の日本通運では、ドローンによる在庫管理の実証実験を行っています。これは、倉庫内でドローンがパレットの位置関係をレーザーで探知し、商品タグを読み取り、在庫数量を把握するという手法です。
また、海外ではドローンにAIを搭載し、ドローンが撮影した画像から在庫数量を自動で把握するという方法も用いられています。
このような物流における革命は、巨大企業Amazonへの対抗策として講じられているものですが、そのAmazonもAIによる画像解析を用いた無人店舗『Amazon Go』を全米各地で運営しています。
『Amazon Go』では、在庫管理にとどまらず、顧客の動きもAIで解析します。買い物客がかごに商品を入れただけで購入商品をAIが瞬時に把握し、その商品を持って出口ゲートをくぐっただけで、事前登録してあるカードで決済を行います。つまり、購入から決済まで人の手を介すことなく、すべてが完全自動化された店舗となっているのです。これは、
単に業務効率を上げるだけでなく、膨大な購買データが自動で生成されるため、マーケティングデータとしての活用も可能となっている
のです。
このように、AIの技術は『商品』という物理的な物を介在する分野においても人の手を介在しないで完結できる方向に進んでいます。
また、これらの購買情報がシステム化されることにより、新たな商品開発や販売チャネルの開発へとつながっていきます。
私たちの仕事は作業から創造へ。
在庫がもたらす情報に耳を傾けて、新たなチャンスに繋げていく力が今、まさに求められているのかもしれません。
関連リンク