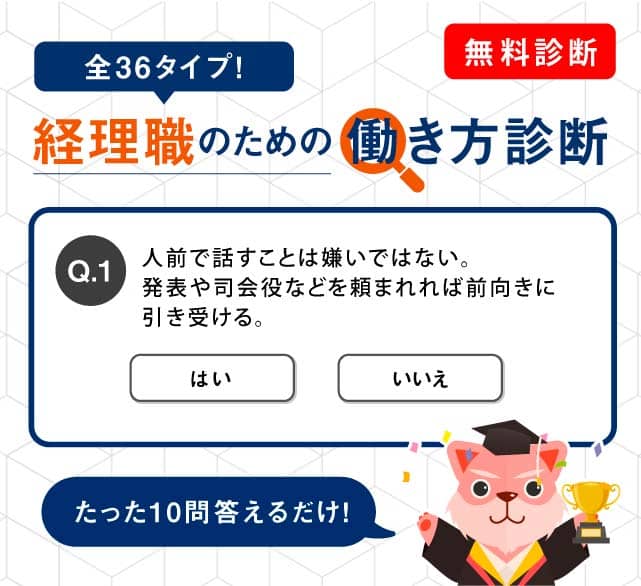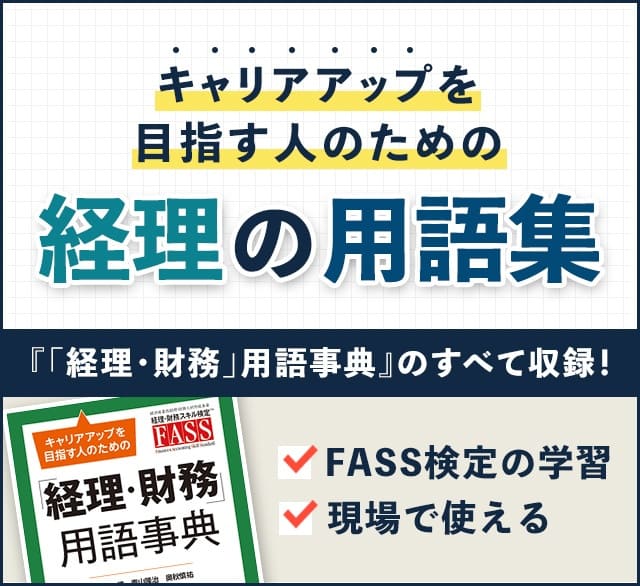1.経理の現場と税務申告
コロナウィルスが問題となった時期に決算期を迎えた企業は、テレワーク環境を余儀なくされた中で、税務申告についてどのように対応していたのであろうか。
この点については、多くの企業で担当者が出社し、これまでと同様に申告業務を行っていたという意見があった。というのも、テレワーク環境を整え、業務をオンラインで行っている企業にとっても、限られた担当者が一年に一度しか行わない税務申告については、中小企業と同様のインストール型の税務申告用ソフトを使うのが一般的であるため、
利用できるPCに制限がある
ためである。
また、税理士による代理申告を行う中小企業ではあまり想像できないが、多くの企業でこれまでe-Taxの利用は少なく、税務ソフトを利用して作成した申告書を紙にプリントし、添付書類とともに提出している状況にあった。
2.電子申告義務化により変わる税務
こうした状況を踏まえ、平成30年度の税制改正において資本金額等が1億円を超える法人については、電子申告が義務化されることとなった。
これにより、令和2年度からの運用に備え、多くの企業がe-Taxに対応した税務システムへの変更を余儀なくされることとなった。テレワーク環境下で税務に関しても支障がなかった一部の企業では、e-Taxでの申告が可能な環境であったことが業務を進めることができた理由であるという。
3.e-Taxと電子証明書
ここで、e-Taxの仕組みを簡単に見ていこう。
e-Taxは、正式には「
国税電子申告・納税システム
」といい、その運用は2004年2月から開始されている。デジタル化の遅れが問題視される行政手続きにおいて、すでに15年以上の実績があるシステムである。
e-Taxを使えば、郵送で行われていた申告書などの税務書類の提出を電子データで送付できるため、スピーディーな申告が可能となる。
この電子データでの送付の際に問題となるのが、
押印に代わる認証システム
である。
代表者の押印ができない電子データをe-Taxで送付する場合には、正しいデータであり、改ざん等がされていないことを証明するため、
データの送付の際、「電子証明書」を添付しなければならない
。
この電子証明書は、「書類の送信者が誰であるのか?」を特定する情報である。個人の場合「マイナンバーカード」のICチップ内に格納されているため、マイナンバーカードがあれば電子申告が可能であるが、法人の場合には法務局から「商業電子認証ソフト」を利用し、発行することができる。
 (法務省民事局「商業登記電子証明書 は・じ・め・て ガイド~制度の概要~」)
(法務省民事局「商業登記電子証明書 は・じ・め・て ガイド~制度の概要~」)
4.電子証明書とe-Tax利用のハードル
こうした電子証明書を利用した行政手続きはe-Taxに限らず、下記のようなさまざまな分野で利用されている。

国税庁の資料によると、
令和元年度のe-Taxの利用率は、すでに法人税や消費税の申告に関しては80%を超えている
(国税庁「令和元年度におけるe-Taxの利用状況等について」参照)。
しかし、こうした電子証明書の利用に関する手続きは簡単であるとは言えない。
証明書を取得するだけでも申請用のソフトがあり、郵送による書類の送付も行わなければならないが、さらにe-Taxを利用する際にも税務署への開始届の提出やe-Taxソフトのダウンロード、利用者情報の登録など利用するまでに行うべきハードルが高い。また、利用できるOSやブラウザソフトも限られているため、MACユーザーなど一部の利用者に制限がかかってしまう。こうした使い勝手の悪さがこれまで嫌煙されてきた理由である。
5.DXと行政のデジタル化
こうした点を踏まえ、個人の確定申告に関しては、電子証明書による認証を行わず、ID・パスワードによる方法を平成31年1月から一時的に取り入れており、システム的な手軽さとスマートフォンでの申告が可能なこともあり好評を得ている。
手続き開始時には、IDの発行を求め、多くの納税者が税務署に殺到したというから、利用者にとって使いやすいものであるか否かは、デジタル化にとって最も重要な課題であることが証明されているのである。
 (国税庁「e-Tax利用の簡便化の概要について」)
(国税庁「e-Tax利用の簡便化の概要について」)
折しも国はデジタル庁創設に向け、多くの行政手続きを見直している最中であるが、これまでの行政主体の「使わせる」デジタルではなく、
利用者が「使いたい」デジタルへの改革が求められる
。これには、誰もが簡単に使えるシステムが不可欠なのである。
これは、
単にこれまでのやり方をデジタルに置き換えるのではなく、初めからデジタルを前提とした方法を新しく構築するDX(デジタル・トランスフォーメーション)が不可欠
なのである。
毎年、確定申告の時期には多くの納税者が税務署に殺到するが、こうした非効率で、密となりやすい環境はデジタルの力で変えてかなければならない。Withコロナ時代は、デジタルの力で我々の日常をより利便性の高いものに変えていくWithデジタルの時代となるであろう。
関連リンク