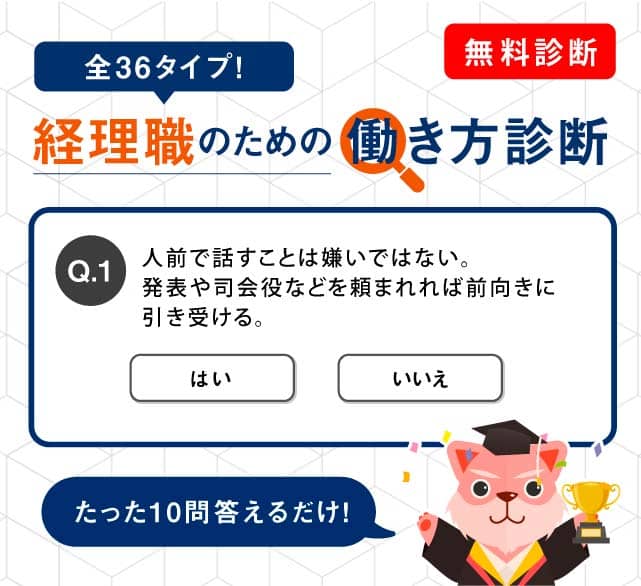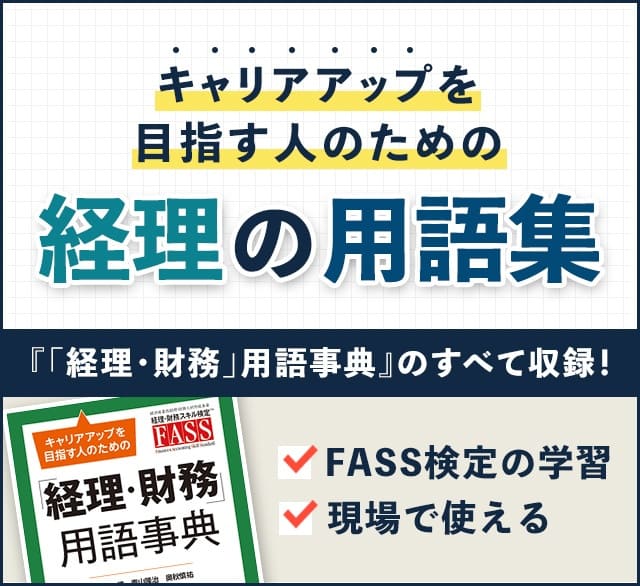2020年、猛威を振るったコロナウィルスの存在は我々の生活に多くの問題を突きつけた。しかし、そのことにより、2020年末の現在、人々の生き方が大きくシフトしていく手応えを残している。
このコラムは、企業経理部への取材を元に執筆した。
企業経理の現場における実際の声
を通じて、Withコロナ時代の経理の在り方を考えていきたいと思う。
第1回 アンダーコロナのテレワーク実態~テレワークを阻むセキュリティー問題~

2020年12月1日 小島 孝子
目次
1.テレワークの準備はコロナ前に進んでいた?
2020年の初めから話題が出始めたコロナウィルスであるが、我々日本人の多くがその存在を認識したのはダイヤモンド・プリンセス号が横浜港に帰着した2月であった。
コロナウィルスが猛威を振るいだし、いよいよ多くの人がその恐怖を理解しはじめた3月、国の要請もあり、大手企業の多くがテレワークに切替え出していた。
そんな中で、いち早くテレワークに切り替えができていた大手企業にはある特徴があった。それは、この騒ぎが起きる数か月以上前からテレワークを進めていた事業者だ。 テレワーク化が進んでいた要因、それこそがなんと「オリンピック」 なのである。
2.オリンピックとテレワークの実証実験
2017年7月から、国は2020年のオリンピックの開催予定日であった7月24日を 「テレワーク・デイ」 と定義し、オリンピックまでにテレワークの本格的な導入を目標としていた。これは、オリンピック期間中の都市部の交通量を減らすことを目標としていたが、長時間労働がもたらす多くの不幸な事件を機に、テレワークという働き方自体の定着も目指していた。
2017年の実証実験には自治体を含むさまざまな業界から922社もの企業が参加し、実に6.3万人もの人がテレワークを体験した。
そこでは、今でこそ当たり前となった、人がいなくなったオフィス、テレビ会議の様子、自宅での作業風景が、あたかも未来の企業の姿であるかのように紹介されている。

これにより、もっとも効果の高かったとされる東京メトロ豊洲駅ではピーク時(午前8時)の乗客が 前年同日に比べ10%も減少 し、その効果が確認されている。
3.実感のわかないテレワーク
こうした取り組みに積極的に参加していた企業にとっては、2020年にテレワーク化されていることは既定路線であり、今回お話を伺うことができた 大企業のほとんどがコロナ前の時点ですでに週2~3日通勤が実施されていた という。国によるテレワークに向けた助成金の施策も行われ、システム環境などをテレワークに向け整えていたのである。
これに対し、中小企業を含む多くの企業は、コロナ前においては「テレワーク」という言葉すらどこか遠くの国の出来事のようであった。
特に経理を取り巻く環境においては、法律に基づく帳票が仕事の前提であり、自宅で行える環境になかった。そのため、緊急事態宣言を期に、突然テレワークを強制された多くの企業がすぐに対応することができなかったのだ。なぜなら、そこにはセキュリティーという大きな障壁が立ちはだかっていたからである。
4.セキュリティーとテレワーク
多くの企業にとって、会社外部で仕事をさせることに対する抵抗感の強い最も大きな理由が セキュリティーの問題 である。
近年、個人情報保護の問題は大きな社会問題となることも多く、一度大きな流出が起きてしまうと株価にも影響する大損害となり兼ねない。
そのため、各企業はより強固な社内LANを構築し、外部からのアクセスを制限することでこれを防止してきた。これが事前にリモート環境の準備ができていない企業にとってはネックとなってしまったのだ。
5.テレワークの肝は外部に情報を持ち出さない処理
しかし、オリンピックを目指し、準備を進めていた企業にとっては、すでにこの問題もカバーされていた。
具体的には、サーバー側に保存されたデータをクライアント端末側に送られた画面情報だけで入力等の操作を行うことができる 仮想化デスクトップ という方法がある。
これを採用することで、データは社内に設置されたサーバーから持ち出すことなく、外部からでもデータ入力が可能となるだけでなく、クライアント端末ではデータを持たないため、 仮に端末の盗難や紛失があった際もデータ流出することがない 。これに特化したシンクライアント端末はクライアントPCにHDDすら持たないため、データが保存されることはなく、セキュリティー面で注目されるシステムである。

6.クラウド化が進む経費処理
また、立替経費の処理については、多くのクラウドベンダーによってより利便性の高いシステムが開発されている。大手メーカーや広告代理店など多くの企業で導入されているConcurでは、従業員がスマートフォンで撮影した画像をシステムに取り込みそのまま経費申請ができるだけでなく、他社サービスとの連携機能により、suicaの情報から交通費の精算をできたり、タクシー会社の配車アプリと連携させることで予約から経費申請までをシステム内で完結することができる。
しかも、データはクラウド内にあるため、経費申請だけでなく、上長による承認作業や内部監査に関してもテレワーク環境で行うことができるのである。
7.業務プロセスの簡素化を阻む予算の壁
もちろん、これらの システムを導入するには多大な予算がかかり、経理を含む間接部門への予算配分の少なさという問題は、大手金融機関ですら生じている 。しかし、システム導入はテレワークの肝である。オリンピックに向けたテレワーク助成金は、コロナ対策のための助成金に形を変えてすでに公募が行われている。コロナ禍を向こう10年の方向性を見据える転換期として捉えると、まさに絶好の機会なのである。
数か月前までは遠い未来の出来事であったテレワークであるが、技術的な問題はもうすでに整えられている。
コロナウィルスはしばらく猛威を振るうであろう。Withコロナ時代とは、私たちの日常をデジタルの力でより人間らしく充実した世界へと再構築すべき世界なのかもしれない。
関連リンク
- 執筆者プロフィール
-
金子 智朗(かねこ ともあき)
コンサルタント、公認会計士、税理士1965年生まれ。東京大学工学部、同大学院工学系研究科修士課程卒業。日本航空(株)において情報システムの企画・開発に従事しながら、1996年に公認会計士第2次試験合格。プライスウォーターハウスコンサルタント等を経て独立。現在、ブライトワイズコンサルティング合同会社代表社員。
会計とITの専門性を活かしたコンサルティングを中心に、企業研修や各種セミナーの講師なども多数行っている。名古屋商科大学大学院ビジネススクール教授も務める。
- 著書
- 『MBA財務会計』(日経BP社)
『「管理会計の基本」がすべてわかる本』(秀和システム)
『ケースで学ぶ管理会計』(同文舘出版社)
『新・会計図解事典』(日経BP社)
など多数。