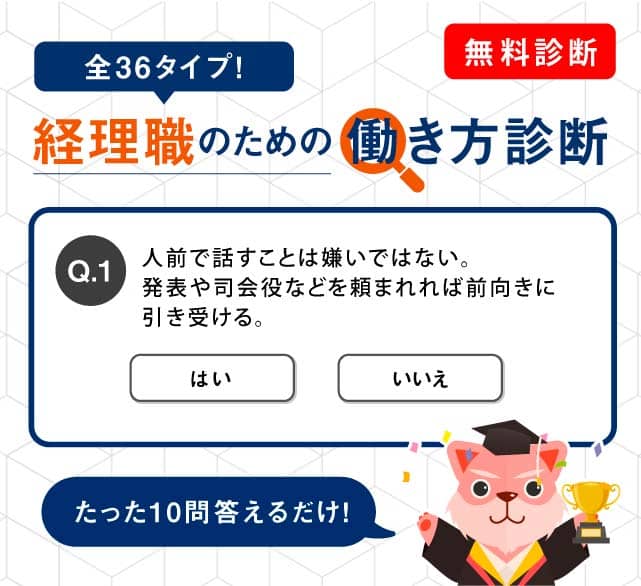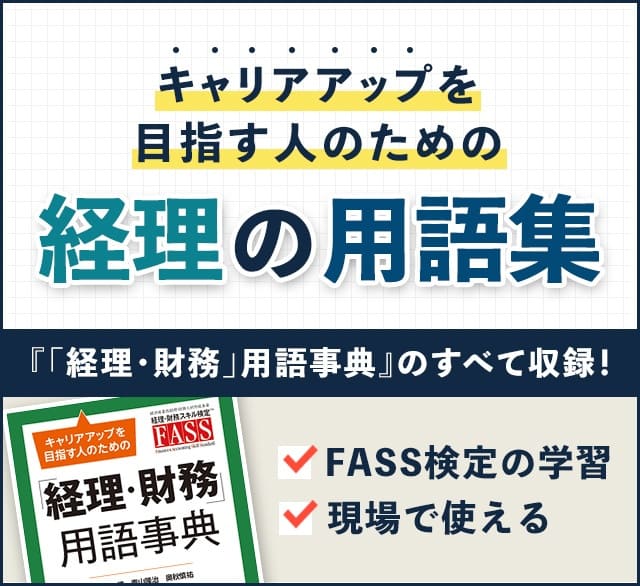コロナウィルスの蔓延が深刻な社会問題となってきた2020年春。日本の多くの企業が決算期を迎える3月は例年、経理現場においても年次決算を迎える重要な時期である。
そんな中、2020年4月7日、政府の発令した緊急事態宣言により、これまでのような経済活動に制限が加わるようになった。
具体的には、外出自粛の要請に応じ、混雑する通勤電車での出勤を改め、これまで努力目標とされていたテレワークへの強制的な転換が求められていたのだ。これにより、決算業務は多くの企業がテレワーク環境の中手探りで業務を行う事態となったのだ。
決算は、そして、その後の会計監査や株主総会はどのようになったのか。2021年1月7日、ふたたび一都三県で緊急事態宣言が発令となるなか、経理現場で奮闘する職員の声も含めて見ていこう。
1.政府の対応とそれに伴う監査への影響
外出自粛の要請を踏まえ、内閣府は2020年4月17日、「企業内容等の開示に関する内閣府令」をいち早く改正し、2020年4月20日から2020年9月29日までに提出が求められる開示資料の提出期限を一律2020年9月30日まで延長することを決めた。
これにより、定時株主総会の日程を後ろ倒しにできることなったわけであるが、実際のところ、開示が遅れたケースはあるのであろうか?
東京商工リサーチの調べによると、上場企業2406社のうち、従来の予定から開示を送らせた企業はわずか495社、
全体の13.1%にしか過ぎなかった
。
多くの企業が混乱の状況化にあってもスケジュールを順守していることは日本らしさともいえる。しかし、実態は驚くほどスムーズに作業が行われていたという。
2.すでに経理はテレワーク可能な業務であった?!
上場企業数社の経理担当者に実際に話を伺うと、テレワークにより、決算や監査業務に支障を来すようなことはとりわけ見当たらなかったそうである。
通常の経理業務においては、第1回でも見てきたように、すでにテレワーク環境が推奨されていたことから、決算においてもその延長に過ぎず、それぞれが粛々と自宅で作業を進めており、
スケジュール的にはあまり支障は出なかった
という。開示が間に合わなかったという企業においても、自社の都合というよりも監査法人側の対応の遅れがその理由であった。
経理業務において、テレワークを阻む理由として主に押印や紙の請求書による支払業務などが挙げられたが、これらはすべて外部との取引である。外部との日常処理から離れた決算業務は、すでに外部との取引が終わったあとの、GL(総勘定元帳、General Ledger)上に集められたデータを確認、修正していく作業であるのだから、当然と言えば当然の話である。
働く場所が変わってもその業務内容に影響はなかった
のである。唯一影響が出たというコミュニケーションの問題はこの先の回で詳しく見ていくこととする。
3.監査法人の対応はどうなっていたのか?
また、会計監査においても、通常の監査のように狭い会議室内にパソコンを持ち込み、作業を行うことはまさに政府が注意した三密(密集、密閉、密接)環境に当たる。そのため、原則としてBIG4などの大手監査法人では、
企業に来社することはなく、電話やオンライン会議システムなどを用いて監査を行っていた
という。
ただし、対応する側の企業は監査法人の質問や資料提出にこたえるべく、交代で出社を行い対応していたというから、この点は今後、課題が残る点である。
4.株主総会の運営はどうなっていたのか
また、株主総会については、決算開示に関する内閣府からの発令に応じて、経済産業省及び法務省の連名で
「株主総会運営に係るQ&A」
を発表している。
これによると、新型コロナへの影響を踏まえ、株主への総会の参加自粛を訴えることは可能であるとし、書面等により事前に議決権を行使できる環境下であれば、会場に出席しなくても決議の成立要件は満たすものとされている。
すなわち、
通常通りの運営を行ったうえで参加者を制限しても権利行使に問題はないとしている
。これに則り、ほとんどの上場企業では通常通りの総会の開催を行ったそうである。
5.オンラインによる株主総会の運営は可能であるのか?
それでは、通常の会議のようにオンラインでの株主総会の開催はできるのであろうか?
株主総会の機能には、議案に関する承認可決以外に質問や議事の提起があり、議案に関する株主の権利行使は前述のとおり事前に書面等で行うことができる。しかし、参加によるリアルタイムでの議決権の行使など、本当の意味でのオンライン株主総会を行うには、
システムの開発コストの問題だけではなく、法律上の問題が生じる可能性がある
。リアルの参加者と同一条件でないと議決権の無効や取消の対象となってしまうのだ。
これを最大限に配慮した株主総会のフローを検討し、開催したあるソフト会社においても、この「リアルと同一条件」という難題に配慮するため、多額の予算をかけ、綿密に準備をしてきたが、それでも明確に合法であるとは言い難い状況だという。今後、デジタル化政策を進める政府の対応が待たれる点であるといえる。
 (参考:攻める総務by ITmediaビジネスONLINE 「株主総会のオンライン化、立ちはだかる“法律の壁” 先駆者・富士ソフトの挑戦記)
(参考:攻める総務by ITmediaビジネスONLINE 「株主総会のオンライン化、立ちはだかる“法律の壁” 先駆者・富士ソフトの挑戦記)
このように、多くの上場企業ではこれまで進めてきたテレワーク対応の成果がまさに発揮された結果となった。今後、決算業務だけでなく、監査や株主総会も民間ベンダーなどのシステム開発により、さらなる利便性の向上が見込まれるであろう。
これに対し、これまで腰の重かった政府もデジタル庁創設を目指し、新たな国家戦略を構築している最中にある。コロナウィルスとの共存は、民官共闘の新しい国造りの概念となっていくであろうことをここで改めて確認しておきたい。
関連リンク