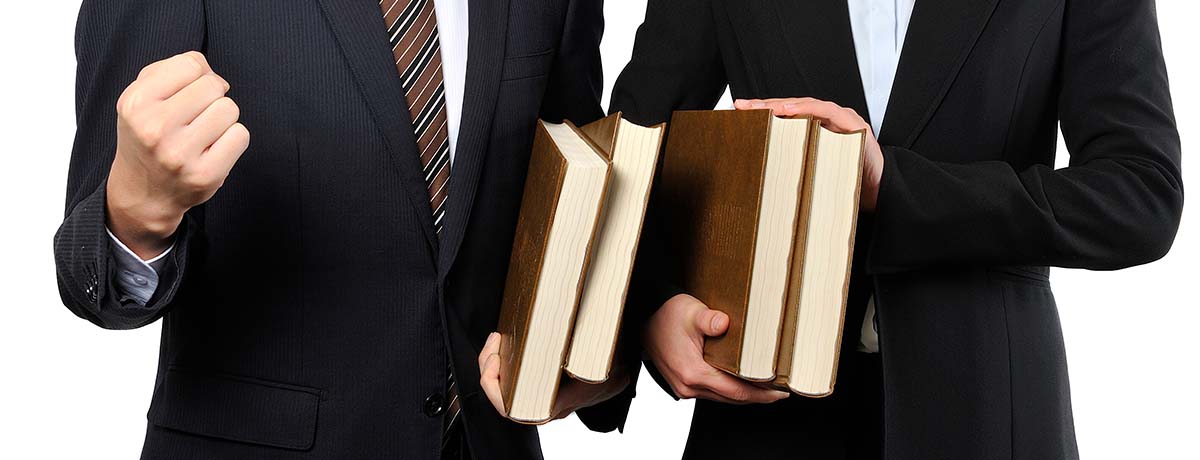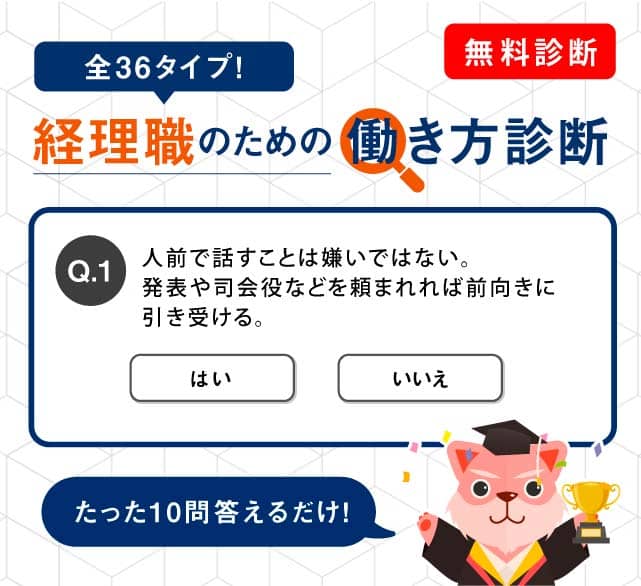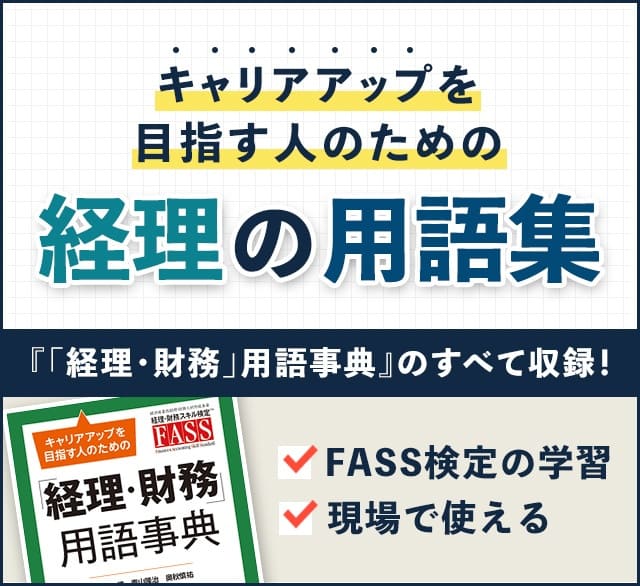■日商簿記1級と公認会計士の根本的な違いとは
(1)国家資格と検定資格
公認会計士は、歴とした
国家資格
になります。監査業務を行うことをできる唯一の国家資格であり、会計・監査の知識について国のお墨付きを得ることができます。
日商簿記1級は、
日本商工会議所が主催する検定資格
です。つまり自身の知識のレベルの程度を確認するとともに、他者に客観的にそれを証明するために付与される資格ということになります。
(2)資格の獲得を目指す受験層
受験層においても大きな違いがあります。
公認会計士資格は、例外はありますが、大学生以上の層が、資格所得に専念し、大半は人生をかけて挑戦する資格になります。ほとんどの挑戦層は
大学生か、大学を卒業した者
となります。特に大学生で資格を取得した人は、学生時代の時間のほとんどを資格取得に費やしたという人がほとんどです。
他方で簿記検定試験は、簿記関連の知識をどの程度身につけているかの検証のための資格です。このため、公認会計士試験が就職浪人してまで取得を目指すものが多数いるのに対し、簿記検定の挑戦者の年齢層は幅広になります。
高校生から社会人まで何かを行いながら目指す試験
ということができるでしょう。
(3)試験の相違
日商簿記1級は年2回実施される試験です。商業簿記、会計学、工業簿記、原価計算の4科目で構成され、合格ラインは正答率70%以上が必要であり、1科目でも40%を下回ると不合格になります。これは一見シンプルに見えますが、
実は非常に厳しい合格条件
と言えるでしょう。
一方、公認会計士試験は二段階制を採用しています。公認会計士の試験方式は「1次試験」と「2次試験」に分けられています。公認会計士の
1次試験では短答式の試験が行われ、2次試験では論文式の試験
が行われます。短答式試験は年2回、論文式試験は年1回という頻度で実施され、科目合格制度により段階的な合格が可能です。
(4)学習内容の深度と広さ
公認会計士試験は、簿記検定の商業簿記、会計学、工業簿記、原価計算の範囲を含みます。しかしながらその範囲でも
公認会計士試験の方が圧倒的に問題の難易度は高い
です。
特に差があるのが理論問題。また、簿記や原価計算の計算についても、日商簿記1級では基礎的な論点にかかる問題が出題されますが、公認会計士試験では基礎的な論点の問題はほとんど出題されません。
日商簿記1級では各論点の基本が問われるのに対し、公認会計士では実務指針や現行の会計基準等の背景にある考え方を踏まえての対応が要求されるため、単なる知識の量の違いではなく、
思考の深さも問われる
ことになります。
(5)業務の本質的な違い
日商簿記1級は
会計・経理を担当する仕事
に関連して活かされます。他方、公認会計士は独占業務である
監査を中心とした専門業務
に従事します。
つまり、日商簿記1級の資格取得を通じて連結財務諸表を作成する際に必要な知識を得ることができますが、実務において連結財務諸表を作成するにあたって簿記1級が必須ということはありません。しかしながら、連結財務諸表を作成するにあたっては、やはり簿記1級程度の知識を備えていることが必要です。
他方、公認会計士が行う監査は、企業の財務諸表が適正に作成されているかを第三者として検証する業務であり、
監査を行うためには必須の資格
です。公認会計士は、連結財務諸表を中心に監査意見を出すことから、連結財務諸表の作成プロセス、論点について精通していなければなりません。
企業が作成してきた連結財務諸表を批判的に検証するといったことが可能になるのは、前提として連結財務諸表の作成過程を相当程度把握していなければならないので、当然に簿記1級程度の知識は前提となります。
■転職市場における現実的な価値評価
(1)日商簿記1級の市場価値の実態
日商簿記1級は難関資格と認知されているため、就職・転職においてその知識と向上心は高く評価されます。大手企業の経理部門では、連結財務諸表を作成することが必須であることが多いため、日商簿記1級レベルの知識や技能が求められますが、そのようなスキルを持った人材はかなり不足しています。
筆者自身、上場企業の経理部で採用担当をしていたことがありますが、
日商簿記1級を保持した応募者は一人も現れませんでした
。このように人材不足の状況においては、日商簿記1級を持っていることは転職希望者にとって追い風となるでしょう。
(2)公認会計士の圧倒的な市場優位性
大手監査法人の初任給は30万円以上は間違いなくあり、入社7年目で年収1000万円を超える場合が多くあるので、年収アップを目指す方にはおすすめの資格と言えるでしょう。この数字は日商簿記1級取得者との明確な差を示しています。
さらに重要なのは、公認会計士のキャリアの多様性です。監査法人での経験を積んだ後、一般企業のCFOやコンサルティングファーム、投資銀行など、多様なキャリアパスが開かれています。
これは、公認会計士資格が、経理分野に限定されず、監査、会社法、経営学など関連する分野も相当程度学習することで付加価値があること、監査の経験が「あるべき企業の姿」を見ているという知見が期待されているからと推測しています。
ただ、
公認会計士資格を有していても経理実務にすぐに就けるかについては疑問符
が残ります。採用する側の経理部門の方は経理実務のプロであることは間違いはないのですが、必ずしも公認会計士資格について深い理解があるとは限らず、むしろその逆の方が多いでしょう。監査実務の経験があっても経理実務の未経験者に経理実務を任せることができるのか疑問符を持つことになるのは当然と思うべきです。
(3)実務経験と資格の相互作用
結局のところ、転職市場では、実務経験を問われる場合がほとんどでしょう。
経理実務の経験を得ることを目的として、違う職種から経理業務の世界への転職を考えている場合は、
まず経験を積むことを最優先して一日も早く転職することをおすすめ
します。資格だけでは限界があり、実務経験との組み合わせが真の市場価値を生み出します。
他方で、違う職種から経理業務の世界へ転職するには、日商簿記検定資格を得ることは必須ではないかと考えます。未経験者であっても、日商簿記検定資格は、経理職に転職する際の希望者の本気度を測る重要なバロメータになるからです。とりあえず日商簿記2級程度は取らないといくら経理の人員が不足しているといっても経理責任者が未経験を採用したいと思わないでしょう。
座学だけでも日商簿記1級を持っていると、さらに有利になるのは言うまでもありません。
■効率的なキャリア戦略の立て方
日商簿記1級と公認会計士資格を取るという点に絞って取りやすさを考えるならば以下の2パターンが考えられます。
(1)パターン1:段階的アプローチ
日商簿記1級から始めるアプローチには確実なメリットがあります。1級を取得することは簿記と管理会計論について
公認会計士講座の内容を先取りで学習することと同じ効果があります
。その結果、公認会計士試験の合格への見通し及び自信がつくというメリットがあります。
このアプローチは特に、会計の適性を確認したい人や、現在の仕事を続けながら段階的にスキルアップしたい人に適しています。簿記や会計業務に知識の裏付けを得たい、少しずつステップアップを目指したいという人にとって、日商簿記1級取得を目指すという選択はよいと考えられます。
(2)パターン2:直接チャレンジアプローチ
公認会計士試験を受ける決心が固まっているのであれば、日商簿記1級は受ける必要はありません。この理由として、日商簿記1級でよく出題される範囲は公認会計士試験では基礎的な論点にすぎず、
回り道になってしまう
点が挙げられます。
公認会計士を目指すことを決めている場合は、簿記講座ではなく
最初から公認会計士講座を申し込むことがおすすめ
です。なぜなら、公認会計士の資格取得の道程から見ると簿記の論点は必須の項目の一つとして位置づけられ、その上、公認会計士試験合格へ最短距離で学習することができるからです。公認会計士試験合格間近という段階であれば、日商簿記1級の取得は容易になります。
■具体的な転職戦略とキャリア設計
(1)日商簿記1級を活用した転職先の選び方
日商簿記1級を活かせる仕事として、最もオーソドックスなのが
「上場企業の経理部門」
です。未経験から転職するのであれば、私は上場経理が最もオススメだと感じます。上場企業の経理は、制度対応が充実しており、体系的なスキルが身につきやすい環境にあるからです。
(2)年収と待遇の現実的な期待値
日商簿記1級があると「実務経験なし」でも好待遇で応募できる求人が多く、日商簿記1級の価値の大きさが分かります。具体的には、未経験でも年収350-500万円程度からスタートできる求人が多く見られるようです。
ただし、経理・会計業界の多くの求人が必須資格を日商簿記2級としています。そのため、就職活動や転職活動で応募できる求人の数を増やすという観点では、
わざわざ難易度が高い簿記1級の取得を目指す必要はない
ともいえるかもしれません。
(3)公認会計士合格後のキャリアパス
公認会計士試験に合格した場合は、ほぼ確実に監査法人への就職することになります。そこで数年間の実務経験を積んだ後、以下のようなキャリアパスが開かれます。
-
一般企業の経理・財務部門での管理職
-
コンサルティングファームでの専門職
-
投資銀行や投資ファンドでの分析業務
-
独立開業による会計事務所経営
-
上場企業のCFOやCEOなどの経営陣
これらの選択肢は、日商簿記1級取得のみでは到達困難な領域です。
■まとめ
日商簿記1級と公認会計士、どちらを選ぶべきかという問いに対する答えは一つではありません。
重要なのは、あなたの現在の状況、将来の目標、そしてリスク許容度を総合的に考慮すること
です。
会計の世界で長期的に活躍したいと考えているなら、公認会計士を目指すことをお勧めします。公認会計士試験の勉強をしていてある程度のレベルに行けば日商簿記1級は無対策で対応できるからです。
一方で、現在の仕事を続けながら段階的にスキルアップしたい場合、公認会計士資格にこだわりがない場合は、簿記3級、2級、1級という段階的な取得が賢明な選択となります。
最も重要なのは、
一度選択した道を継続する意志と、変化に対応する柔軟性を持つこと
です。会計の世界は常に進化しており、継続的な学習と成長が求められるということを認識してください。
あなたの会計キャリアが成功に向かうことを心から願っています。どの道を選択するにしても、その選択を信じて全力で取り組むことが、最良の結果をもたらすのです。
関連リンク