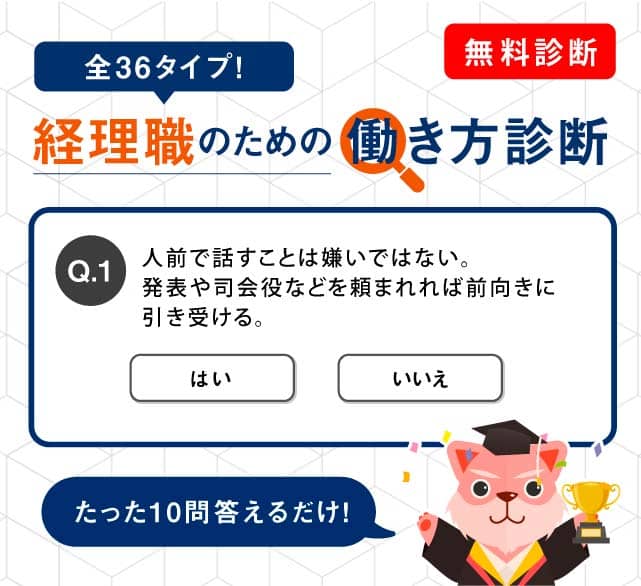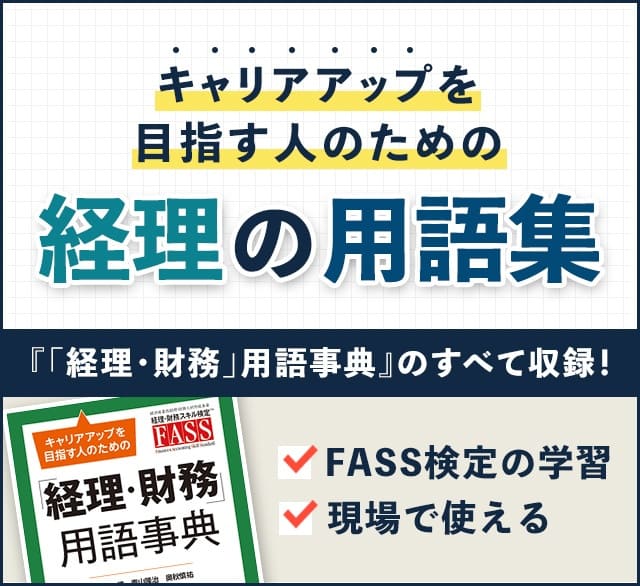平成の時代に何があったのか?
日本にとって厳しい冬の時代ともいえる平成の時代は、会計の世界においてはまさに「変革」の時代であったといえます。この30年、われわれを取り巻く環境はどのように変わっていったのでしょうか。
バブル期を経て発展した多くの企業が事業規模を拡大していくにつれ、企業グループを形成し発展していくことから「連結会計」が生まれました。また、国際化の波はさまざまな日本独自の会計基準を世界共通の基準に合わせていく必要性を生み、今まさに「IFRS(国際財務報告基準)」といった一つの国際基準にコンバージェンス(収斂)するよう、変革のさなかにあります。
われわれが日々行う経理業務に関しても旧時代の手書きやいわゆる「オフコン」を主流とした「コンピューター会計」から、Windows95の登場以降、誰もが手軽に個人のパソコンで会計処理ができるような会計ソフトが多数開発され、経理業務そのものの在り方が大きく変わった30年であったといえます。また、技術革新はAIの登場により、経理業務そのものの在り方さえ変えようとしています。
今回は「売掛金管理」業務についてのお話をしますが、売掛金管理の業務としての重要性を確認するために、まずは企業活動まで広げて見ていきましょう。
1.売掛金管理業務の現在
(1)「売上」と「不良債権」
企業活動を行うための源泉は
「売上」
です。右肩上がりの成長を続けたバブル時代、売上の規模を拡大していくことが企業規模の成長ととらえられてきました。
しかし、数字だけの積み上げを重視した結果として行った無理な売上の増加は、経済成長が止まった瞬間、回収不可能な債権を多額に積み残してしまいました。これが
「不良債権」
と呼ばれるものです。不良債権は会社の経営にどのような弊害をもたらすのでしょうか。
(2)企業の活動サイクルと売掛金
もう1人は上場企業の社長の方です。この方は私と雑談している中で次のようなことをおっしゃっていました。
企業活動を行うためには、資本が必要となります。
「資本」とは、活動のために必要な資金(お金)を指します
。企業活動を行うにあたり、まずこの活動の原資となる資金を集め、商品や設備といったさまざまな資産に変えていきます。こうして現金から商品に変わった(仕入れた)資産を元に企業活動が展開され、そこから売上を産み、さらにその資金を次の仕入れに充て循環させていくことで企業は成長していきます。

したがって、通常の業務サイクルでは、
売上代金の回収よりも先に仕入代金の支払いが生じます
。そのため、銀行などから借入金により一時的にこの不足する資金を調達したり、仕入代金そのものの支払いを掛け取引として支払いのタイミングを遅らせたりして、このサイクルを循環させます。このサイクルの中で、
売上代金が実際に入金されなければこの循環が断ち切られてしまい、最悪な場合、仕入れ代金の決済や銀行への借入金の返済資金が不足し、倒産となってしまいます
。
このように、売上があり、決算書上の利益が生じていても資金ショートにより、倒産してしまうことを
「黒字倒産」
といいます。
(3)売掛金管理の基本的な方法
売掛金管理は原則として取引先ごとにあるマスターデータをもとに管理をしていきます。これは、簿記の学習で行った「売掛金元帳」のイメージそのものです。

会計ソフトでの記帳データの入力では、「売掛金」勘定にマスターデータの取引先ごとのコードを紐づけて、入出金管理を行います。
発行した請求書のデータをもとに計上されている売掛金に対し、入金があった場合にはいつの分の請求に対する入金かを突合し、入金の仕訳処理をしていきます
。この作業を
「入金消込」
といいます。こうして、消込処理がされた後の各取引先の残高が正しいものとなっているかを毎月確認していきます。
中には、入金予定日に入金されていないものもあるため、毎月の管理を行い、支払いが滞っているものに関しては原因を突き止め、督促を行うなどの対応を行う必要があります。
支払いに対する督促が遅れたことにより、不良債権化することもありますから、売掛金管理においては、異常な状況が起きていることをすぐに把握できるような業務フローを作ることが重要です。
2.売掛金業務における新しい技術
(1)ERPシステム等の活用
これまで、営業が持つ売上のデータは各部署で管理され、経理部署は各部署から上がってきたデータを見て経理処理の対応をするというフローになっていました。しかし、営業の持つ各顧客の売上データを会計システムと直接連携させる
「ERP(enterprise resource planning)統合基幹業務システム」
と呼ばれるシステムを用いることにより、
売上データが経理現場においてもタイムラグがなく把握できるようになってきています
。
これは、自社システムを持つ大手企業だけでなく、市販のパッケージソフトやクラウドソフトでも対応できるものが増え、
経理現場において請求データのエントリー業務の削減につながっています
。
(2)入金消込におけるAIの活用
また近年、主流となりつつあるクラウド会計システムなどでは、
「API連携」
という技術を用いて、
各銀行のネットバンキングデータを直接会計ソフトのシステムに連携させることが可能となりました
。また、さらにこのシステムを拡張させ、入金データと請求データの突合をシステム上で行い、一致するものの消込を行うことができるものもあります。
この技術にAIによる学習機能を持たせることにより、自動消込の正確性は飛躍的に上昇し自動化率100%に近い水準まで来ているものもあります。
これまでの入金消込は、経理担当者が仕訳入力したものを「売掛金元帳」で1件1件確認しなければならず、この確認に多大な時間を要していましたが、今後はこういった技術革新により、ほぼ人の手を用いないでも滞留債権を拾い出すことが可能となるところまで技術革新が進んでいるのです。
3.売掛金における今後の「守りの業務」と「攻めの業務」とは?
ここでは今後AIにまかせてもよい業務を「守りの業務」、人間がさらに専門性に磨きをかけてやっていかなくてはならない業務を「攻めの業務」と定義します。
(1)売掛金の「守りの業務」
ご説明してきたように、データ処理でほぼ仕訳入力までが行えるようになると、これまで
この入力や確認の処理を行っていた人員が削減される
こととなります。すでに発生している売掛金を不良債権化させない、いわば「守り」の業務はAI の得意とする分野であり、今後は今以上に人の手を離れた業務となっていくでしょう。
○ 売掛金における「守りの業務」
-
入金確認
-
消し込み
-
仕訳入力
-
未入金の請求書の特定
(2)売掛金の「攻めの業務」
それでは、人はどのような技術が必要なのでしょうか。その答えの一つが、取引の発生段階において、「収益」だけでなく
正常な「収入」が見込まれる取引であるのかの見極め
。すなわち、「与信管理」などの「攻め」の業務です。
これからの社会は、「信用力」がさまざまな方法で可視化される時代です。企業によっては与信管理に帝国データバンクなどのサービスを利用しているかと思います。これも評点などのデータ化されている部分は、ある程度はAIで判断できることもあるでしょう。
しかし、
AIは決められたルールに則り処理することや整理する作業は得意でも、判断することはできません。それはあくまでも人間の領域です
。
さまざまな方法で分析された信用情報をもとに、「本当に企業にとって望ましい取引先とはいったいどのようなものであるのか」、これを判断する武器である管理会計は、今後さらに重要性を増すでしょう。これを利用した判断こそ、人間にしかできない「攻め」の経理業務となり得るのです。
○ 売掛金における「攻めの業務」
4.おわりに
売掛金業務で重要なのは、冒頭の「
1(2)企業の活動サイクルと売掛金
」で述べたように、企業活動において売上の代金が入金されないことを防ぐことが大前提にあります。ここであげたERPやAPI連携などのAIの活用もこの前提を忘れて、
単に「作業が楽になってよかった」で済ませては意味がありません
。
得意先ごとに取引金額の上限を設定し、その企業の経営状況ごとにこの設定額を上下させるなど、未入金となるリスクを回避することがこの業務の肝となるでしょう。
次回は、買掛金業務についてお話をします。
関連リンク