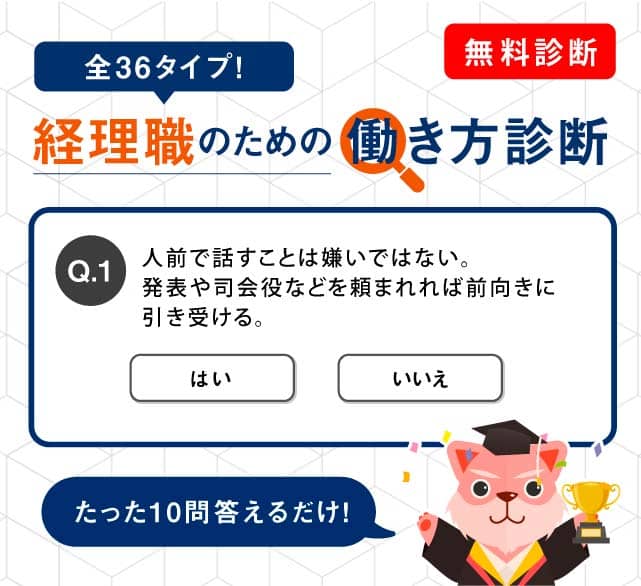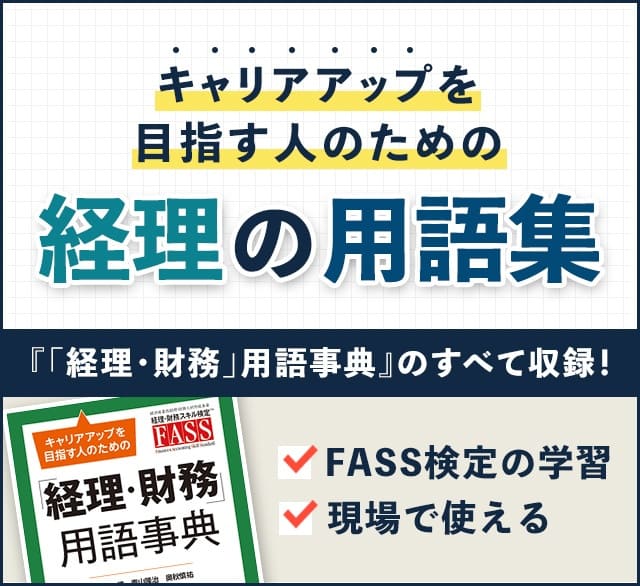■どうして建設業界の経理職が注目されているの?
近年、建設業界の経理職への転職希望者が増加している背景には、業界の安定性と専門性の高さがあります。公共工事などのインフラ分野は比較的安定している一方で、民間建築分野(住宅・オフィス・商業施設など)は景気や金利の変動・原材料価格の影響を受けます。
また、2024年から始まった働き方改革関連法案の適用により、建設業界でも労働環境の改善が進んでいます。これまで長時間労働が課題とされてきた業界ですが、業務の効率化やデジタル化により、働きやすい環境が整備されつつあります。
建設業界の経理職は、工事会計という特殊な分野の専門性を身につけることができるため、転職市場での価値も高く評価されます。一度習得した知識は他の建設会社でも活用でき、キャリアアップの機会も豊富にあります。
■一般企業の経理との大きな違いとは
建設業の経理業務は、他の業界と比べて独特な特徴を持っています。最も顕著な相違点は、売上の認識タイミングです。通常の商業では商品の引き渡し時に即座に売上を記録しますが、建設分野では長期工事に対応した専門的な計上方式を採用しています。
(1)進行基準による計上
進行基準による計上では、作業の進み具合に合わせて段階的に収益を記録します。これにより、数年にわたる大型プロジェクトでも適切な収益管理が実現できます。完成基準による計上では、全工程が終了した段階で収益を一度に記録する方法です。
(2)工事関連の特殊な勘定項目
工事関連の特殊な勘定項目も重要な違いです。進行中工事の支出額は、作業継続中の各種コストを暫定的に記録する項目で、他業界の製造中商品に該当します。工事完了時の未回収金は、作業終了後の代金回収待ち金額を管理する項目です。
■どんな企業で建設業経理の募集があるのか
建設業経理の求人は、業界内の様々な企業で募集されています。
(1)ゼネコン(総合建設業)
最も規模が大きいのはゼネコン(総合建設業)で、大型の建設プロジェクトを手がける企業です。大手ゼネコンでは、複数の工事を同時進行で管理するため、高度な経理スキルが求められます。
(2)サブコン(専門工事業)
サブコン(専門工事業)は、電気工事、配管工事、内装工事など、特定の分野に特化した建設会社です。専門性が高い分、その分野の工事会計に詳しくなることができ、専門的なキャリアを築くことが可能です。
(3)工務店・住宅メーカー
工務店や住宅メーカーでは、主に住宅建設を手がけており、比較的小規模な工事が中心となります。個人顧客との取引が多いため、一般的な売買取引の処理も多く、建設業会計の入門としても適しています。
■どんな業務内容が建設業の経理にはあるのか
建設業の経理職が担当の担当業務は、標準的な会計業務に加えプラスして、建築分野特有の専門業務が数多くあります。
(1)日次業務
日次業務では、材料の仕入れ処理、労務費の計上、外注費の支払い処理などがあります。これらの費用は工事別に分類し、適切な工事原価として計上する必要があります。
(2)財務業務
毎月の財務業務においては、各プロジェクトの進捗状況を把握し、工事進行基準に基づく売上計上を行います。工事現場からの出来高報告書を基に、当月の売上高を算定し、適切に計上します。また、各工事の原価集計も重要な業務で、材料費、労務費、外注費、経費を工事別に整理し、工事台帳に反映させます。
(3)原価計算と予算管理の重要性
建設業界の会計処理では、プロジェクト単位での詳細な費用追跡が必要になります。製造業のように同一製品を大量生産する場合とは異なり、建設では各プロジェクトで異なる資材や技術者が必要となるため、個別の費用管理が不可欠です。
個別管理手法が広く用いられており、各プロジェクトの直接経費と間接経費を正確に分類し、真の工事費用を算定することが重要です。大規模集合住宅の建築と小規模改修工事では、必要な資材や人員コストが大幅に違うため、各プロジェクトの費用を明確に区分し、正確に算定する必要があります。
さらに、プロジェクトの進捗状況に応じた費用集計を行い、収入とのバランスを確認しながら適正な収益率を維持することも要求されます。こうした費用算定の正確性が、建設業の経営安定につながる重要な要素となります。
(4)工事台帳と出来高管理の仕組み
工事台帳は、各工事プロジェクトの収支を管理する重要な帳簿です。工事ごとに作成され、契約金額、予算原価、実際原価、出来高、粗利益などが記録されます。経理職は、この工事台帳を正確に維持管理し、経営陣に対して各工事の収益状況を報告します。
出来高管理では、工事の進捗状況を金額ベースで把握します。工事現場の施工管理者からの報告を基に、当月の出来高を算定し、売上として計上します。出来高の算定方法には、工事進行基準に基づく方法や、完成部分の割合に基づく方法などがあります。
■どのようなスキルや資格が建設業経理には必要なのか
建設業の経理職に求められるスキルや資格は、一般的な経理知識に加えて、建設業特有の専門知識が必要です。最も基本となるのは簿記の知識で、日商簿記2級以上の取得が望ましいとされています。簿記の基礎知識があることでまた、建築分野特有の財務業務も理解しやすくなります。
建設業経理士は、建築分野界での経理職には非常に重要な資格です。1級と2級があり、2級では建設業の簿記、原価計算、会社会計の基礎知識が問われます。1級では、より高度な財務諸表の作成や分析能力が求められます。
(1)建設業経理士と日商簿記の違いとは
建設業経理士と日商簿記検定は、ともに会計に関する技能を証明する資格制度ですが、対象範囲や学習内容に明確な違いがあります。
日商簿記検定は商業活動全般に適用できる基礎的な会計技能を扱い、様々な業種で通用する汎用性の高い資格です。これに対し、建設業経理士は建設分野に限定した専門技能で、建設特有の会計知識を重点的に学習します。
建設業経理士2級の学習範囲には、進行基準計上や工事関連の特殊勘定項目、建設業独自の費用算定手法などが含まれます。費用計算分野では、直接経費と間接経費の適切な配分方法、プロジェクト別費用算定の技術などを習得します。
多数の建設企業では、建設業経理士の取得を推進しており、資格に応じた手当を支給する制度を導入しています。建設業許可を持つ企業では、経営状況審査において建設業経理士の保有者数が評価基準となるため、有資格者の存在価値は特に高く評価されています。
(2)実務経験と求められる人物像
建設業の経理職への転職において、実務経験の要件は企業や職位によって大きく異なります。未経験者でも応募可能な求人は数多くあり、特に人手不足が深刻な中小企業では、未経験者を積極的に採用している場合があります。
異業種ではあるもののITの開発などを行う企業での経験は、処理的に近いものがあるので歓迎されることもあります。
建設業の経理職には、数字に強いだけでなく、コミュニケーション能力や協調性も重要な要素となります。建設現場との連携が必要な場面が多く、現場の状況を理解し、適切にコミュニケーションを取ることが求められます。
現場理解力も重要なスキルです。実際の工事がどのように進行し、どのような材料や労働力が必要かを理解することで、より正確な原価計算や予算管理が可能になります。
■どの程度の年収や待遇が建設業経理では期待できるのか
建設業界の経理職の年収は、企業規模や経験年数、保有資格によって大きく異なりますが、他の業界と比較して比較的高い水準にあります。未経験者の場合、年収300万円から400万円程度からスタートすることが多く、経験を積むことで段階的に年収アップが期待できます。
経験者の場合、3年以上の経理経験があれば年収400万円から500万円程度、5年以上の経験があれば500万円から600万円程度が相場となっています。建設業経理士1級などの資格を保有している場合は、さらに高い年収が期待できます。
【給与アップのポイント】
(1)資格取得
建設業の経理職で給与アップを図るためには、いくつかのポイントがあります。まず、資格取得は最も確実な方法です。建設業経理士1級の取得により、資格手当を受けることができる企業もあります。
(2)マネジメント経験
マネジメント経験も重要な要素です。部下の指導や業務管理の経験があることで、管理職への昇進が可能になり、大幅な年収アップが期待できます。特に、複数の工事プロジェクトを同時に管理できる能力は高く評価されます。
(3)システム導入などの実績
システム導入や業務効率化の実績も評価されます。ERP(統合基幹業務システム)の導入経験や、業務プロセスの改善実績がある場合は、転職時の年収交渉でも有利になります。
■入社後にギャップを感じやすいポイント
建設業に転職した際に、多くの人がギャップを感じるポイントがいくつかあります。
まず、業務の繁忙期と閑散期の差が激しいことです。工事の進捗や決算期に合わせて業務量が大きく変動するため、時期によっては長時間労働が必要になることがあります。
現場との温度差も感じやすいポイントです。オフィスで数字を扱う経理職と、実際に建設作業を行う現場スタッフとでは、業務の性質や文化が大きく異なります。この違いを理解し、適切にコミュニケーションを取ることが必要です。
建設業特有の商慣習も戸惑いの原因となることがあります。手形取引の多用や、工事代金の支払いサイトの長さなど、他の業界とは異なる商習慣があります。これらの慣習を理解し、適応を実行することが重要です。
■どうすれば建設業の経理に転職できるのか
建設業の経理職への転職を成功させるためには、段階的なアプローチと入念な準備が重要です。転職活動を始める前に、まず自分の現在のスキルレベルを正確に把握し、建設業界で求められるスキルとのギャップを明確にすることから始めましょう。
(1)まずは簿記・建設業経理士の学習から
転職準備の第一歩として、簿記の基礎知識を固めることが重要です。未経験者は日商簿記3級から始め、できれば2級まで取得することを目指しましょう。簿記2級レベルの知識があれば、建設分野独自の会計処理も理解しやすくなります。
建設業経理士2級の取得も強く推奨されます。建設業経理士は、特に建設業許可を持つ企業で経営事項審査(経審)対策として重視される資格です。この資格は建設業界での専門性を示す重要な指標であり、転職時の大きなアピールポイントになります。学習期間は3か月から6か月程度が目安で、通信講座や夜間講座を活用することで、働きながらでも取得可能です。
(2)応募書類と面接対策のポイント
建設業経理への転職における応募書類では、志望動機の書き方が特に重要です。「社会インフラの整備に貢献したい」「モノづくりの現場で専門性を発揮したい」など、建設業界の特性を理解していることを示す内容を盛り込みましょう。
面接では、業界特有の知識について質問されることが多いため、事前の準備が重要です。工事会計の基本概念、工事進行基準と工事完成基準の違い、原価管理の重要性などについて、基本的な説明ができるよう準備しておきましょう。
転職エージェントの活用も効果的な手段です。経理・会計に特化したエージェントであれば業界の内部情報や非公開求人を持っていることが多く、個人では得られない情報を提供してくれます。また、面接対策や給与交渉においても専門的なアドバイスを受けることができます。
■実際に建設業経理に転職した方々の成功事例
【転職成功者の声1】メーカー経理から建設会社経理へ(30代男性)
「製造業の経理から地域密着型の建設会社に転職して2年が経ちました。最初は工事進行基準や未成工事支出金など、聞いたことのない会計処理に戸惑いましたが、先輩の丁寧な指導のおかげで徐々に理解できるようになりました。
現在は月15件程度の工事案件を担当し、各現場の原価管理を行っています。完成した建物を見たときの達成感は、メーカー時代には味わえないものです。建設業経理士2級も取得し、年収も前職より100万円アップしています。」
【転職成功者の声2】経理未経験から建設会社の経理補助へ(20代女性)
「事務職から建設会社の経理補助に転職して1年半になります。経理は完全未経験でしたが、簿記3級を取得してから応募し、丁寧な研修制度のおかげで基本的な業務はできるようになりました。建設現場を見学する機会もあり、自分が処理している数字が実際の工事とどのように関連しているかを理解できるのが面白いです。
現在は建設業経理士2級の取得に向けて勉強中です。」
■どんなメリット・デメリットが建設業経理にはあるのか
(1)メリット:専門性の高さとスキルの定着
建設業経理の最大のメリットは、高度な専門性を身につけることができる点です。
工事会計は他の業界では経験できない独特の分野であり、一度習得すれば転職市場での価値が長期間維持されます。この専門性により、他の経理職と差別化を図ることができ、キャリアアップの機会も豊富にあります。
業界の安定性も大きなメリットです。建設業は社会インフラの維持・更新に欠かせない産業であり、長期的な需要が見込めます。給与水準は企業規模や事業内容により差が大きく、大手ゼネコンなどでは高水準の給与が期待できますが、中小企業では業界平均水準となるケースもあります。
また、資格取得による資格手当の支給や、プロジェクト成功に対する成果報酬制度を設けている企業も多くあります。
(2)デメリット:業務量の変動と業界特有の課題
建設業経理のデメリットとして、業務量の季節変動があげられます。決算期や工事の完成時期、公共事業の発注時期などに業務が集中し、一時的に長時間労働が必要になることがあります。
業界特有の商慣習への適応も課題となります。手形取引の多用、工事代金の支払いサイトの長さ、現場との独特のコミュニケーション方法など、他の業界とは異なる慣習があります。これらに慣れるまでには時間がかかる場合があります。
■どのようなキャリアパスが建設業経理にはあるのか
建設業の経理職には、明確で多様なキャリアパスが用意されています。
(1)社内でのキャリアパス
基本的には、財務担当者からスタートし、主任、係長、課長、部長と段階的に昇進していく道筋があります。各段階で求められるスキルや責任範囲が明確に定義されており、目標設定がしやすい環境があります。
課長レベルでは、経理部門全体の管理や、経営会議での報告業務も担当します。この段階では、年収600万円から800万円程度が期待でき、企業の中核人材としての地位を確立できます。
(2)将来的に活かせる転職先
建設業で培った経理スキルは、様々な業界で活用することができます。建設業をクライアントに持つ会計事務所や税理士法人では、専門の担当として実務経験が評価されることもあります。不動産業界も有力な転職先で、建設と不動産は密接に関連しており、建設業で培った知識は不動産開発や賃貸管理業務でも活用できます。
コンサルティング業界でも、建設業界の知見を持つ経理職は重宝されます。建設会社の経営改善や、M&Aにおける財務分析など、専門的なコンサルティングサービスを提供できます。
■まとめ:建設業経理は専門性と安定性で将来性も抜群
建設業界の経理職は、高い専門性と安定した雇用環境を兼ね備えた、非常に魅力的なキャリア選択です。工事会計という他の業界では経験できない独特の分野を習得することで、転職市場での価値を大幅に向上させることができます。
業界の特性上、社会インフラの整備に直接貢献できるため、仕事に対する誇りとやりがいを感じられる職種です。給与面でも他の業界と比較して有利であり、資格取得や経験年数に応じて着実にキャリアアップが可能です。
特に中小企業では未経験者を受け入れるケースもあり、日商簿記2級レベルの知識と業界への理解・学習意欲があれば、十分にチャレンジ可能です。簿記の基礎知識から始めて、建設業経理士の資格取得を目指すことで、確実にキャリアを築くことができます。
建設業界の経理職は、専門性、安定性、将来性のすべてを兼ね備えた優れた職種です。転職を検討している方は、ぜひこの機会に建設業界でのキャリア構築にチャレンジしてみてください。