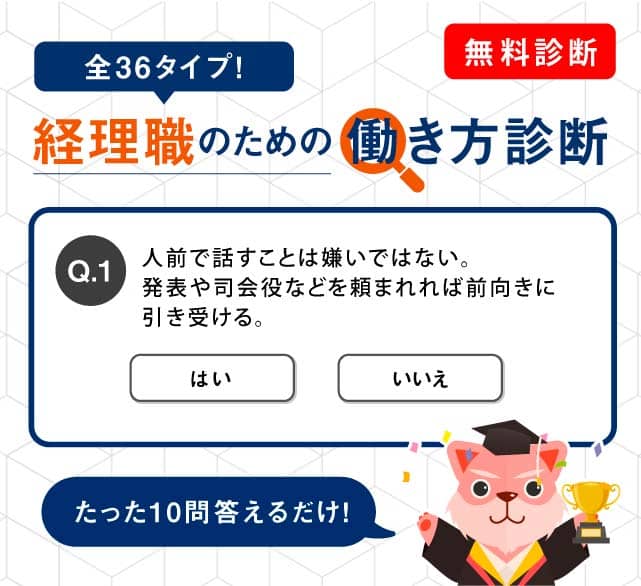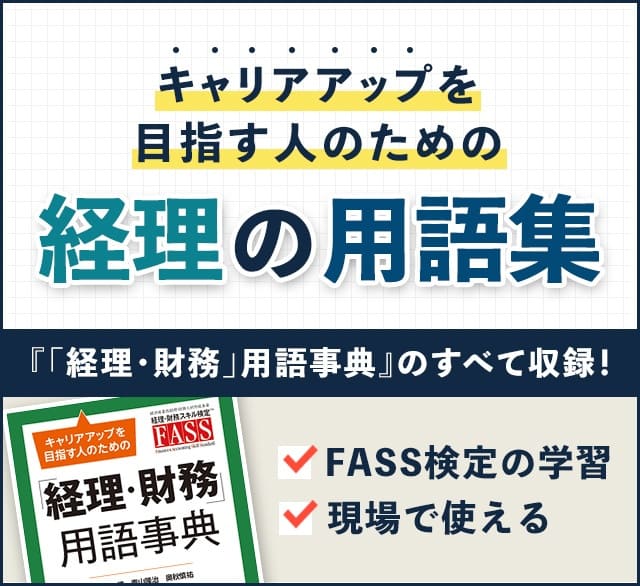1.耐用年数の持つ意味
会計の学習に当たり、比較的初期の段階から出てくるのが
「減価償却」
という項目です。
定率法や定額法といった手法にばかり着目がいく項目ですが、これらは費用項目の算定方法であると同時に、固定資産そのものの評価額の算定という側面もあります。

上記は固定資産の仕訳上の動きを図式化したものですが、その資産の耐用年数を元に計算された減価償却費の金額は当期の収益獲得のために使われた部分として損益計算書に費用として計上されます。このとき、備品の償却後簿価(間接法の場合は取得価額と減価償却累計額との差額)は、備品の期末評価額として貸借対照表に計上されます。
それでは、「耐用年数」とは一体何なのでしょうか?これは文字通り、
その資産の「使用に耐えうる年数」
です。すなわち、税法で用いられる「法定耐用年数」は、該当資産が使用に耐えうる一般的な目安の年数を指し、償却完了間近の資産は「そろそろガタが出てくる」という合図を放っている資産なのです。
2.期末評価額と資金繰りの関係
この
評価額の管理がされてない場合どんな問題が生じるのでしょうか。
不動産業界において不動産評価の一つの目安となるのが15年という年数です。これは、給排水設備の耐用年数を現します。給排水設備は使用頻度が高く、外壁などに比べ傷みやすい特徴があります。建物自体に劣化が顕在していなくても給排水設備の故障により建物の使用ができなくなる可能性もあるのです。
賃貸マンションなどの収益物件では、これが即、収益減につながるわけですから、一大事です。急な出費だけでなく、収益も途絶えてしまっては経営そのものに影響が出る可能性もあります。そのため、不動産オーナーは15年ごとに改修が必要となる前提で資金計画を立てなければなりません。
こうした耐用年数と資金繰りの関係は不動産オーナーに限らず生じます。店舗内装などは10年ですが、10年営業すると外見上の汚れが目立ち、みすぼらしさから顧客離れが生じるかもしれないでしょう。工場の機械も故障が生じれば製造ラインがストップし、大幅な機会損失が生じてしまいます。このように、期末簿価は文字通り「あとどのくらい持ちこたえるか」の一つの指標なのです。
3.情報化社会における問題
また、固定資産管理は、近年の情報化社会における必要性も増しています。
企業が抱えるデータ量は年々増え、膨大な顧客データや在庫データなど経営におけるIT化の過程を支えるさまざまな機器が必要となっています。今やオフィスのパソコンは一人一台が普通であり、サーバー端末や通信機器、携帯端末、コピー機やスキャナーといったOA機器など多種多様な資産が固定資産台帳に計上されます。
こうした情報通信機器においては、「紛失=情報漏洩」という大きな問題が生じます。
(1)法制度化と会計監査への対応
2003年に成立した個人情報保護法では、こうした情報漏洩に関する重い罰則が設けられ、企業はよりいっそう情報管理に敏感にならざるを得ない環境となりました。また、2008年からは、財務諸表の適正性を監査する会計監査だけでなく、その
作成のプロセスにも着目した内部統制監査が実施されるようになりました。
この監査の対象はIT分野にも及ぶため、「誰がどこでどの資産を使用しているのか?」といった詳細な情報までの管理が必須となっていったのです。
(2)高度化する会計基準への対応
これに加え、日本で長年採用されていた取得原価主義では、
期末財務諸表に「含み損」が反映されない
ことが大きな問題となっていました。
特に事業買収により発生する営業権は、買収した企業が投資に見合う収益を産まなければ、実体のない資産になります。しかし、投資損失を認識することは株主に対する説明責任が発生するだけでなく、場合によっては巨額の損失計上に伴い、株主代表訴訟に発展する可能性も秘めているからです。そのため、こうした損失を計上せず、会計技術により表面化させない粉飾決算の事例が相次いで発生しました。
この代表例が「東芝事件」です。これは、東芝が買収した海外企業に係る減損損失を連結決算上、外して開示した事例です。
企業買収は投資額が巨額になるため、その損失額も巨額になります。そのため、買収時点における評価額の算定(デュ―・デリジェンス)に加え、会計基準に則った減損兆候の把握など、より高度な会計技術が必要となっているのです。
4.固定資産管理の現状
(1)ソフトによる管理
複雑な事情を持つ固定資産の管理ですが、現状、どのような管理が行われているのでしょうか。 固定資産の管理は、通常、固定資産台帳に資産の登録を行い管理します。
固定資産台帳はさまざまなベンダーから管理用ソフトが出されており、これを利用することで自動的に償却費の計算が行われ、台帳が完成します。また、ERP(Enterprise Resources Planning「基幹系情報システム」第1回参照)の機能をもつソフトあれば、固定資産管理ソフトのデータをもとに仕訳生成が行われ、会計データに反映されます。
経理部門が行う作業は、事前にラベルなどで付した台帳番号を元に期末にその資産が実際に社内にあるのかを目視で確認し、廃棄等の事実があればその情報を固定資産管理システムに反映するだけです。
 (「3年後に必ず差が出る 20代から知っておきたい経理の教科書 」2014年 翔泳社)
(「3年後に必ず差が出る 20代から知っておきたい経理の教科書 」2014年 翔泳社)
(2)監査における台帳の不備
一見すると、大変な作業に思えない確認作業ですが、実際には会計監査上の不備もある項目です。なぜなら、大規模な法人ともあれば、社内にあるパソコンは何千台もあり、工場や営業所などのように、日常的に経理担当者がいないような部署もあります。
社内のさまざまな場所でさまざまな方法により管理されている固定資産の情報をタイムリーに把握することは社内ルールを整備しても困難な作業であるのです。
5.データ活用による固定資産管理のミライ
(1)固定資産管理におけるデータ処理活用
こうした大規模法人における固定資産の物理的な管理方法として着目されているのがバーコードやRFIDタグ、QRコードなどを活用した管理です。
対象資産に台帳の登録情報の内容をデータ化したバーコードを添付し、廃棄等があった場合はそのバーコードを読み取り廃棄処理に回します。これをルール化することで、台帳上タイムリーに除却や売却の情報が登録されます。また、近年では専用端末の必要がないRFIDタグやQRコードなども活用されています。
(2)システムによるIT資産管理
情報漏洩の問題が生じるパソコンなどのIT資産については、ハードウェア、ソフトウェアに関する情報をオンライン上のデータから自動収集し、管理することが可能です。
システム部門において、操作ログを管理するなど、内部統制監査に対応するための対策も行われています。
(3)固定資産管理はすべてIT化できるのか?
それでは、今後、固定資産の管理はすべてIT化できるのでしょうか。
固定資産の管理において、すべてを人の手を介さず管理するというのはこれからも難しい問題かもしれません。
なぜなら
「評価」を行うのは、企業の意思決定に関わることである
からです。
なぜ、減損隠しのような事件が起きるのか。そこには、悲しいことに企業の意思があるのです。固定資産の会計処理はどんどん複雑化しています。しかし、この複雑化した部分はすべて「現況を人がどのように評価するのか」という判断に関する事項なのです。
(4)会計処理と会計人の倫理観
会計は、人と人、企業と企業の共通ルールであり、そのルールは人が作り出したものです。自然に生まれたものではありませんから、
これに関わるすべてのひとがこの共通ルールに則って処理を行っているという信頼性がなければ、成立しません。
評価は「解釈」と言い換えることもできます。すなわち、人がすでに起きている事象をどのように解釈するのかにより評価額は異なるということなのです。
それは、AIが活躍するミライにおいても変わらない事実でしょう。
そのときに、我々はどのような仕事を行えばよいのでしょうか?
会計における信頼性を担保すること、これには携わる一人一人の倫理観が試されているのです。
関連リンク