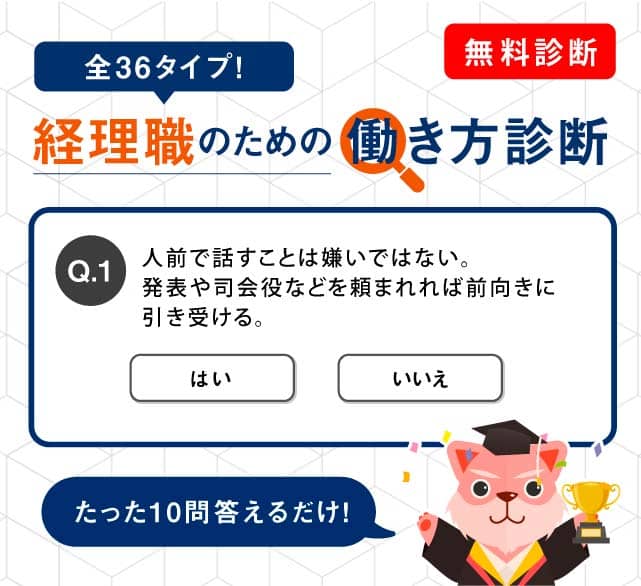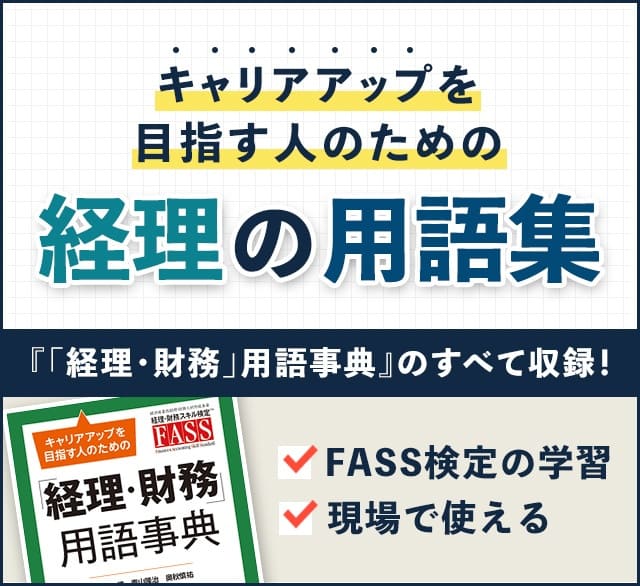1.経理現場におけるテレワーク化の現状
これまで、日本では一部のIT企業を除き、業務は会社に出勤し行うことを前提にフローが確立されてきた。
しかし、この状況は令和2年4月7日、政府の発令した「緊急事態宣言」をきっかけに変えることを余儀なくされた。外出禁止を原則とし、オフィスワークは在宅でのリモートワーク(政府の発表では「テレワーク」という呼称を採用している)に変更するよう要請を受けたことに対し、大手企業から少しずつリモートワーク化を実行していった。その結果、丸の内や新橋などのオフィス街から多くのサラリーマンが消えた。
これは、経理職においても例外ではない。
(1)リモートワークの実態
ジャスネットコミュニケーションズが行ったリモートワークに関する調査(有効回答数176人)によると、
「毎日リモートワークをしている」と回答した人は全体のわずか5.5%(8人)
に過ぎない。また、「毎日いままで通り会社に通っている」と答えた人は43.2%(63人)にも上る。
Q リモートワークの状況について
-
1. 必要のあるときだけ、会社に行っている → 75人(51.3%)
-
2. 毎日いままで通り会社に通っている → 63人(43.2%)
-
3. 毎日リモートワークをしている → 8人(5.5%)
さらに、回答者の属性を調べると経理部の規模が1~5人程度の中小企業が全体の66.5%(97人)を占めており、このことから
リモートワークは中小企業の経理部門においては、いまだハードルが高い
ものであることがわかる。
Q 経理部の人数を教えてください
-
1. 1~5人 → 97人(66.5%)
-
2. 6~10人 → 27人(18.5%)
-
3. 11人以上 → 22人(15%)
具体的にはどのような業務がリモート化の弊害となっているのであろうか?
(2)業務をリモート化できない理由
調査の結果によると、リモート化できない業務は下記のような業務である。
Q どのような業務で会社に行っていますか?(複数回答可)
-
1. 支払い業務(請求書の計上処理含む)→ 119件
-
2. 請求書発行、押印など → 74件
-
3. 決算対応 → 66件
-
4. 監査や税務調査、銀行などの対応 → 64件
-
5. 会議出席や報告のため → 26件
この結果のうち、上位3項目は以前このコラム(
「AI時代における経理業務のミライ」
)でも指摘してきた内容である。特に支払い業務に関しては、相手先により対応やフォーマットが異なる請求書を処理しなければならず、
ペーパーレス化を完全に行うためには取引業者すべてにこれを求めなければならないため、実質不可能
である。
近年利用が進んでいるクラウド会計ソフトにおいても社内で受け取った請求書をPDF化する人員は必要であり、100%出社せず業務を行うことは不可能であろう。
(3)ハンコ至上主義の弊害
また、日本における
「ハンコ至上主義」
の押印文化は廃れることがない。これに関しては、進んだ民間企業においては電子フォーマットで作成された請求書をメールで送付したり、電子契約書を取り入れたりと電子化が進んでいるが、ネックとなるのが
役所関係と銀行取引
である。これらの機関の多くの取引が大量の書類に記入し、押印しなければならず、リモート率が比較的高い職場においてもこのために出勤せざるを得ない担当者がいるという意見は見受けられた。
また、その場合、
決裁権限を持つ上司とのスケジュール調整も必要
であるという煩わしさもある。
経理部署に限らず、この押印文化が、企業が取引を進めるうえで弊害となり、問題となっていた。リモート化が進むことで誰もが共通認識としてこの問題を持った今、国全体の取り組みが問われるであろう。
(4)テレビ会議の普及
自粛モードが高まる中で、多くの人が体験し、興味を引いたのが
「リモート会議」
である。
通常の会議は、移動時間の制約や会議室の予約などさまざまな制約があったが、オンラインであれば、出席者のスケジュールさえあれば瞬時に開催できるため、
意思決定が速くなるメリット
がある。しかし、これは自宅でのリモート環境下において世界中どこでも出勤時間の制約なくミーティングが可能であるため、気が付けば一日中ミーティングが続く「ミーティング疲れ」を生じさせているケースもある。
こうしたツールの活用方法は、今後共通ルール化されていくであろうが、その過渡期においては、こうした問題は発生するであろう。
(5)社内LANやイントラネットによる弊害
経理部門のリモート化における最大の問題が経理システムそのものにある。
経理は社内の機密を扱う部門であり、これまで特に大手企業においては複数台のパソコン同士による社内LANや社内のイントラネット内のみで経理を行ってきた経緯がある。
これらは、近年、企業の情報漏洩による数々の問題もあり、強固なセキュリティー環境の下運用されている。そのため、
パソコンを持ち出すことによるセキュリティーの脆弱性を理由に経営サイドがリモート化を躊躇したり、そもそも社外では利用できないシステムになっていたり
というケースもある。
これに対し、経理に設備投資できない中小企業やベンチャー企業などでは、初めからクラウドをベースに社内システムを構築しているため、リモート化にもすぐに対応できている。今回の経験を踏まえ、経理システムの変更とそれに対応できるベンダーの選定が課題となる企業は多いであろう。
2.リモートワークで3月決算をどう迎えるの
奇しくもこの緊急事態宣言が出された4月上旬は3月決算法人においてはまさに決算業務の真っ只中である。通常であれば、これから監査業務や株主総会などの決算確定のためのプロセス業務が発生するはずである。実際のところ、例年通りの決算を迎えることは不可能であると判断する企業も多く、そのため、政府も数々の特例措置を設けている。それでは、通常行う決算について、どのような課題が生じるであろうか。
(1)決算業務における意思確認
調査の結果によると、リモート化が難しい業務は他の作業者とのコミュニケーションの取り方である。
決算においては、月次のルーティーンによる業務フローだけでなく、決算整理に代表される決算特有の業務も存在する。
これには、経理チーム内で各担当者が通常決められており、それぞれが担当箇所に関する情報を集め、処理しなければならない。しかし、経理業務は一人で行えるものではないため、
意思確認の問題
が生ずる。
具体的には、下記の2点が問題となる
①
経理部署内
において
他の業務担当者
との意思確認
②
他部署
における
業務担当者
との意思確認
(2)経理内部における意思疎通
上記①については、それぞれの担当者ごとの
タスクの洗い出しとスケジュール、達成度合を可視化
することがこれまで以上に重要である。
スケジュールの遅れは、他社のフローへの遅れへとつながってしまうが、面と向かって話す機会がなく、進捗の把握が難しくなる可能性がある。タスク管理ツールやチャットツールなどをうまく活用し、互いに進捗を共有することが重要である。また、そのためには
上長承認の際、押印以外の方法による意思決定のフローを定める必要
がある。
また、②のように、他部署が上げてくる売上の伝票やイレギュラーな請求、上長承認の漏れの確認など、各担当者に問い合わせが必要なケースもある。その際に、担当者とどのように連絡を取りあい、疑問点を解消していくかといった問題に対する対応策も検討しておく必要があるだろう。
3.リモートワークにおける監査
経理による決算業務が終了したら、会計監査が行われる。
緊急事態宣言下において、東証により4月9日時点で51社の決算発表の延期を公表し、6月の株主総会の日程変更企業はごく少数といった内容が共有された。
監査業務は、監査法人よる調書の確認が行われる。そのため、通常は企業内で用意された会議室を使い、社内のLANなどを利用した環境で帳簿の確認とそれに伴う調書の確認を行わなければならない。これは、まさに政府が注意を呼びかける三密環境に値するため、これを回避することを考えなくてはならない。
オンラインによる監査業務は、監査対象企業のインフラの状況に左右される
ことになる。こうした状況から、開示の遅れはやむなしとの判断となったのであろう。
以前から「働き方改革」を標榜し、監査業務のシステム化を進めてきた大手監査法人では、
基礎的な作業の標準化や残高確認のオンライン化など、すでにリモートワークを想定した動きをしていたことも多く、その効果が生かされる局面に来ている
。ポスト・コロナの監査業務では、今回の経験を踏まえ、よりオンライン上での対応を行えるインフラ整備が企業、監査法人ともに進むのではないだろうか。
4.株主総会に関する影響
定時株主総会は、決算日の翌日から、通常3カ月以内に設定されるよう、定款で定められている。しかし、前述のとおり、多くの上場企業において決算の遅れから株主総会の遅れが想定されている。
これを踏まえ、金融庁は決算開示について
9月末までの一律延長も視野に入れている
。しかし、従来の方法を変えるには、迅速な法改正を行わなければならず、こうした事情も今後の監査のあり方に影響を及ぼすであろう。
株主総会の開催のプロセスは、通常、総会開催前2週間前までに招集通知を発行しなければならないし、株主の過半数の出席による総会の開催が会社法上の要件となっている。こうした、
株主総会に関する法律上の手続きがリモート化の妨げになるケースも想定される
。
経済産業省は、リアルの株主総会の会場とインターネットでの同時配信を用い、オンラインでの参加を可能とする「
ハイブリット型バーチャル株主総会
」を推奨している。こうした、オンライン型の総会の整備も今後、加速していくであろう。
5.さいごに
これ以前の企業文化は、改めて日本という国の国力の低下に結びついているという事実を誰もが感じていたにも関わらず、これまでその転換ができなかった。これに対し、これまで誰もが疑問に思わなかった社内での業務が、実は労働者に相当な負荷を掛けていたことがこの1カ月でより明確になったのである。
これまで「理想論」と見過ごされてきたリモート化がより現実のものとして迫られた
のが、このポスト・コロナの現状ではないだろうか。
社内の環境整備や政府の対応の遅れにより、対応できてこなかった部分は、これを機に大きく見直しが図られることであろう。
多くの国民が「なぜリモートなのか?」という問いに対する明確な答えをもつことにより、この先、我々の日常が大きく変わっていく兆しは見え始めている。
関連リンク