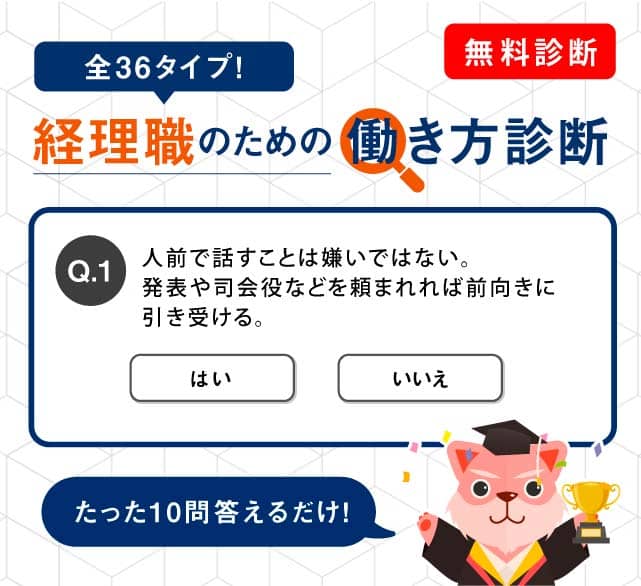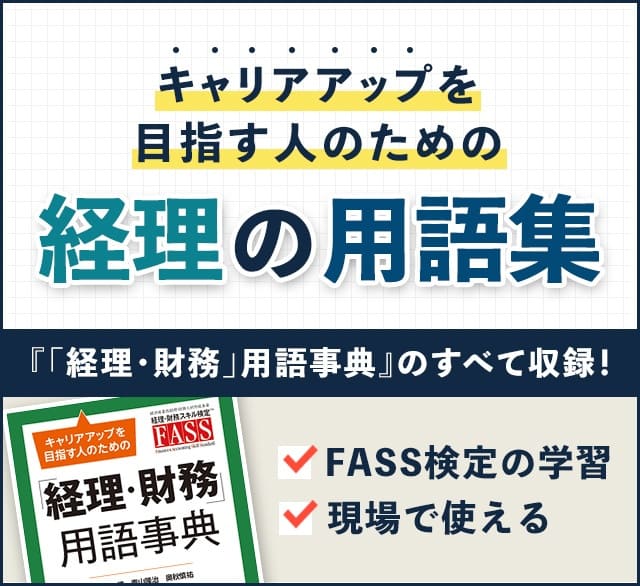「会計士と税理士の違いってなんですか?」これは、こういった仕事に携わる誰もが一度は受けたことのある質問でしょう。
かくいう私も「なぜ税理士になったのか?」と言われると、たまたまこの仕事を紹介してくれた方が税理士の方だっただけで、会計士の方に誘われたら会計士を目指していたかもしれません。もしかしたら、このコラムを読んでいる方にも正確な違いがわからない方もいるのではないかと思います。
税務も会計に関わる業務を行う中で必須の知識であることは間違いありません。
今回は、「税効果会計」という「会計処理」を通して税務と会計の違いを見ていきましょう。
1.会計の目的と税務の目的の違い
会計と税務では、収益や費用の考え方に多少のずれがあります。これは、同じ「会計基準」というツールを前提としながらも目的が違うためです。
会計の目的は投資家などの利害関係者の判断を歪めないことであり、そのため、前回(第8回)確認したようにさまざまな手法で企業の
「あるべき姿」
を算定します。これに対し、税務は税金の算定が目的であり、課税されるべき利益(これを
「所得」
といいます)が公平に算定される
「課税の公平」
を重視しています。そのため、法律の規定にない見積もり計上などを認めていません。
法人税の計算は、会計上で計算した利益をベースにこの会計と税務で相違する部分の金額を加減算して求めます。

※収益のマイナスは利益にマイナスのインパクト、費用のマイナスは利益にプラスのインパクト
2.税効果会計とは?
ここで着目するのが、損益計算書末尾の
「税引前当期純利益
」と
「法人税等(法人税、住民税及び事業税)」
の関係性です。
損益計算書に表示される「税引前当期純利益」は会計のルールにより算定された利益であるのに対し、そこからマイナス表示される「法人税等」は会計上の利益を上の図のように税務上の利益に修正した「所得」をベースに算定されていますから、損益計算書上、この2つの金額は連動していないことになります。これを
「会計上の利益に対する税金」
になるよう、調整する目的で行われる処理が「税効果会計」です。

3.差異の調整方法割
会計上と税務上の差異は費用の前倒し計上に当たる
繰延税金資産(前払税金)
と準備金の積立てなどの特殊な事情による
繰延税金負債(未払税金)
がありますが、ここでは理解しやすい繰延税金資産を見ていきましょう。
繰延税金資産が発生する状況は、以下のように会計上も税務上もいつかは費用として計上されるものの、その計上時期が両社でズレているもの、すなわち、期間対応のズレによるケースです。
-
1.減価償却超過額の発生(税法上の償却限度額以上の償却費の計上)
-
2.引当金の計上(貸倒引当金以外の引当金の計上)
-
3.評価損の計上(税法上容認される以外の評価損の計上)
-
4.繰越欠損金の発生
たとえば、会計上、費用の見積もりで引当金を計上しても税務上は確定していない費用である引当金の計上はできません。そのため、一時的に
税金計算上、この費用を戻した利益で税金計算
を行います。
税務上の経費算入した会計期間においては、会計上の費用が発生していないにも関わらず、税務上の経費は増え、税金の支払いが減るため、引当金を計上した前の会計期間では、その分の資金が一時的にプールされていることとなります。この将来における税金の減少分を前払資産ととらえ、計上したものが繰延税金資産です。

4.税効果会計はAI化できるのか?
さて、ここまでが税効果会計という処理の説明です。ルール自体は難しい話なので、理解できなかった方はひとまず置いておいてここから考えてみて下さい。この処理は税務なのか、会計なのか、どちらに感じたでしょうか?
税効果会計は、貸借対照表や損益計算書の表示に関するルール
ですから、
「会計上のルール」
です。しかし、「なぜ、このような差異が生じるのか?」、「どのような項目に差異が生じるのか?」といった
本質的な内容は税務を理解していなければ判断できません
。
AI化の条件は業務の定型化です。
差異となり得る項目は、会計上の事情による調整であり、何を調整すべきかは個々の事象に対し、計上要件に当てはまるかどうかを確認しながら行うものです。
継続的に毎期発生するものは、ある程度プログラミングが可能ですが、
特殊な事情
によりたまたま発生したものについて、
処理の必要性に気付くことができるか
は、個人の能力による部分が多いのです。
5.会計なのか税務なのか?
ここでよく言われることが、「税理士は会計をわかってない」「会計士は税金をわかっていない」ということです。
これらの2つの資格は、日本では国家資格であり、それぞれがプロフェッショナルと言われますが、
海外で税理士という資格がある国はごくわずか
です。それは、そもそも税務も会計処理の一環であり、この
2つを切り離して考えるのはナンセンス
と考えるからです。
内科医と外科医の違いのように、税理士や会計士もそのジャンルにおける得意分野が異なります。しかし、会計に携わる業務である以上、このような両方の分野に跨る問題は発生します。
税務の難しさは毎年のようにころころと変わる税制のキャッチアップです。また、産業構造自体の変革は企業の活動サイクルの変更であり、これに合わせた会計処理を考えるだけでなく、税務においても会計においても
デジタル化や国際基準への理解など新たな課題
が求められる時代となっています。
こうした様々な問題を
会計や税務の垣根を越えて総合的に理解
することはもはや会計人としてはマスト。その中で自身の得意分野を形成していける人材こそが、真の会計のプロフェッショナルではないでしょうか。
関連リンク