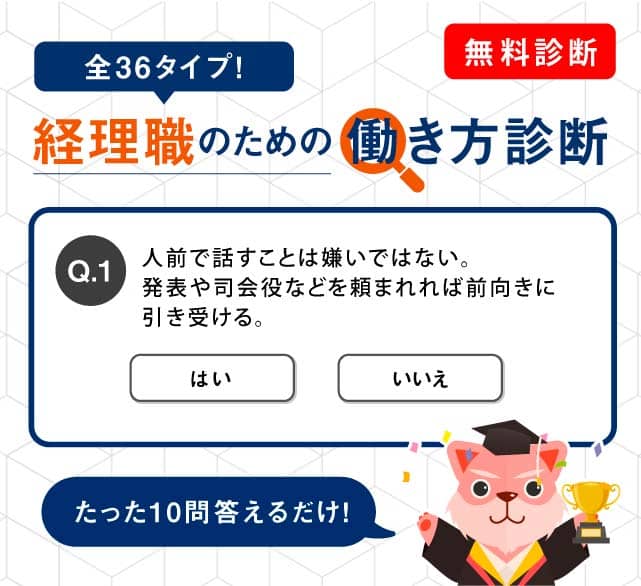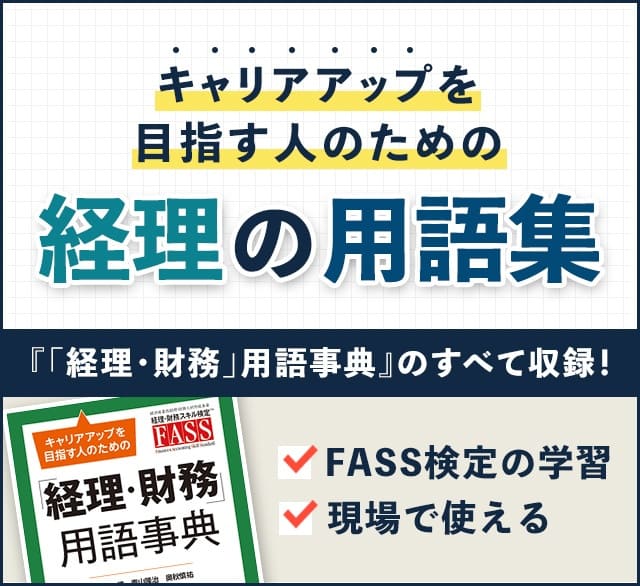■ 社会人だからこそ活かせる強みと成功のポイント
学生と異なり、資格勉強のために使える自由な時間が少ない社会人。現在の仕事を疎かにせず、次のステップに向けた準備を行うのは困難も伴うものです。一方で、社会人として身につけたものが、税理士を目指すうえでメリットとなることも。
まずは発想を転換し、社会人が税理士試験に臨むメリットについて考えてみましょう。
(1)実務経験と人脈の活用
社会人としての経理に関連する業務や実際の経理処理に触れてきた経験。それは参考書やテキストで出会う税務会計の知識を、実体験として深く理解できるきっかけとなるでしょう。
また他業種の経験が、税務会計の実務で役立つことも多いはずです。営業や接客の経験をお持ちの方なら、顧問先担当者や経営者への直接対応でコミュニケーションスキルを存分に発揮できます。事前に簿記や会計の勉強をした方なら、簿記論や財務諸表論といった科目の勉強で有利になります。
さらに社会人経験の中で培った人脈も大きな資産です。これまでの職場で出会った同僚や上司、取引先、関連会社の人材、友人など。培った人間関係が、将来の顧客候補や業務拡大のきっかけとなる可能性があります。
(2)時間管理能力と責任感
時間管理能力も社会人の強みです。仕事で培った効率的な時間の使い方やスケジュール管理スキルは、限られた時間の中で勉強を進める際に大いに役立ちます。また、プレッシャーに慣れていることも、試験本番での冷静な対応につながります。
社会人としての責任感や継続力も大きな強みです。税理士試験は長期戦になるため、途中で挫折する人も多いものです。しかし、社会人として培った責任感や忍耐力があれば、困難な状況でも勉強を続けることができるでしょう。
(3)明確な目的意識と戦略的アプローチ
明確な目的意識を持っていることも社会人の強みです。学生とは異なり、社会人になってから目指す方は「なぜ税理士になりたいのか」「税理士になって何をしたいのか」という明確な目標を持っています。この目的意識があることで、勉強に対するモチベーションを維持し、効率的な学習を続けることができるのです。
社会人から税理士を目指すことは確かに大変な挑戦ですが、戦略的なアプローチと継続的な努力によって、道は開けるでしょう。自分の強みを活かし、効率的な学習法を身につけることで、税理士という専門職への転身を成功させることができるはずです。
■ 社会人が税理士になるための基本的な道筋
では、具体的に税理士になるためのルートや試験の詳細について見てみましょう。
(1)税理士になるためのルートは3つ
社会人が税理士になるためには「税理士試験に合格 → その後、実務経験を積む」という流れが一般的です。税理士資格を手に入れるルートは、以下の3つ。
- 税理士試験に合格する(一部の科目は「大学院修士課程で税法または会計学に関する研究」を行い、「税理士法に基づく審査を通過」することで免除可)
- 公認会計士試験に合格する(公認会計士は税理士登録が可能)
- 税務署などで一定期間勤務する(23年勤務で全科目免除)
社会人の場合、難易度の高さや必要な時間から考慮し、現実的には税理士試験を受験することになるでしょう。
(2)税理士試験が、社会人に適している最大の理由
税理士試験は5科目の合格が必要ですが、一度に全科目を受験する必要はありません。試験科目は、必須科目として「簿記論」「財務諸表論」の2科目に加え、「法人税法」または「所得税法」のいずれか1科目が必要です。それ以外の選択科目の相続税法、消費税法、酒税法、国税徴収法、住民税、事業税の中から2科目を選択します。
重要なのは、税理士試験は科目合格制度のため、一度合格した科目は生涯にわたって有効であることです。
つまり、毎年1科目ずつ合格していけば、5年で税理士になることができます。このように、仕事と勉強のバランスを取りながら着実に進めやすいのが税理士資格の特徴です。この科目合格制度こそが、働きながら税理士を目指す社会人にとって最大のメリットといえるでしょう。
一方で、社会人が5科目を取得することのハードさは、税理士の方が書いた下記のコラムにまとまっていますので、ご一読ください。
(3)資格者として登録に必要な2年以上の実務経験
税理士試験に合格しても、すぐに税理士として開業できるわけではありません。税理士になるためには、税理士試験合格後に2年以上の実務経験が必要です。実務経験は「税理士事務所・会計事務所・税理士法人・企業の経理部門」などで積むことが可能です。
一般的には科目勉強と並行し、税理士事務所などで補助業務に携わり、実務経験の取得を同時並行で進めています。また、税理士法第三条によれば「租税または会計に関する事務に従事した期間が通算して2年以上あること」と定められています。登録時点での連続性が問われることもありますので、登録を希望する税理士会へ事前に確認しましょう。
実務経験を積んだ後は、税理士会への登録手続きを行います。この登録が完了して初めて、税理士として業務を行うことができるようになります。登録には登録免許税や入会金などの費用がかかりますが、これらは税理士としてのキャリアをスタートさせるための必要投資といえるでしょう。
■ 効率的な科目選択戦略
前項でご紹介したように、税理士資格の取得には5科目の合格が必要です。税理士試験の科目選択は、その後の勉強計画や将来のキャリアに大きく影響するもの。ここでは「どの科目を、どの順番で」といったような、効率的な科目選択について説明します。
(1)まずは必修科目から!その攻略法は
まず、必須科目の「簿記論」と「財務諸表論」から始めるのが一般的です。これらの科目は税理士業務の基礎となるだけでなく、他の科目の理解にも役立ちます。
簿記論は計算中心の科目で、継続的な練習が必要です。毎日少しずつでも計算問題を解く習慣をつけることで、計算スピードと正確性が向上します。財務諸表論は理論と計算の両方が出題されるため、バランスよく学習する必要があります。
(2)各税法の特徴。後のキャリアに役に立ちやすい科目は?
「法人税法」は最もメジャーな科目で、将来的に企業の顧問税理士を目指す場合には必須といえるでしょう。ただし学習量が多く、働きながら合格するには相当な覚悟が必要です。一方で業務の要となることも多い知識なので、ここを回避した資格者を敬遠する会計事務所もないことはありません。
「所得税法」は個人の確定申告に関する科目で、個人事業主や不動産所得のある方のサポートに役立ちます。
「相続税法」は高齢化社会の中で需要が高まっている分野です。相続税法の改正以降、相談や案件も増加し、税理士としての価値も高まりやすい科目になっています。「消費税法」は比較的学習量が少なく、初学者にも取り組みやすい科目として人気があります。
(3)現職から考える効果的な科目選択
科目は、自分の現在の職業や将来の目標に応じて選ぶことが重要です。
現在の職業が会計事務所勤務の場合、実務で触れる機会の多い科目から始めることで、実務と学習の相乗効果が期待できます。一般企業勤務の場合は、自社の業務に関連する科目を選ぶことで、学習内容を実務に活かすことができるでしょう。
金融機関勤務の場合は、相続税法や所得税法が実務に直結しやすい科目です。不動産業界の場合は、所得税法や相続税法の知識が重要になります。このように、現在の職業と関連の深い科目を選ぶことで、学習効率を高めることができます。
■ 資格学校と独学のメリット・デメリット
社会人が資格勉強をスタートする際、資格の学校に通うか独学で進めるかは重要な選択です。それぞれにメリット、デメリットがあるため、スタートに際して十分に考えることが大切になります。
(1)資格学校に通うメリット、活用法
資格学校に通う最大のメリットは、体系的なカリキュラムと質の高い教材が用意されていることです。税理士試験は出題範囲が広く、独学では何から始めればよいかわからないといったケースが少なくありません。資格学校では、長年の指導経験に基づいた効率的な学習順序が組まれているため、迷うことなく勉強を進めることができます。
また、講師による質問対応や添削指導も大きなメリットです。わからない点をすぐに解決できることで、学習効率が大幅に向上。さらに定期的な模擬試験や答練により、自分の実力を客観的に把握することができます。
(2)資格学校に通うデメリットと対策
一方、資格学校のデメリットとしては、費用が高いことが挙げられるでしょう。多くの場合が、1科目あたり10万円から20万円程度。5科目すべて受講すると相当な費用負担となります。また、決められた時間に通学する必要があるため、仕事のスケジュールとの調整が困難な場合も。特に繁忙期は通学できない回が続いてしまい、そのまま行かなくなって…ということも見られるようです。
これらのデメリットを軽減するために、通信講座やオンライン講座を活用する方法もあります。通信講座であれば、自分のペースで学習を進めることができ、通学時間も必要ありません。また、一部の科目のみ資格学校を利用し、その他は独学で進めるという方法も効果的です。
◆独学のメリットと成功のポイント
独学の最大のメリットは、費用を抑えることができることです。市販の教材と問題集を使用すれば、1科目あたり数万円で済みます。また、自分のペースで学習を進めることができるため、仕事が忙しい時期は勉強量を減らし、余裕のある時期に集中して取り組むことが可能です。中には独学の良さを「自分で判例などを調べる癖がつき、それが実務にも生きる」と話す受験生もいます。
しかし、独学には質問できる相手がいないという大きなデメリットがあります。税法は複雑で理解が困難な部分が多いため、疑問点を相談などで解決できないと学習が停滞する結果に。また、出題傾向の分析や学習計画の立て方など、受験戦略の面で不安が残る場合もあります。
また、勉強仲間もいないことで、モチベーションの維持が難しいという難点もあります。
■ 働きながらでも実践できる勉強法
社会人が税理士試験に合格するためには、限られた時間の中で最大限の学習効果を得る必要があります。ここでは効果的と言われる勉強法について、いくつかご紹介しましょう。
(1)効果的な学習の進め方
まず、テキストを一通り読み終えてから問題集に取り組むという従来の勉強法は、社会人には適しません。時間が限られているため、テキストの重要部分を読んだら、すぐに基礎的な問題を解いて理解を深めるという方法が効果的です。
計算科目については、毎日少しずつでも計算問題を解く習慣をつけることが重要です。簿記論の場合、1日30分でも継続的に問題を解くことで、計算スピードと正確性が向上します。理論科目については、通勤時間などの隙間時間を活用した暗記が効果的です。
(2)過去問と模擬試験を最大限に活用する
過去問演習は合格への近道です。ただし、古い問題をやみくもに解くのではなく、出題傾向を分析して重要な論点を中心に学習することが大切です。また、間違えた問題は必ず解き直しをして、同じミスを繰り返さないようにしましょう。
模擬試験の活用も重要です。実際の試験と同じ時間配分で問題を解くことで、試験当日の時間管理能力を身につけることができます。また、他の受験生との相対的な位置を把握することで、自分の実力を客観的に評価できます。
(3)最新の情報は常に収集を
最新の法改正情報についても、常にアンテナを張っておく必要があります。税法は毎年改正があるため、古い教材だけでは対応できません。専門誌や資格学校の情報を活用して、最新の情報を入手しましょう。
インターネットを活用した情報収集も効果的です。国税庁のホームページや税理士会の情報、専門サイトなどを定期的にチェックすることで、最新の動向を把握することができます。こうした姿勢は、資格取得後も変わらずに仕事に必要なスタンスとなるでしょう。
■ 社会人ならではの時間管理術
仕事と勉強の両立は、本当に大変だった。多くの税理士が語ってくれていますが、その最たる苦労が「時間の確保と使い方」です。では、実際に働きながら資格取得に至った先輩たちは、どのような方法を使っていたのでしょうか。
(1)生活パターンの分析から勉強時間を割り出す
一般的に、税理士試験の各科目には500時間から1000時間の学習時間が必要とされています。これを仕事しながら確保するには、戦略的な時間管理が不可欠です。
まず、自分の生活パターンを詳細に分析しましょう。通勤時間、昼休み、帰宅後の時間、休日の過ごし方など、一週間のスケジュールを書き出してみてください。その中で、勉強に充てられる時間を見つけ出し、習慣化していくのです。
朝型の人であれば、早起きして出社前の1時間を勉強時間に充てることが効果的です。夜型の人は、帰宅後の時間を活用しましょう。ただし、疲れている状態では集中力が続かないため、効率的な勉強法が重要になります。
(2)スキマ時間の効果的な活用
多くの税理士が「スキマ時間」の重要性を話す機会を耳にしてきました。例えば通勤時間も貴重な学習時間です。電車通勤の場合、理論の暗記や問題集の復習に活用できます。車通勤の場合は、音声教材を利用した学習が有効です。昼休みの30分も積み重ねれば、月に約10時間の学習時間を確保できます。
スキマ時間を有効活用するためには、いつでも勉強できる準備が必要です。スマートフォンのアプリを活用した学習や、重要な論点をまとめた単語帳などを常に携帯することで、わずかな時間でも学習を進めることができます。
(3)休日の使い方が合否を決める?
意外に大事なのが「休日の使い方」です。平日にできない計算問題や過去問は、まとめた時間がつくれる休日に行うのが効率的です。ただ一方で、休日全てを勉強に充ててしまうと、疲労による体調不良や「燃え尽き症候群」の心配が…。時には休息やリフレッシュの時間も大切です。
また、ある税理士の言葉を紹介すると「せっかく立てた月ごと年ごとの勉強計画も、必ずしも予定通りに進むとは限りません。思いがけない仕事で、予定が崩れることもしばしば。だから、休日はあえて予定に組み込まず、予備の日程として空けておくのも手です」とのことです。メリハリを利かせながら、効率的な学習を目指しましょう。
■ モチベーション維持の秘訣
毎年計画的に、という進め方ができる税理士試験。それは逆に言えば、長期戦になりやすいことを指しています。特に社会人の場合、仕事の忙しさや疲労により、勉強意欲が低下することがあるものです。
そこでモチベーションを維持する秘訣について、いくつかポイントをご紹介します。
(1)目標設定は明確に
まず、明確な目標設定が必要です。「税理士になりたい」という漠然とした目標ではなく、「3年後に独立開業して年収1000万円を達成する」といった具体的で測定可能な目標を設定しましょう。
また、短期的な目標として、「今年は簿記論に合格する」「来月の模擬試験で上位30%に入る」といった中間目標も設定することで、達成感を味わいながら勉強を続けることができます。
(2)進捗の可視化と成果の実感
勉強の成果を可視化することも効果的です。学習時間を記録する、あるいは問題集の進捗状況をグラフにする。こうしたことで努力が目に見える形で確認できるでしょう。また、模擬試験の成績の推移を記録すると、実力の向上も実感できます。
スマートフォンのアプリを活用して、学習記録を管理することも有効です。日々の学習時間や進捗を記録することで、継続的な学習の習慣を身につけることができます。
(3)仲間との交流や適度な休息
同じ目標を持つ仲間との交流も効果的です。資格学校の仲間との何気ない日常的なやり取り。あるいはインターネット上の税理士受験生コミュニティに参加する。こうした交流から、情報交換や相互激励を行うことができます。一人では挫折しそうになっても、仲間の存在があることで頑張り続けることができるでしょう。
適度な休息とリフレッシュも忘れてはいけません。毎日勉強漬けの生活では、かえって効率が悪くなってしまいます。週に1日は完全に勉強から離れる日を作る、好きな趣味や運動の時間を確保するなど、メリハリのある生活を心がけましょう。
■ 試験直前期の対策と当日の心構え
試験当日は、1年の成果を示す大切な日。その日を万全の態勢で迎えられるよう、直前期には勉強の進捗だけでなく、心身の調整にも気を配りましょう。
(1)直前期の効果的な学習法
税理士試験の直前期は、これまでの学習成果を最大限に発揮するための重要な時期です。
試験1か月前からは新しい問題に取り組むよりも、これまで解いた問題の復習に重点を置きましょう。特に、間違えた問題や苦手な分野を中心に復習することで、弱点を克服できます。
計算科目については、計算スピードと正確性の向上が重要です。同じ問題を何度も解くことで、計算手順を体に覚えさせましょう。理論科目については、重要な条文や判例を正確に暗記し、論述問題に対応できるよう準備しておきます。
(2)体調管理と生活リズムの調整
体調管理も非常に重要です。試験直前になって体調を崩してしまっては、これまでの努力が水の泡になってしまいます。規則正しい生活を心がけ、十分な睡眠を確保しましょう。また、風邪やコロナ、インフルエンザなどの予防にも気を配る必要があります。
試験当日に向けて、生活リズムを調整することも大切です。試験時間に合わせて、頭が最も働く状態を作るために、数週間前から起床時間や食事時間を調整しておきましょう。
(3)自らの準備を信じ、時間配分に注意して
試験当日は、時間配分を意識して問題に取り組むことが重要です。各問題にかける時間を事前に決めておき、時間内に解答できるよう練習しておきましょう。また、見直しの時間も確保しておくことで、単純なミスを防ぐことができます。
緊張は自然な反応ですが、過度に緊張してしまうと本来の実力を発揮できません。深呼吸やリラックス法を身につけておき、試験当日に活用しましょう。また、「これまで十分に勉強してきた」という自信を持つことも重要です。
■ 実務経験の積み方と重要性
すでに述べた通り、税理士試験に合格しても、すぐに税理士として開業できるわけではありません。税理士になるためには、税理士試験合格後に2年以上の実務経験が必要です。どこで、どのように実務経験を積むと良いのか。そのポイントについてご紹介します。
(1)勤務する場所で変わる「身につくスキル」
実務経験を積む場所として最も一般的なのは、税理士事務所や会計事務所での勤務です。ここでは、実際の顧客対応や税務申告書の作成、税務相談などの実務を通じて、試験では学べない実践的なスキルを身につけることができます。
また、企業の経理部門での勤務も実務経験として認められます。特に上場企業の経理部門では、高度な会計処理や税務処理に携わることができ、企業側の視点から税務を理解することができます。これは将来、税理士としてクライアントを持つ際に大きなアドバンテージとなるでしょう。
(2)経験を積む時間を、最大限に活用する
実務経験を積む際には、単に業務をこなすだけでなく、積極的に学ぶ姿勢を持つことが肝要です。疑問点があれば先輩や上司に質問する。新しい業務には率先して取り組んでみる。こうしたことで、より多くの経験を得ることができます。
実務で扱う案件は、試験問題とは異なる複雑さを持っています。この複雑さを通じて、現場における税法の適用方法や、顧客とのコミュニケーション方法を習得。更に、自らの得意分野や興味のある分野を発見する機会にもなるはずです。
(3)人脈づくりとキャリア形成に役立つ時間
この時期に、税理士との人脈を構築することも後に効果を発揮します。同じ事務所の先輩税理士や、セミナーや研修会で出会う先輩税理士。こうした人たちとの関係を大切にすることで、独立開業の際にも大きな支援となるでしょう。
また実務経験を通じて、自分の将来のキャリアプランを具体的に描くことができます。税理士事務所で働き続けるか、独立開業するか、それとも企業内税理士として活躍するか。実際に働いてみることで自分の適性を見極める機会にもなります。
■ 合格後のキャリアプランとステップアップ
最後に、税理士となった後に描けるキャリアプランについて、代表的なものをご紹介しましょう。
(1)安定して多彩な業務を経験できる勤務税理士
税理士事務所や税理士法人で勤務税理士として働く場合、安定した収入を得ながら多種多様な業務に携わるチャンスが得やすいことに気がつくでしょう。顧客対応や税務申告、税務相談など、税理士業務全般を経験することで、実践的なスキルを身につけることができます。
また、事務所の規模や特色によって、扱う業務の種類や顧客層が異なるため、自分の興味や適性に合った事務所を選ぶことが重要です。大手事務所では組織的な業務運営を学ぶことができ、中小事務所では幅広い業務に携わることができます。相続特化や医業特化など、業務や業種に特化した事務所に勤務すれば、特定の分野に深い専門性を磨くことが可能です。
(2)一国一城の主として…独立開業の道
独立開業は多くの税理士が目指すキャリアパスです。自分の事務所を持つことで、業務の選択や料金設定などを自由に決めることができます。成功すれば高収入を得ることも可能ですが、顧客開拓や事務所経営など、税務業務以外の能力も求められます。
開業前には、十分な実務経験と人脈、そして開業資金の準備が必要です。また、開業後の経営安定のために、継続的な顧客との関係構築や、新規顧客の開拓も重要になります。
(3)より深く企業経営に関わる企業内税理士・コンサルタントの道
企業内税理士であれば、上場企業や大手企業の税務部門で、自社の税務問題に専念することができます。一つの企業に深く関わることで、その業界の税務に精通することができ、専門性を高めることができます。
コンサルティング業務への展開も可能です。税務の専門知識を活かして、企業の経営改善や事業再生支援などに携わることができます。これには高度な専門知識と経験が必要ですが、やりがいのある仕事でしょう。
■ まとめ
社会人として働きながら税理士を目指すことは、たしかに簡単な道ではありません。しかし、実務経験や時間管理能力、明確な目的意識など、社会人ならではの強みを活かせば、合格までの道のりを着実に歩むことができます。
効率的な勉強法、科目選択の戦略、モチベーションの保ち方を理解し、自分に合った学習スタイルを築くことが成功の鍵です。本記事で紹介したノウハウを参考に、あなたのペースで確実に一歩一歩、税理士へのキャリアを積み上げていきましょう。