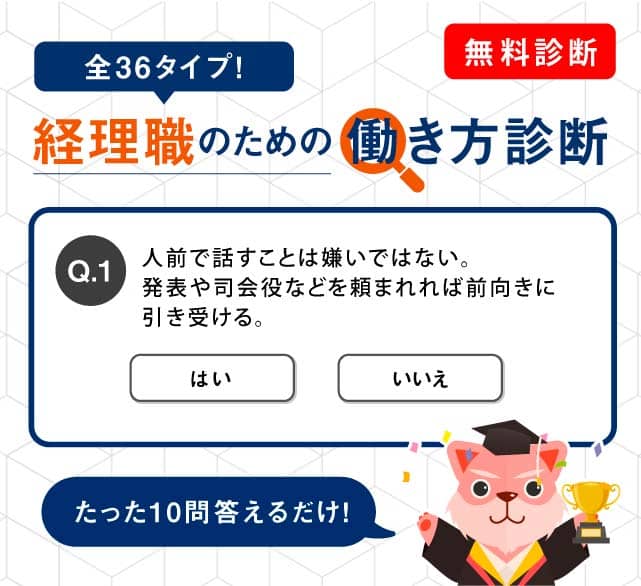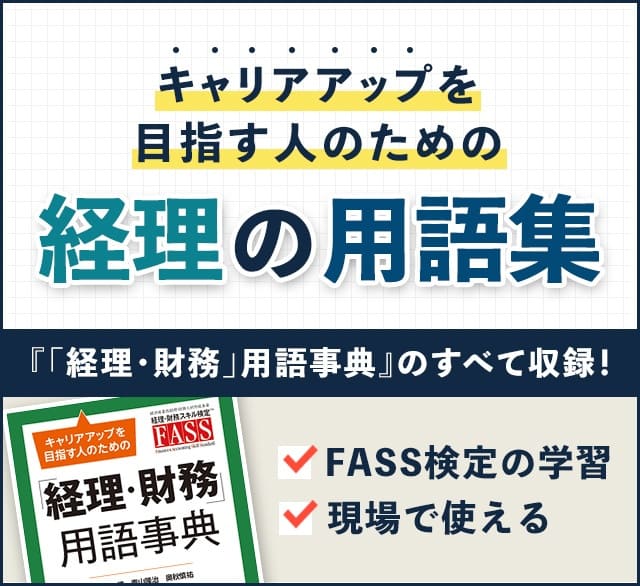1.小口現金と社員立替
どんなに大企業であっても、企業の活動のなかで移動のための交通費や営業の打ち合わせのためのお茶代など、日々細々とした経費は必ず発生します。
このような経費について、簿記の教科書などでは会社の事務所にあらかじめ引き出しておいた「小口現金」を保管し、「定額資金前渡制度(インプレスト方式)」というやり方で精算を行う方法が取り上げられています。

(翔泳社 2014年「3年後に必ず差が出る20代から知っておきたい経理の教科書」小島孝子)
(1)小口現金管理の問題点
このやり方は、従業員数が少ない事業所では、管理が複雑にならず、また、入出金管理を担当者のみが行うことで、管理もしやすいやり方ではありますが、
精算を行わなければならない従業員の数が多くなると担当者の事務負担が膨大になるというデメリット
がありました。また、少額といえども、現金を置いておかなければならないことは、盗難などの危険性もあります。
現金の管理状況は、その企業の「管理体制の鏡」ともいわれています。少額の小口現金であっても監査の対象となり、記帳された現金残高と現金実査による手許現金に相違があれば、内部統制監査(第6回参照)上も問題視される事態となります。
そこで、大手企業などでは、社内に現金を持たないことが一般的となってきています。その代わりに用いられるものが、社員立替による精算です。
(2)社員立替の問題点
小口現金を置かないで、これらの費用が発生した場合には、社員が一時的に立替え、1カ月ごとに立て替え額の明細を作成し、給料の支払いと一緒に精算を受ける「社員立替」の方法で精算を行います。
この方法では、社員が立て替えた金額の明細書を作成し、領収書などの証憑を添付して、経理部門に提出します。経理は提出された精算書や添付資料が「社内規程」に準拠しているか、金額に誤りがないかをチェックし、不備がなければ立替者に振込により支払を行います。

この方法によれば、会社内で現金のやり取りを行う必要がありません。
しかし、
すべての社員が期限内までに精算書の提出を行わなければ、月次の締めに間に合いません。
月次の締めの重要性は、経理部門以外にはなかなか理解されず、このコラムの冒頭で繰り広げられた風景が社内のあちこちで見られるようになってしまいます。
コピー用紙にレシートを並べて貼り付け、外回りのスケジュールを確認しながら、運賃を調べてエクセルのワークシートに集計する・・・事務作業に慣れてない社員にとって、最も苦痛な時間であるかもしれません。
また、それを受け取った経理部門でも、電卓を使って1件1件チェックし・・・と、経理部署における作業負担も膨大にかかる作業となってしまいます。これは、
すなわち人件費の増加にもつながる問題
となってしまったのです。
2.2000年代以降の経費精算
(1)経理部門におけるBPOの活用
経理部門の人件費負担を抑えるため、上場企業などの大企業では、2000年代前半から海外の企業へ経理業務を委託するBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)により、この問題の解決が図られました。
アウトソース先は、中国、ベトナム、ミャンマーなどのアジア諸国が中心で、精算書ごと現地に送り、現地作業員がチェックや仕訳入力作業といったデータ化の処理を行い、データで戻してもらうというやり方です。
海外でのBPOのメリットは、内外価格差により人件費を大幅に押さえられる点でした。しかし、こういった諸外国も2010年代に入ると経済成長が著しく、委託料も上昇傾向にあります。また、現地の言語で作成された詳細な指示書や日本語のわかる仲介者がなければ、精度の問題も出てしまいます。そこで、近年ではこの問題をシステムで解決しようという動きが一般的になってきました。
(2)多種多様経理精算ソフトの乱立
大手から中小企業まで含めた大問題であったこの立替経費問題は、多くのソフトベンダーがしのぎを削り、経理業務の中でも最も急激な進化を遂げてきました。
ソフトによる一般的な作業フローは、経費の立替者が領収書をPDFなどの画像データでソフトにアップロードすると、その画像データをOCR解析し、日付や支払先、取引内容、金額などを読み取り、そのデータをもとに自動仕訳を生成します。
また、領収書を読み取るスキャナーも開発が進み、ベンダーソフトと連携したドキュメントスキャナーで、毎分30枚以上の高速での読み取りが可能なものもあります。
(3)読み取りからキャッシュレス決済へ
メーカーの努力により、スキャナーの精度が上がっても、領収書そのものの読み取りによるデータ化の作業は残ります。また、使用文字数が多い日本語を100%の精度で読み取ることはまだまだ難しいのが現状です(第2回参照)。
そのため、現金による立替は、まだまだ多くの経理処理の時間を要します。
そんな中、大きな展望が期待されるのが、経済産業省が行うキャッシュレス決済推進の取り組みです。
API(Application Programming Interface)
という技術により、会計ソフトが銀行のネットバンキングやクレジットカードの利用履歴のシステムと直接連携し、これらのデータをソフトに直接取り込むことが一般的となりつつあります。
また、これにAIを搭載し、過去の取引履歴などから自動仕訳で生成することが可能なソフトも開発されています。
(4)消費税増税とキャッシュレス還元
さらに、Suica に代表されるICカードや中国でキャッシュレス決済を普及させるきっかけとなったAlipayやWeChatPayと同様のバーコード決済など多種多様なキャッシュレス決済は、2019年10月からの消費税増税に伴い、税負担の緩和措置として行った「キャッシュレス・消費者還元事業」により、多くの人がその利便性を体験する機会を持つことになりました。
これにより、今まで以上にキャッシュレスが浸透すれば、経費をあらかじめ立替えするというオペレーションすらなくすことが可能となるでしょう。
このような事情も受けて、
政府与党は2020年度の税制改正大綱において、クレジットカードなどのデータを領収書の保存と同様に扱えるよう、電子帳簿保存法の施行規則の改正を予定しています。
まさにキャッシュレス元年ともいえる、令和元年を締めくくる発表といえるでしょう。
3.キャッシュレス戦国時代の経理の役割
こうしたキャッシュレス決済の乱立は、会社内部におけるルール付けが重要となります。
せっかく便利なキャッシュレス機能であっても、自社のオペレーションに不向きな方法を採用してしまっては利便性が損なわれてしまいます。
また、クレジットカードなどの後払い決済では、予算管理を徹底しなければなりません。そのため、
「経理規程」をアップデートするスピードは、システムの進化にあわせ、加速度的に進みます。
これまで多くの時間を費やした立替精算の業務が大幅に削減できる未来、それは本当にAIにより、経理がいらなくなる未来なのでしょうか?
その答えはもちろん
「NO」
。
金庫における小口現金の時代からキャッシュレス決済の現代まで、常に進化し続ける経理環境において、そのルールを進化させ続けてきたのは経理に携わる人間であり、これからもAIの仕事ではありません。
経理に求められる力は、目まぐるしく変わる経済環境の中で、これまで以上に変化を受け入れ、ルールを作り、社内の指揮を執る、本当の意味のアカウティング(説明)能力となっていく
のではないでしょうか。
関連リンク