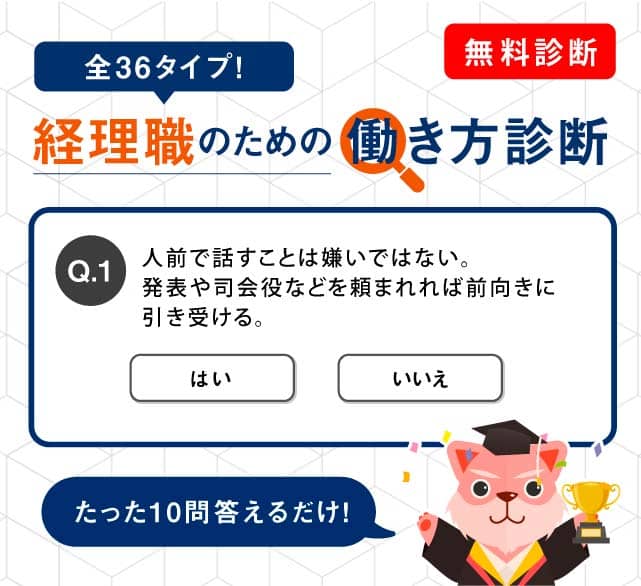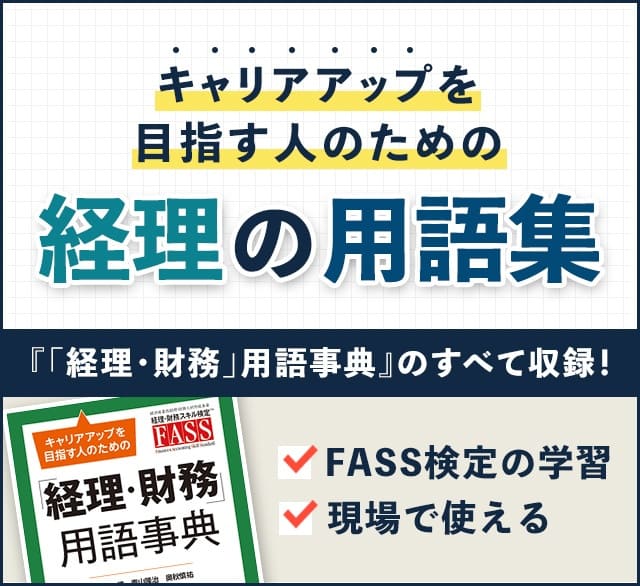1.「お金」は危険と隣り合わせの関係にある
20世紀の日本において、現金は決済手段のメインとなっていました。しかし、お金は持ち主が書かれていないため、常に盗難リスクにさらされています。
これは、社内における業務においても同様です。飲食店や小売店などのお金を扱う業種については、日々現金出納帳やレジ金の集計表などを作成し、1日の終わりに実査を行い、確認を行う必要があります。お金が記録と合わなかった際は、その原因を突き止めなければならず、現金を持つことは確実に経理部署の負担が増えることとなっていました。
2.会社内部から消えつつある「お金」の存在
そのため、最近では会社がなるべく現金を持たないような方法が採られています。売上は、小売店や飲食店などの店舗型のBtoC取引以外では銀行振込が主流となっています。
そのため、多くの業種で、今やお金のやり取りは銀行口座の管理を行うだけで済むようなオペレーションとなっています。
第1回の「売掛金管理業務」でもご紹介したように預金の入出金管理は、これまでは入出金伝票や預金通帳などの証憑をもとに仕訳入力を行い、その仕訳を元に管理していましたが、自社システムと銀行のネットバンキングのシステムを結ぶAPI連携の技術によって、多くの会計ソフトで銀行データを直接取り込むことが可能となりました。そのため、入出金管理は、
あと少しで人の手を介さずデータ化できるところに近づいています。
3.キャッシュレス決済の発展
しかし、そうはいっても前述のように
店舗型のBtoC取引ではいまだに現金取引が主流
です。以下のグラフは先進国におけるキャッシュレス決済の比較をした図になりますが、
日本はわずか20%にも満たない比率
となっています。キャッシュレス決済の先進国といわれる中国や韓国の半分にも及びません。
このようにキャッシュレス化が遅れた原因はどこにあるのでしょうか?
4.現金の信頼度が低い中国と信頼度が高い日本
(1)中国におけるキャッシュレス決済のインフラ化
中国では、偽札が流通するなどの現金の安全性の問題が存在していました。貨幣製造の技術が乏しく、国民が貨幣を不安視する問題が従来からあったのです。そのため、2000年代から発達したキャッシュレス決済は、多くの国民に支持されました。また、近年、その傾向をさらに推し進めたのがアリペイ(Alipay-中国名「支付宝」)の存在です。
バーコードを利用した技術はオンライン、オフラインの双方での決済が可能であり、これにより小規模な店舗であっても多額の設備投資の必要がなくキャッシュレス決済を取り入れることが可能となったのです。また、アリペイは、一つのアプリを通じてタクシーやホテルの予約、映画のチケットの購入、公共料金の支払、病院の予約、銀行振込、投資商品の購入など生活に必要なさまざまなサービスで利用することができ、中国における生活インフラといえるアプリと化しています。
(2)日本における現金の安全性とフレキシビリティー
これに対し日本では、お年玉や大入り袋などもともと現金を好む国民性があっただけでなく、透かしやホログラムを利用した
高度な偽札防止技術を備えた紙幣発行の技術力が現金への多大な信頼へとつながっています。
また、POSレジの処理能力の高さやすぐに現金が手に入れられるほどに発達したATM網のおかげで、
諸外国に比べて圧倒的に現金支払いがしやすい環境が醸成されていた
ため、「あえて現金を使わない理由がない」というところがキャッシュレス化の遅れた最大の原因と言えるでしょう。
また、近年の人手不足の対応として、飲食店などで用いられるタッチパネルを利用した無人レジやスーパーなどで用いられるバーコード読み取り型の無人レジが徐々に普及し始めています。さらに、ユニクロやGUの店舗で利用されているRFID(radio frequency identifier)タグという技術は、IDチップと小型アンテナが一体化された小型回路のようなものを商品タグに埋め込むことで、無線通信によって商品を入れた買い物かごごとタグを読み取り、スピーディーな決済額の集計を可能としています。
5.会計から見るキャッシュレス化の遅れ
しかし、企業の経営戦略の面でむやみにキャッシュレス化を進めればよいというわけではありません。その理由を会計面からみていきましょう。
「企業が原材料や商品仕入などへ現金を投入してから、最終的に現金化されるまで」
(キャッシュ→商品→支払い→販売→回収)の
日数を示す
もので、以下のように算定されます。
営業サイクル :商品を仕入れてから、売上代金を回収するまでの期間
棚卸資産回転期間 :棚卸資産(在庫)が月商の何カ月分あるのかを示す指標
売上債権回転期間 :売上債権の回収期間
仕入債務回転期間 :商品や材料等を仕入れてから決済されるまでの期間
例えば、一般的な小売店のモデルを用いると、CCCは下記のように75日(※)と算定されます。
【図1:小売店のCCCモデル】
このモデルケースの場合、資金が在庫または売上債権として拘束される間に買掛金の支払い期限が到来することになるので、CCCの期間(75日)だけ資金が必要となります。そのため、企業はこの期間分の余剰資金が必要になり、このキャッシュインとキャッシュアウトのギャップが埋まらない場合には銀行借り入れ等で補填する必要が出てくるのです。
CCCを短くするには、棚卸資産回転期間、売上債権回転期間を短くし、仕入債務回転期間を長くすることが重要
です。つまり、入ってくるお金は早めに回収、出ていくお金はなるべくあとにすることによって、剰余資金を持たなくてはならない日数が減るということになります。
その点を踏まえて、現金決済を主たる決済手段とした飲食店のモデルを見ていきましょう。
6.サイゼリヤのCCCにみる飲食店における現金決済の重要性
飲食店においては、小規模店、大手チェーン店問わず、いまだ現金決済が主流です。その中でも「サイゼリヤ」は、キャッシュレス決済に対応しない飲食店代表例ともいえます。上記、算式を元に、サイゼリヤのCCCを算定すると以下のようになります。
【図2:サイゼリヤのCCCモデル】
(株式会社サイゼリヤ 第46期「有価証券報告書」(EDINET)より筆者算定。)
サイゼリヤのモデルは、売掛金が発生しないことから、小売店に比べ営業サイクルが早いことが最大の特徴となっています。
また、支払債務回転期間が1カ月強と短い期間であることに対し、棚卸回転期間が長いことで資金需要は3日程度で足りることになります。しかし、一般的な飲食店のモデルでは、棚卸回転期間は1.5週間程度(10.5日)と比較的短いことから、CCCはマイナスとなる傾向があります。
【図3:一般的な飲食店のモデル】※現金決済のみの場合
仮に支払債務回転期間をサイゼリヤと同様とし、棚卸回転期間を1.5週間(10.5日)と設定した場合には、CCCは-27.68日となります。これは、商品の販売代金がそのまま仕入債務の支払に充てられることを意味します。そのため、現金決済のみを行う事業においては、
支払いのための余剰資金を持っておく必要がない
といえます。
図2
と
図3
を見比べていただくとわかりますが、
サイゼリヤのCCCが一般的な飲食店のモデルよりも長くなる要因は、棚卸回転期間の長さ
です。これは、関税率を下げるためオーストラリアの自社工場で加工した食肉を輸入していることや、人件費を押さえるためセントラルキッチンでいったん調理した料理を各店舗へ配送していることなど、
コストを抑える企業努力が背景にある
と考えられます。
すなわち、
低価格で提供するための最大限の努力が棚卸回転期間の長さに影響している
のです。そのため決済資金に余裕を出すためには、
売掛債務を生じさせないこと(図1における売上債権回転期間をつくらない)や、たとえ数日でもキャッシュレス決済による企業への入金タイミングの遅れをつくらないことがサイゼリヤの低価格戦略を維持するためのキーポイント
となっていたのです。このように、キャッシュの動きは経営戦略に多大な影響を与えます。
CCCを縮めつつ低価格で美味しいものを提供しようとするサイゼリヤの経営戦略には、他の飲食店よりもいっそう現金決済が重要であるということがわかります。
7.キャッシュレス化がもたらす会計の未来への影響
キャッシュレス化の波は、今後さらに加速化していくことでしょう。これにより、経理の未来はどのように変わっていくのでしょうか。
(1)キャッシュレス化における「業務の守り」の側面
諸外国がキャッシュレス化に傾いた原因と同様に人手不足の波は政府による政策としてのキャッシュレス化を推し進めています。会計業務においては、決済手段がキャッシュレス化することで、
仕訳エントリーの手間がなくなり、省力化だけでなく、より正確な帳簿の作成が可能となります。
また、前回(
「第2回 買掛金管理業務」
)で確認したような物理的な紙の情報がなくなるため、
会計に必要な情報をすべてデータで取得することが可能となりうる
のです。
実際に、政府のキャッシュレス化の取り組みの中には
「会計や財務管理の電子化と合わせることで、納税の自動化促進にも貢献。行政側から見ると収税面の効率化が図られる。すなわち、キャッシュレスは、これまでかかっていた行政コスト(収税コスト)という社会コストの削減に寄与するものであり…、」
(経済産業省「キャッシュレス・ビジョン≪要約版」より)という表現もあり、徴税コストの面からキャッシュレス化が会計にもたらす影響を期待しているのです。
(2)キャッシュレス化における「業務の攻め」の側面
一方、6でお話ししたCCCを踏まえればわかる通り、
利便性だけで決済手段を変更ができない理由がある
ということも忘れてはなりません。経済環境の目まぐるしい変革期の中で、企業は生き残るための最善の選択をしなければなりません。
その時こそ、
会計の出番
なのです。 AIによる第四次革命期とも言われる現代は、電気と石油がもたらした第二次産業革命によって時代の変革期にあった明治時代のように、経済の大きな変革期であることを期待されています。そのような時代において、企業の生き残りの鍵を握るのは、
会計データの分析から生み出される経営戦略
です。
この経営戦略を誤らないようにするのは、
CCCのような会計がもたらす情報の活用技術
なのです。労働力不足の現代は、渋沢栄一の活躍した明治時代同様、社会の発展を実現するために必要な人材と資本を結集し、乗り越えなければなりません。
この新時代においても、渋沢のような、新時代を作るリーダーが多数生まれることでしょう。しかし、そのリーダーを支える真の力こそ、経理を中心とした会計のプロフェッショナルの存在なのです。
関連リンク
このカテゴリーの他の記事を見る