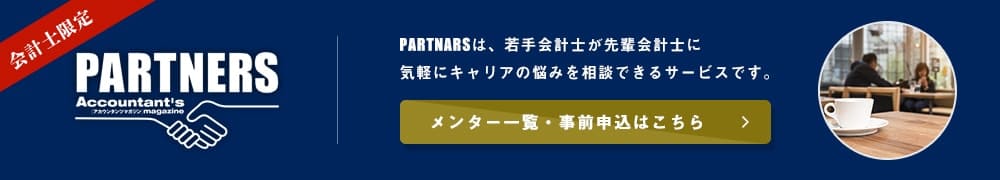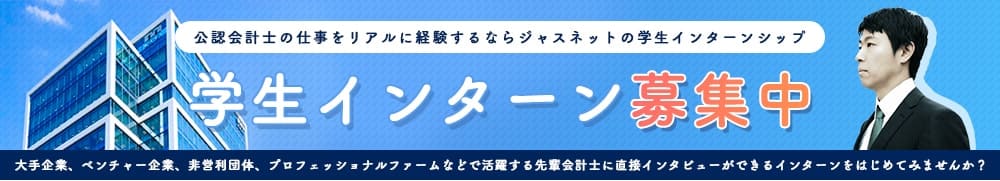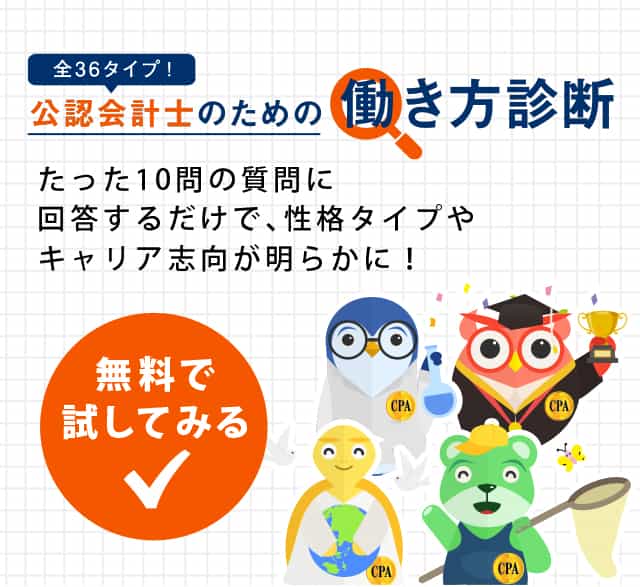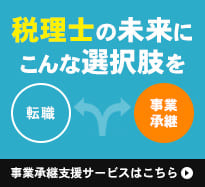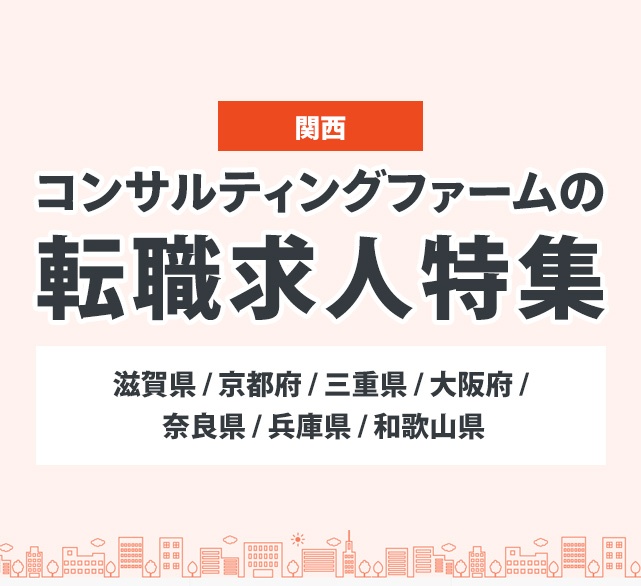【会計士が一番最初に読む IPO入門講座】
第2回 IPO準備の基本(2):IPOできる会社・できない会社の違い

2020年4月24日 齊藤 健太郎
目次
1. IPO件数と動向
2024年から25年にかけてのIPO市場は、世界経済の影響を受けつつも、新興企業の成長資金調達の手段として一定の重要性を維持しています。特に、 AI、脱炭素、ヘルステックなどの成長分野では上場の動きが活発化 するとされているようです。一方で、金利の上昇、インフレの進行や台湾問題などの地政学リスクなどの影響により、市場全体の慎重な姿勢は継続する見込みを行っているところもあるようです。
本章では、昨年2024年のIPO動向、資金調達額、各市場の傾向、地方取引所の状況、プロ投資家向け市場(TPM)の最新トレンドについて解説します。
(1) 2024年のIPOの動向
① 2024年のIPO市場の特徴
2024年のIPO市場の動向を理解するために、まず過去数年間の市場環境を振り返るとおおよそ以下のような流れになります。
-
2021年:IPOブーム
☆コロナ禍での金融緩和政策を受け、スタートアップ企業が積極的にIPOしました。
☆日本国内では125社が上場し、年間のIPO件数が過去10年で最高水準になりました。 -
2022年:市場の冷え込み
☆米国の急激な利上げや、世界的なインフレ懸念が影響し、IPO市場は縮小。
☆日本国内のIPO件数は91社と前年から大幅に減少しました。 -
2023年:回復の兆し
☆金融市場の落ち着きとともに、IPO市場は徐々に持ち直しました。
☆ただし、大型IPOの減少が顕著で、資金調達規模はやや縮小しました。
2024年は、これらの流れを引き継ぎながら、以下のような要因がIPO市場に影響を与えたと考えられます。
| 要因 | 影響 |
|---|---|
| 金利動向 | 金利が高止まりし、投資家のリスク選好が低下し、IPO市場の勢いが削がれた可能性あり。 |
| インフレ | 企業のコスト増がIPO後の業績に悪影響を及ぼす可能性。 |
| 地政学リスク | 米中関係、ウクライナ情勢、中東情勢などが不安定要素として作用。 |
② 2024年のIPO市場について
2024年のIPO市場は、以下のような特徴があったのではないでしょうか。
-
選別型のIPOが主流となった
☆収益基盤が安定していない企業は、IPOを延期または断念するケースが増加したと思われます。これは、市場再編の影響かもしれません。 -
成長分野への投資が集中した
☆AI、脱炭素、バイオテクノロジーなどが注目分野に投資が集中しました。 -
上場後の株価パフォーマンスが重要視される
☆直近のIPOでは、初値が公募価格を大幅に上回るケースが減少しました。これは2022年1月に公正取引委員会が、企業の新規上場時の公開価格に関して、証券会社が一方的に低い値付けをすることは独占禁止法に違反する恐れがあるとの見解を示したことの影響が実務的に浸透してきたことによるものと考えられます。
☆投資家が上場後の成長性をより重視する傾向が強まっているようです。
(2) IPOによる資金調達額の推移
IPO市場の活況度を測る重要な指標として、企業がIPOによって調達する資金額がありますが、過去5年間のデータを見ると、市場の環境変化に応じて調達額が大きく変動しています。
| 年度 | IPO件数 | 資金調達額(億円) |
|---|---|---|
| 2023年 | 96 | 5,900 |
| 2024年 | 86 | 19,162 |
直近2期間のIPO件数、調達金額は上記の通りです。それまでの2021年のIPOブーム時には、調達額が増加しましたが、 2022年以降は、IPO件数が減少し、調達額も縮小傾向 にありました。
その後、2024年は、東京地下鉄(9023、10月23日上場、調達額3,486億円)やキオクシアホールディングス(285A、12月18日上場、同7,843億円)といった大型案件が、年度全体の調達額の増加につながったようです。
(3) 2024年におけるプライム、スタンダード、グロース市場のIPO動向
2022年4月の市場再編により、東京証券取引所は「プライム市場」「スタンダード市場」「グロース市場」の3市場に分かれました。2024年の各市場におけるIPOの動向は以下のようになります。
プライム市場(大企業向け)
- IPO件数は4件と少なく、大型案件が中心でした。
- グローバル投資家の関心が高く、ESG要素が重視されたようです。
- 時価総額500億円以上の企業が主な対象となりました。
スタンダード市場(中堅企業向け)
- 伝統産業の企業が多く、安定した収益モデルが求められました。
- IPO件数は13件とプライム市場より多いですが、調達額は小規模でした。
- 2024年は製造業・ITサービス業の上場が多かったです。
グロース市場(成長企業向け)
- スタートアップ企業のIPOが活発化しました。
- AI、バイオテクノロジー、再生可能エネルギー関連企業が注目されました。
- 2024年のIPOは、64社と全体の74%を占め、市場全体を牽引しました。
2. IPOできる会社とできない会社
いま日本では、 IPO準備企業は、それぞれの進捗に差はあれども、1,000社程度 存在しています。毎年100社弱の会社が上場するわけですので、すべての会社は上場できるわけではありません。
それでは、どのような会社は上場ができ、どのような会社が上場できないのか。経営者が会社を上場させようと考え始め、 上場準備を開始すると、各段階で上場の可否が分岐 していきます。
この各段階は下記の3つになります。
(1) 主幹事証券会社や監査法人が入る前後の段階
(2) 主幹事証券会社や監査法人が関与をはじめ上場準備を行う段階
(3) 上場直前
あと少しで上場できるというところで上場を行わないという段階に分けて、それぞれ考えてみたいと思います。
(1) 主幹事証券会社や監査法人が入る前後の段階の選別
ここでは、会社側の視点に立つケースと主幹事証券会社や監査法人側の視点に立ってみていくケースに分けて考えていくとわかりやすいかと思います。
まず企業の内部から見たIPOできる会社とできない会社の違いを解説します。
① IPOの検討・準備に入る時期の見極めに過大に対応してしまう
企業は上場を通じて資金調達を行います。株式市場が好況なときは、IPO市場も活況であり、市場が活況であれば少ない株数で多くの資金を調達することが可能となります。この点でIPOは、景気動向に左右されることになります。
ただ、そのような 景気動向でIPOの可否を判断するよう会社はそもそも上場すべきではありません。
なぜならIPOは一朝一夕で成し遂げられるものではなく、最低上場する申請期の直前期、直前々期が審査対象年度として監査法人の監査証明が必要となり、また直前々期以前には、監査法人に受嘱してもらうための調査も必要となりますので、どんな会社でも3年はかかります。景気は循環するので、いざIPOする時期になったらどのような経済状況になっているかは分からないものです。
株式市場が良くないから上場準備をやめる、というような企業は、逆に株式市場が良くなってもIPOはできません。つまり上場ができない会社です。
コロナウィルスの影響があった中でも一定数の企業が上場を成し遂げました。
どのような環境下でも自社のおかれている環境を冷静に分析して成長戦略を示すことがCEOには求められます。
したがってIPOの検討・準備に入る時期は景気動向云々ではなく、
中長期的なビジョンをしっかり持てた時期に上場準備を開始するというのが一番望ましい
のです。
そのような企業はIPO想定時期までに必要な対応・書類の準備を完了しており、もし株式市場の市況がその時点であまり良くなければ、回復するまでに時期を待つということも十分にできます。
- 経営者が経理部門などの間接部門に、人件費やその他のコストをかけたくない
- 経営者自身が、自社のことは自分が一番理解していると思い、月次決算、予実管理といった計数管理は必要性を感じていない
こうした考えは、初期のシード、アーリーステージ段階にある企業であれば問題はないです。しかし、組織規模が大きくなると CEOが隅々まで理解できる物理的限界が訪れます 。製品・サービス別や部門別・場所別などの売上高・利益について正確な情報を把握することはできません。このため月次決算をはじめ計数管理を行わないと自社の成長を数値でもって説明できなくなります。
その結果、 自社の業績が数値でもって説明できず、適切な予算編成を行うことがかなわず、予算と実績値の差異を分析できない ということが起こります。この結果として、上場できないということになってしまいます。
② CEOのコーポレート・ガバナンスに対する考え方がどうしても意にそぐわない
IPOを検討している企業のCEOはすべからく自社を成長させてきた方々であり、この点について高く評価されるべきです。
一方で組織を構成する人員が多くなってくると組織マネジメントの重要性が増し、権限移譲と内部統制の両輪で大人数の組織を動かしていかなければなりません。しかしながら、 CEOがそれまでの経営手法を変えることができず、同じ目線を従業員に求める ことになります。これは、ある程度まで成長した企業がIPOできないパターンといえます。そうしたことが起こるのは、下記のように考えられます。
③ 必要となるJ-SOX対応について十分に対応できない
財務情報を企業外部の第三者に説明できるレベルで正確にするためには、社内ルール、業務フロー・マニュアルが整備され、業務が適切に運用できる仕組みが構築されていなければなりません。
上場企業には内部統制報告制度が設けられており、IPO準備においては、J-SOX対応が可能となるように社内体制を整備していくことが求められます。本来、自社の業務に関する情報を効率的かつ効果的に正しく経営者が把握できるようにしておくことは、会社にとって整備すべき課題です。
そうしたインフラの下で初めて経営理念及び経営者のビジョンに沿って従業員が動くことができるのです。 組織の成長とともに「コーポレート・ガバナンスの在り方を変えなければならないということを理解できるかどう 」がIPOを可能にするかどうかにおいて大変重要なエッセンスとなります。
次に企業の外部から見たIPOできる会社とできない会社の違いを解説します。
④ 会社の利益水準が十分ではない
会社が上場するには、多額の資金を要します。管理部門の充実、監査法人との間の監査契約の締結、社外役員や常勤監査役の選定と設置、内部監査部門も設置など、CEOからみてコストと要するようなことを社内に取り入れていかなければなりません。
こうした体制構築には多額の資金を要します。 主幹事証券会社によっては、上場をしたい会社がこうした社内体制を構築することが可能かどうかは、会社の資金力をもとに判断 します。具体的には会社の利益水準が一定以上持っていないと社内体制の構築のためのコストを割くことができないため、上場準備作業が遅延します。
いくら上場を望んでいても利益水準が十分ではない会社に対しては、主幹事証券会社が、主幹事契約を締結することはほとんどありません。
⑤ 会社の株主や主要な取引先に反社会的勢力との関係があるものがいる
上場会社は、すべて 反社会的勢力との関係が遮断されていなければなりません 。しかしながら、上場準備段階で反社会的勢力に属する方が役員や株主、主要な取引先にいるような場合、主幹事証券会社や証券取引所はそのような会社を受け入れることはありません。
(2) 主幹事証券会社や監査法人が関与をはじめ上場準備を行う段階
一定の利益水準が確保され上場準備に入ったにも関わらず上場を断念するケースとしては、下記のように様々な要因があります。
- ① 会社の利益計画が十分に検討されて構築しない場合
- ② 会社の利益計画が繰り返し未達であり会社の業績を安定的に追うことができない場合
- ③ 会社と利害関係者の関連当事者取引が厚く、実質的に会社が上場することに懐疑的な場合
- ④ 適時開示のための社内体制の構築ができず取締役会を迅速に開催することができない場合
- ⑤ 公認会計士監査のための資料を十分に行うことができず、監査証明を提出することができない場合
①
会社の利益計画が十分に検討されて構築しない場合とは、簡潔にいうときちんと
予算を組めない会社
ということになります。
予算を組めない会社の業績を把握することができないと、自社の業績を株主に説明することができないことになるため、このような企業は上場できず断念することになります。
②
利益計画を作成しているにもかかわらず、いつも予算を達成していない企業というものも存在しています。この場合、会社を取り巻く市況が悪いとかの外的要因もありますが、
きちんと自社の属する業界動向を把握していない、現場が数値にコミットした行動をとらない
など、何らかの問題がある会社がほとんどです。
このように予算を達成できない会社には、株主は安心して出資することをためらうことになるため、このような企業は上場できません。
③ 会社の経営者がいかに上場を望んだとしても、 経営者一族の他企業が上場に懐疑的 で結局上場を断念したというケースがあります。上場して株式を「公開」するということは、全くの外部者が株をもって企業の成長に投資することになるわけですから、自社の問題というだけではなく、オーナーと密接な関係を持つ会社との取引関係を清算したり、資本関係を清算するということが往々にしてあります。
こうした企業は、それぞれの会社は親族同士で支えあっているということもあることから、経営以外の反対により上場を断念することになります。
④ 適時開示のための社内体制の構築ができないというのは、簡単に言うと 会社の経理体制を構築できず、迅速に会社の業績を把握することができない ということになります。こうした課題はよく耳にします。月次決算の早期化という切り口で課題解決策を下記のコラムにて紹介していますので、その内容を確認しながら対応してみてください。
⑤ 自社の作成した財務諸表には何らかの根拠があって入力されているはずが、資料が全く整理されておらず、 公認会計士監査を受けられる体制にない状態 のことを指します。このような場合、監査法人はどの資料を基に監査を進めていけばよいのかわからないので、監査証明を出すことができず、結果上場を断念するというケースになります。
(3) 上場直前
(1)(2)の課題をすべてクリアしたにもかかわらず上場を取りやめる場合もあります。
例えば、下記3つのケースになります。
- ① 上場前に決める売出株式の価格が想定していた価格よりも低く、株式の売出を取りやめる場合
- ② 上場する段になって何らかの理由でCEOが自身に注目が集まることを恐れ、急に雲隠れする場合
- ③ 監査法人が行政処分を受けて、その監査証明に依拠して上場するわけにはいかないと取引所が拒絶する場合
①
取引所の上場承認がおりると、残るは証券界者が上場企業の株式をいったん引受けて市場に対して株を売却することになります。
これらのことを
公募売り出し
といいますが、
会社が望んだ株価と主幹事証券会社が想定した株価との間で乖離が見られる
ことがあります。この場合、会社は株価が折り合わないことを理由に上場を取りやめることがあります。
② 会社が上場すると経営者の略歴は丸裸にされます。そのため、 学歴、社歴などを隠したい人は上場を目前にして会社を売却してしまい、上場を取りやめる というケースもあります。完全に経営者のわがままですが、実際に目の当たりにしたことがありますので、こうした些細なことも本人にとっては重大問題ですので、上場を取りやめる理由にもなってしまいます。
③
上場するためには、監査法人監査を受けなければならないことは当然ではあるのですが、
肝心の監査法人が行政処分を受けた結果、業務停止命令を受けてしまい、上場が流れてしまう
ことがあります。
取引所の言い分はこのような問題を起こすような監査法人が行う監査結果は信用できないということなのですが、実際に目の当たりし、監査難民になってしまう企業をいくつか見てきました。
3. まとめ
上場準備を行ってプロジェクトとしても進めたとしても順調にいくような企業はまずないと思います。その中において、会社は上場を断念する瞬間というものあり得ますので、他社事例として参考にしていただけるとよいかと思います。
- 第1回 IPO準備の基本(1):IPOする目的の整理
- 第2回 IPO準備の基本(2):IPOできる会社・できない会社の違い
- 第3回 IPO準備の基本(3):IPO準備において求められる体制
- 第4回 IPO準備の基本(4):IPOすべきではない会社について
- 第5回 IPO準備の基本(5):IPOスケジュールについて
- 第6回 スケジュール別IPO準備:IPO3年~4年前に対応すべき事項
- 第7回 スケジュール別IPO準備:IPO2年前(直前々期)に対応すべき事項
- 第8回 スケジュール別IPO準備:IPO1年前(直前期)に対応すべき事項
- 第9回 スケジュール別IPO準備:申請年度に対応すべき事項
- 第10回 IPO達成後の企業の在り方
関連リンク
- USCPA資格取得で開けるキャリアとは? 年収・転職先・成功事例を徹底解説
- 【会計士が一番最初に読む IPO入門講座】
- 【会計士が一番最初に読む IPO入門講座】
- USCPA(米国公認会計士)の年収は?監査法人、税理士法人から事業会社まで
- USCPA(米国公認会計士)が活躍できる転職先と、そのメリット、デメリットは?
- 【第3回】監査や経理の担当者が知っておくべき!『モダンExcel』(全10回)
- 【第2回】監査や経理担当者が知っておくべき!『モダンExcel』データ分析超入門(全10回)
- 【第1回】監査や経理担当者が知っておくべき!『モダンExcel』データ分析超入門(全10回)
- 初めての株式鑑定評価~公認会計士として、意識しなければならない点とは?【第2回】
- 初めての株式鑑定評価~公認会計士として、意識しなければならない点とは?【第1回】
- 執筆者プロフィール
-
齊藤 健太郎(さいとう けんたろう)
ジャスネットコミュニケーションズ株式会社 エグゼクティブエージェント
公認会計士・税理士/齊藤公認会計士事務所横浜国立大学経済学部卒業
横浜国立大学国際経済法学研究科修了:専攻は会社法
- 2003/2-2006/9
- エイチエス証券株式会社引受審査部所属
- 2006/9-2010/7
- あずさ監査法人第5事業部(IPO専門部署)所属
- 2010/8-2012/10
- あずさ監査法人 IT監査部所属
- 2012/10-2017/11
- LINE株式会社 内部監査室 マネージャー
- 2017/11-2020/9
- ライフアンドデザイングループ 取締役CFO
- 2020/10-2023/1
- 日本M&Aセンター TPM事業部 上場審査部 JQS