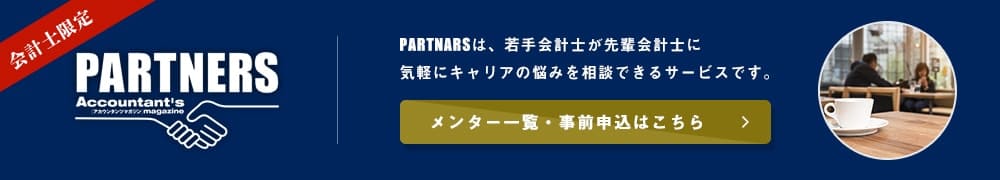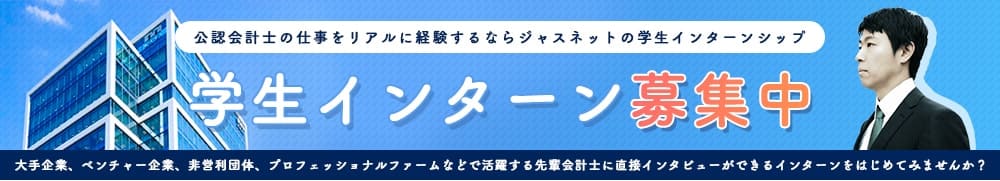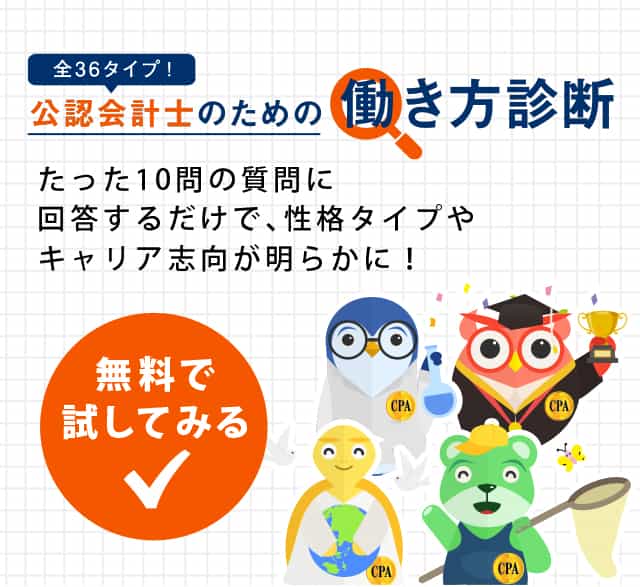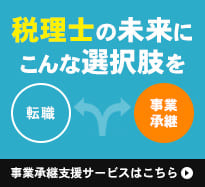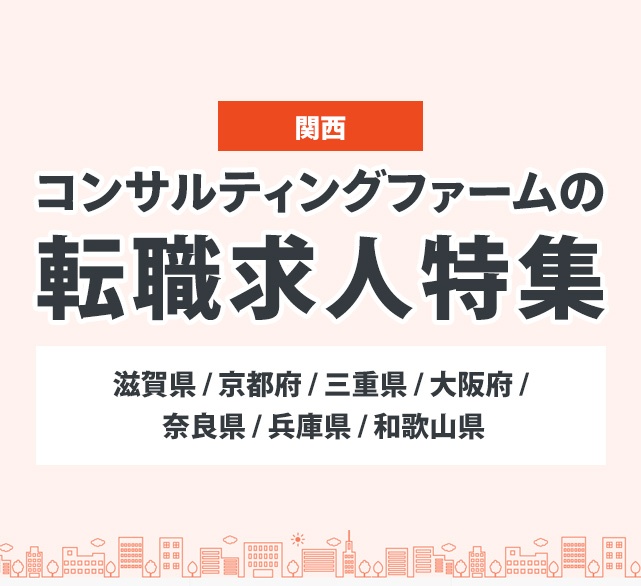■ 予算の全体的な枠組み
予算とは、
企業で決められた数値目標
のことを言います。もう少し具体的に言うと、売上予算の場合は「どのくらいの売上を目標とするか」、経費予算の場合は「経費をどのくらいまで抑えるか」などの目標値が予算となります。
予算には、
「予算編成」
と
「予算統制」
という言葉が使われます。
この「予算編成」と「予算統制」は、会社が適切な予算を作り、それを実際に運用する上において重要な概念となります。
予算編成:
予算統制:
上場審査ですと、
「予算編成のプロセスが会社の状況に照らし合わせて適切に作成されているのか」
、「予算統制のプロセスが、策定した予算と実績の差を分析して差異を減らせているか」ということが、上場予定企業の重要な審査項目となります。
このため上場を志向する企業やガバナンス体制の構築を目指す企業においては、この予算編成と予算統制の考え方はきちんと身につけておくことが必須になりますので、これらの事項を丁寧に説明していきたいと思います。
■ 予算編成と予算統制
(1)予算のPDCAサイクル
予算を運用するためには、下記のPDCAサイクルに予算を組み込む必要があります。
PDCAサイクル:
P:
D:
C:
A:
(2)予算編成の2つの視点
予算編成は、PDCAサイクルのPの部分に該当します。予算編成が妥当であるかどうかといことについては、2つの視点が必要です。
① 予算編成が、適切な手順を踏んで行われているのか
② 事業計画・予算が合理的であるか
(3)予算編成を行う上での注意点
実際に予算を編成する上では、2つの視点を踏まえた上で以下の5つのポイントがとくに重要です。
① 事業計画や施策が具体的かどうか
② 予算策定において必要性の吟味と実現可能性の検証が行われているか
③ 全社の財務目標と各部門の目標に整合性があるか
④ 予算立案のための基礎情報が十分に揃っているか
⑤ 各部門の成果指標であるKPIをしっかり設定しているか
(4)予算編成にあたって生じるよくある問題点
予算編成をしてみて、往々にして生じるよくある問題として以下のようなことが考えられます。
① 高すぎる目標や現実的に実現不可能な目標を立ててしまう
② 低すぎる目標を設定してしまう
③ 会社全体の財務目標数値や施策と部門ごとの目標数値・施策に整合性がない
各部門が目標を達成しても全社的には目標未達成ということになりかねないため、予算管理機能が喪失する
ことになります。
このような問題点がみられるような予算は、予算編成のプロセスにおいて、なんらかの課題を抱えていることが多く、その結果として、できあがった予算が、役に立たないということになることが往々にしてあります。とは言うものの実際には、
予算の策定はトライアンドエラーを繰り返して、合理的な予算ができあがっていくもの
だと思いますので、上場を志向する企業は、上場準備初期段階から予算について取り組んでいくことが必要です。
(5)予算統制とは
予算統制は、PDCAサイクルのCの部分に該当します。
策定した予算を月次実績と比較し、問題点や課題を分析し、改善するための対策を検討できるようにすることをいいます。
取締役会の場で、予算実績差異分析の結果が報告され、審議されることは、取締役会での議論、結論が会社の重要な方向付けを行うことにもつながるので、予算統制は極めて重要なものになります。
(6)予算統制(業績管理)の必要性
予算統制には以下のような効果があるため重要視されます。
① 会社の状況を把握することで、経営者が適切な経営判断を行うことができるようになる。
② 会社の将来見通しを数値で説明できるため、会社の様々なステークホルダーの理解を得ることができる。
③ 予算と会社の実績を比較することになるため、実績数値の異常な変動や間違いを早期に発見することにつながる。
もっとも、会社の状況を正確に把握し、間違いなどを発見するためには、月次業績や事業状況を早期に把握し、分析できる体制が構築されていることが前提となります。
また、分析を適切に行うためには、策定された予算数値が合理的であることが前提となります。
■ 上場審査と予算編成の合理性について
上場を志向する企業にとっては、
適切な予算の策定と予算統制は極めて重要な事項
になります。有価証券上場規程第 219 条(「実質審査基準」といわれます)において、グロース市場に上場しようとする会社に必要な適格要件として「事業計画の合理性」があります。
「事業計画に合理性がある」というためには、「(1)事業計画が、そのビジネスモデル、事業環境、リスク要因等を踏まえて、適切に策定されていると認められること。」「(2)事業計画を遂行するために必要な事業基盤が整備されていると認められること又は整備される合理的な見込みがあること。」と基準が明記されています。
そのように言えるようにするためには、やはり、予算編成と編成された予算を基に行われる実績管理(予算統制)が、下記の(1)~(5)の状況であることが必要であるため、上記の予算編成と予算統制の各項目を確認しながら、いったん予算を策定されてはいかがでしょうか。
(1) 適切な手順を踏んで予算編成が行われているか
関連リンク
このカテゴリーの他の記事を見る