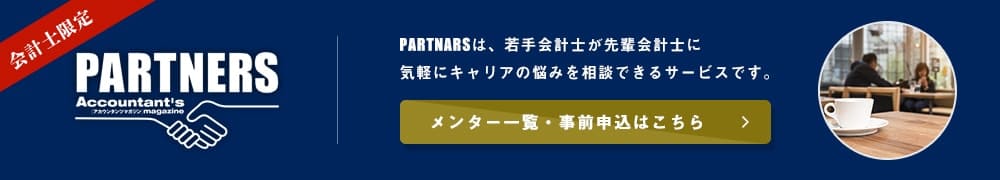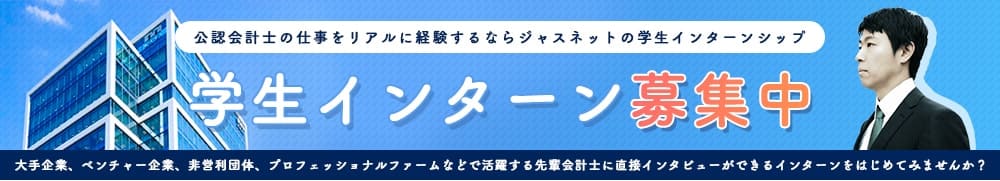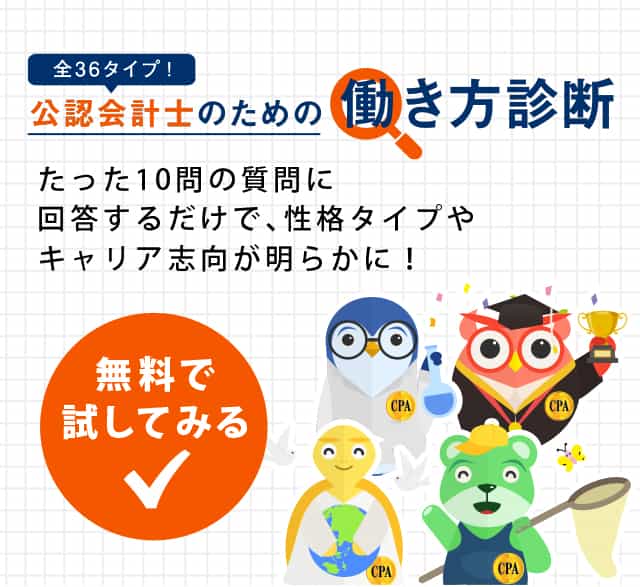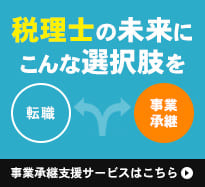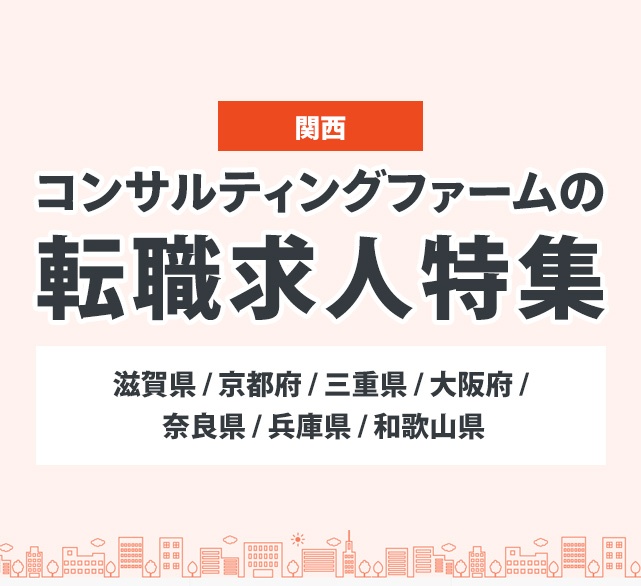【会計士が一番最初に読む IPO入門講座】
第4回 IPO準備の基本(4):上場すべきではない会社とは?審査で落ちる企業の特徴と具体事例を解説

2020年4月24日 齊藤 健太郎
目次
■上場の基準を準拠しない会社
(1)形式基準を満たせない会社
形式基準とは、各株式市場により必要とされる形式基準の内容は異なりますが、主な審査項目は以下の①~⑦の通りです。この形式基準を満たさない企業の理由の如何を問わず、上場申請の不受理となり、上場できません。
下記の形式基準のうち、 ①~⑥は、主幹事証券会社と資本政策の観点から相談しながら進め、⑤~⑦は、監査法人と相談しながら進めていく必要があります。
こうした話し合いの中で折り合いをつけられない会社は、本来であれば、適切対処策を取ることができるのにあえて取らない会社ということになります。よって、上場すべきではない会社ということになります。
形式基準は、下記における実質基準と異なり、事実の有無がはっきりしているので、白黒がつけやすく、 上場すべきではない企業の線引きが明確 になります。
①株主数
上場時の株主数の見込みです。上場時には基準となる株主数を上回るように公募・売出の数量を決めたり、証券会社が1人あたりの購入株数を調整したりします。
市場により株主数の見込が異なりますが、企業規模、市場のステージが進むほど株主数の数は多くなります。
②上場時公募・売出
上場申請日から上場日の前日までに行う公募もしくは売出のことをいいます。
新興企業向け市場では、上場時において一定数の公募・売出が義務付けられています。これにより上場後の株式の流通性が確保されます。
③流通株式
上場時を見込んで、流通株式数、流通株式時価総額、流通株式比率など一定数以上の基準をクリアする必要があります。
(ⅰ)流通株式数
株式市場において流通性が期待される株式数のことをいいます。これは、発行済み株式総数から、流動性の乏しい株式(上場株式数の10%以上を所有する株主が所有する株式、役員やその近親者等が所有する株式、自己株式等)の数を差し引いて算定します。
この流通株式数は、上場申請日のものではなく、上場日において見込まれる数で判断します。
(ⅱ)流通通株式比率
(ⅰ)の流通株式数を上場日において見込まれる申請会社の発行済株式総数で除して算定します。
(ⅲ)流通株式時価総額
(ⅰ)の流通株式数に株価を乗じて算定します。ここでの株価は、上場時における想定発行価格または想定売出価格に基づきます。
④事業継続年数
上場申請日から起算して一定期間、株式会社として取締役会を設置し、かつ、継続的に事業活動を行っていることが求められます。
⑤純資産の額
上場申請日の直前事業年度の末日における純資産額に、上場時の公募で増加が見込まれる純資産の額を加算した額です。連結財務諸表を作成している場合は、連結ベースの純資産額が基準となります。
⑥利益の額
連結財務諸表を作成している場合は連結ベースの経常損益に非支配株主損益を加減した額であり、連結財務諸表を作成していない期間や連結財務諸表を作成していない場合は単体ベースの経常損益です。なお、プライム、スタンダードなど市場によって異なる金額基準を設けています。
グロース市場には、利益の額は形式基準で求められていませんが、成長可能性という別の尺度が求められています。
⑦財務諸表の監査意見
上場申請に際して提出する新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)における財務諸表に対する監査意見は、直前々期は無限定適正意見もしくは除外事項を付した限定付適正意見、直前期は無限定適正意見が求められます(但し、天災等による例外あり)。
上場規則上、直前々期は除外事項を付した限定付適正意見でも問題ないとされていますが、実務的には無限定適正意見が必要と思われます。
(2)実質基準を満たせない会社
実質基準は、開示の体制やコーポレート・ガバナンスの状況などを確認する定性的な基準に該当します。
日本取引所グループのWEBページにおいては、上場審査の内容として以下の項目とその内容を市場ごとに明記しています(表1参照)。これらの内容を満たすことができない企業は、実質基準を満たせない企業として、上場すべきではない企業となります。
【プライム市場】
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 1 | 企業の継続性及び収益性 | 継続的に事業を営み、安定的かつ優れた収益基盤を有していること |
| 2 | 企業経営の健全性 | 事業を公正かつ忠実に遂行していること |
| 3 | 企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性 | コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が適切に整備され、機能していること |
| 4 | 企業内容等の開示の適正性 | 企業内容等の開示を適正に行うことができる状況にあること |
| 5 | その他公益又は投資者保護の観点から当取引所が必要と認める事項 | |
【スタンダード市場】
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 1 | 企業の継続性及び収益性 | 継続的に事業を営み、かつ、安定的な収益基盤を有していること |
| 2 | 企業経営の健全性 | 事業を公正かつ忠実に遂行していること |
| 3 | 企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性 | コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が適切に整備され、機能していること |
| 4 | 企業内容等の開示の適正性 | 企業内容等の開示を適正に行うことができる状況にあること |
| 5 | その他公益又は投資者保護の観点から当取引所が必要と認める事項 | |
【グロース市場】
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 1 | 企業内容、リスク情報等の開示の適切性 | 企業内容、リスク情報等の開示を適切に行うことができる状況にあること |
| 2 | 企業経営の健全性 | 事業を公正かつ忠実に遂行していること |
| 3 | 企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性 | コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が、企業の規模や成熟度等に応じて整備され、適切に機能していること |
| 4 | 事業計画の合理性 | 相応に合理的な事業計画を策定しており、当該事業計画を遂行するために必要な事業基盤を整備していること又は整備する合理的な見込みのあること |
| 5 | その他公益又は投資者保護の観点から当取引所が必要と認める事項 | |
*出展:日本取引所グループ WEBページより
①形式的に上場基準を満たすことを考える経営者の問題
実質基準は、証券取引所の引受審査で上記の基準を満たしているか審査され、取引所審査でも再び同じ観点から審査されることになります。
基本的には主幹事証券会社の指導を中心として、会社が上記の実質基準に準拠しているといえるまで指導を受けることとなります。
上記の基準を満たすべく、主幹事証券会社による指導が入っていくのですが、上記の基準をただ形式的に満たせばよいと考え、利益さえ出ればなんとかなるだろうと考える経営者は少なからずいます。
このような会社は「上場すべきではない企業」として、 引受審査段階から警戒され、何らかの理由で上場申請まで至らないことも多々ある ので注意が必要です。
②合理的な事業計画を立てられない企業の限界
特にグロース市場を目指すベンチャー企業に多いのですが、合理的な事業計画を立てられない企業というものは一定数存在しています。こうした企業は、会社の事業予測を組み立てられない企業であることから、他者から広く資金を調達する資格はなく、やはり上場すべきではない企業となります。
■反社会的勢力と関係のある会社
上場すべきではない企業として、反社会的勢力と関係のある会社は、上場することができません。
会社にとって以下のステークホルダーに対しては、常時・定期的に反社会的勢力と関係がないことを確認しなければなりません。
- ①株主
- ②役職員
- ③主要取引先等
- ④企業グループ内の他の会社
このような関係遮断が求められるのは以下のような理由があるからです。
- 暴力団等と企業が契約を締結することは、企業が犯罪行為等損害を受ける蓋然性が高いこと(暴力団の反社会性・犯罪性)
- 証券市場からの反社会的勢力排除は、暴力団の資金源に打撃を与えることができること(治安対策上の観点)
- 投資者保護や、健全で公正な証券市場の維持、コンプライアンスの確保のため(証券市場及び証券関係者の健全性維持)
上場準備企業が、上場する際には、「反社会的勢力との関係がないことを示す確認書」を提出することになります。実際に反社会的勢力との関係が継続している場合は、上場することができません。
上場したのちに反社会的勢力と関係が発覚し、取引所との間の上場契約違反を根拠に上場廃止となった企業も複数存在 しています。こうした企業は、上場すべきではない企業となります。
■上場株式会社としてきちんとした資金運用が期待できない会社
(1)保育事業の事例
明文上の規定はないものの、株式会社としての正常な運用が期待しえないために上場すべきはないと判断される企業も存在します。
例えば、保育園事業を運営している会社の場合、運営する認可保育所では、自治体から補助金をもらい指針に基づき施設を運営することで売上を立てます。このような事業体が獲得した収益を株主に分配することを自由にできるのかという点では、疑問があります。
そもそも株式会社は、獲得した収益を配当金として分配することが自由にできる企業体を指しますが、この保育事業の展開により獲得した利益を配当分配として利益分配を行うことについては、グレーゾーンになります。
このため保育事業を営む上場会社は、HD化し、保育事業を子会社運営することでこうした課題を回避しています。こうしたHD運営自体が認められるかも一つの論点となりますが、 直接許認可で収益を獲得している事業運営を行っている事業体は、株式上場することは実質的に難しくなっています。
こうした企業は、保育事業単体で上場することができず、一度ホールディングス化を経て上場することになります。
(2)関連当事者取引の解消ができない事例
①関連当事者取引の把握・解消が不十分な企業
関連当事者取引とは、会社の役員(またその近親者)、主要株主(またはその近親者)、関連会社(または関連会社の子会社)など、会社に密接に関わるステークホルダーとの間で行われる取引になります。
関連当事者取引がある場合には、会計基準上は開示を求められます。また、 上場審査の観点においては、上場前の適切なタイミングにおいて、その取引の解消が、原則的な対応として求められます。 なぜ関連当事者取引の解消が必要であるのかについては、関連当事者取引そのものの考え方に由来しています。この辺りは別に紹介しているのでここでは割愛します。
特に未上場の会社は、不動産の賃貸借契約などで関連当事者取引が行われているケースが多々あります。すべての関連当事者取引を把握し、解消するには時間がかかることもあるため、直前期末もしくは可能であれば直前々期末までに解消しておくことが必要です。
しかしながら、上場前に関連当事者取引の把握が完了しておらず、取引関係の解消が図られない場合は、上場することができません。
そもそも関連当事者把握しきれず、その取引関係も把握できないような会社は、会社の体制自体も問題視されます。さらに関連当事者取引の特殊性も認識していないため、上場すべきではない会社となります。
②解消できない関連当事者取引への対応と留意点
一方で、事業上の必要性、合理性から解消できない関連当事者取引というものが存在します。こうした場合には、主幹事証券会社やJ-Adviser と協力して取引所の理解を得ながら進めていく必要があります。
また、銀行借入に関する経営者保証に関しては、「経営者保証ガイドライン」の存在により、上場に伴い解消することができます。経営者保証ガイドラインによると、上場企業になるということが企業の財務状況の透明性の確保が担保されるため、 会社の資金借入に関する経営者保証が解消される ことになります。
上場を達成した経営者が 最も嬉しいメリットの一つ として常に取り上げられる項目ですので、この点は留意しておきましょう。
■まとめ
以上、上場すべきではない会社の事例を取り上げてみました。これらの事項に共通しているのは、「対策を行おうとすればできるのに、あえて行うことをせずにルールを潜脱して上場しようとする企業」ということとなるため、即アウトとなるような事例として取り上げてみました。
一部は第2回で説明した、上場できる会社、上場できない会社の内容と被りますが、今回の説明は、主幹事証券会社、取引所、監査法人サイドの見方によりフォーカスした事例となります。
上場を目指す会社は、上場を目指す以上は、各ステークホルダーの見方に寄り添って対応していきましょう。
関連リンク
- USCPA資格取得で開けるキャリアとは? 年収・転職先・成功事例を徹底解説
- 【会計士が一番最初に読む IPO入門講座】
- USCPA(米国公認会計士)の年収は?監査法人、税理士法人から事業会社まで
- USCPA(米国公認会計士)が活躍できる転職先と、そのメリット、デメリットは?
- 【第3回】監査や経理の担当者が知っておくべき!『モダンExcel』(全10回)
- 【第2回】監査や経理担当者が知っておくべき!『モダンExcel』データ分析超入門(全10回)
- 【第1回】監査や経理担当者が知っておくべき!『モダンExcel』データ分析超入門(全10回)
- 初めての株式鑑定評価~公認会計士として、意識しなければならない点とは?【第2回】
- 初めての株式鑑定評価~公認会計士として、意識しなければならない点とは?【第1回】
- 【会計士が一番最初に読む IPO入門講座】
- 執筆者プロフィール
-
齊藤 健太郎(さいとう けんたろう)
ジャスネットコミュニケーションズ株式会社 エグゼクティブエージェント
公認会計士・税理士/齊藤公認会計士事務所横浜国立大学経済学部卒業
横浜国立大学国際経済法学研究科修了:専攻は会社法
- 2003/2-2006/9
- エイチエス証券株式会社引受審査部所属
- 2006/9-2010/7
- あずさ監査法人第5事業部(IPO専門部署)所属
- 2010/8-2012/10
- あずさ監査法人 IT監査部所属
- 2012/10-2017/11
- LINE株式会社 内部監査室 マネージャー
- 2017/11-2020/9
- ライフアンドデザイングループ 取締役CFO
- 2020/10-2023/1
- 日本M&Aセンター TPM事業部 上場審査部 JQS