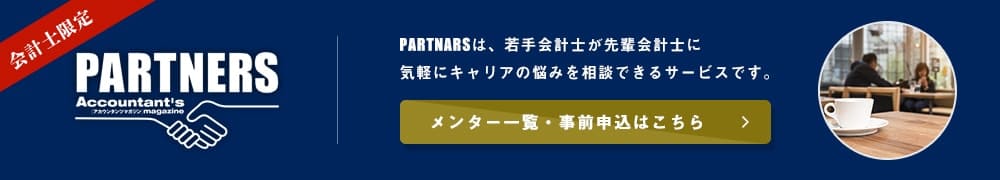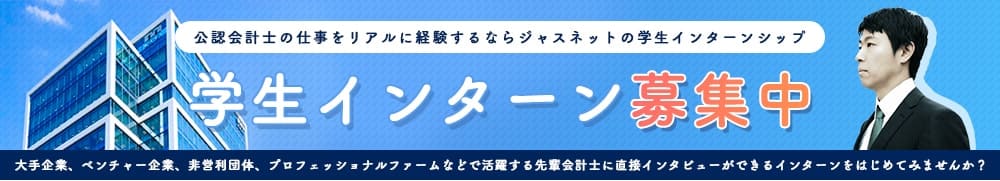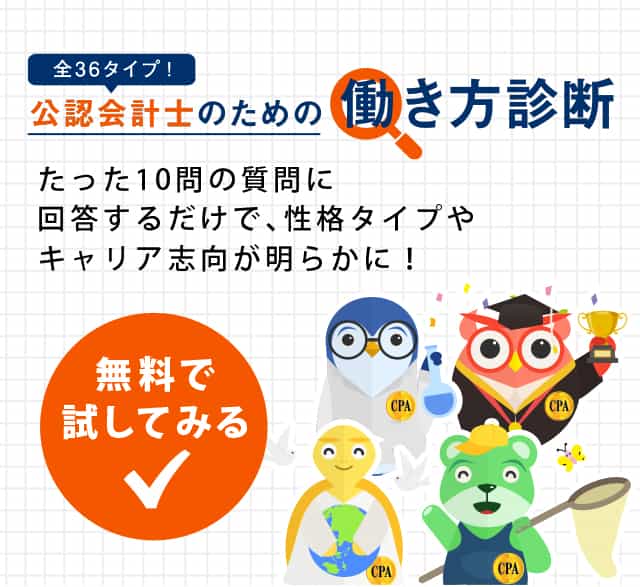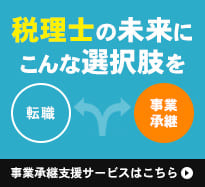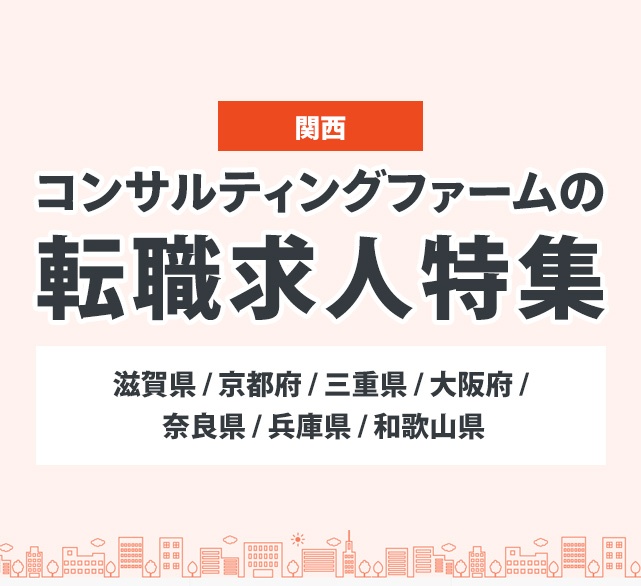■ IPO準備において求められる体制
IPOを実現するには、外部プレーヤーの存在が不可欠です。経営者が最初にIPO準備をはじめるには、
監査法人と主幹事証券会社(またはJ-Adviser)などを選定する必要
があります。
(1)監査法人の選定
<監査法人の必要性>
会社が上場するためには、基本的に上場する前の2期間の監査証明を得なければなりません。「基本的に」といったのは、TOKYO PRO Market市場に上場する場合は、上場する前の1期間の監査証明によって上場することができるからです。
最初に監査法人の監査を選定すると
監査法人から短期調査(ショートレビュー)報告書を通して、会社が財務諸表監査を受けるにあたって必要な課題点の一通り、財務面を中心にアドバイスを受けることができます
。
監査法人にはいわゆる4大監査法人から、準大手、中小監査事務所まで様々です。このショートレビューを受けるにあたっては、登録上場会社等監査人(日本公認会計士協会の品質管理レビューを受けた者に限る。)から受ける必要があります。
<登録上場会社等監査人とは何か>
なお、登録上場会社等監査人は、公認会計士協会の品質管理レビューを受けます。わたしもある監査法人の品質管理パートナーを行っているため、機を見て登録上場会社等監査人とは何ぞやということを詳述したいと思います。こちらは、今回は割愛します。
<監査の費用感>
ショートレビューでおよそ100万円~200万円、上場の2期前で(会社の規模により様々ですが)最低でも1,000万円程度の監査報酬が必要
となります。
この辺りの費用感については、最初の段階では、大手から中小監査事務所で大差はないかと思います。こうした費用負担が困難な会社は、そもそも上場することが適していません。
<日本公認会計士協会の案内>
日本公認会計士協会では、上場準備のために「
会計監査を受ける前に準備しておきたいポイント
」を公表しております。よくまとめられているので必読の内容かと思います。
もし実際に読んでみてよくわからないということでしたら、経営者ご自身でその内容を理解できるように専門家をそばに置いてレクチャーを受ける、実務に落とし込めるだけの人材を採用するなどの措置を採る必要があると思います。
株式新規上場(IPO)のための事前準備ガイドブック「会計監査を受ける前に準備しておきたいポイント」公表のご案内 | 日本公認会計士協会
(2)主幹事証券等の選定
会社が上場するためには、主幹事証券会社の選定をしなければなりません。またTOKYO PRO Market上場を目指す場合は、
J-Adviserの選定が必要
となります。
こうした主幹事証券会社やJ-adviserは、監査法人などと同様に証券取引所に上場するために必須の支援機関です。IPO準備から上場まで、企業に寄り添い伴走するパートナーとなります。
① 主幹事証券会社
<主幹事証券会社とは何者か>
主幹事証券会社は、
上場準備段階では資本政策や社内体制整備のアドバイス
を行います。
また、上場に当たっては、取引所審査への手続のサポートや資金調達のための株式の公募・売出し等を引き受けるための引受審査などを行います。また、上場のための公募・売出し等を引き受ける際には、一連の事務手続きを日程に従って実行していく役割を担うなど幅広い役割を担うことになります。
<主幹事証券会社となる証券会社とは>
日本国内における証券会社の数は、270社程度といわれていますが、アンダーライティング業務、いわゆる主幹事証券業務を行いうる証券会社は、
国内で20社程度
しかありません。
アンダーライティング業務は、企業が新たに株式や債券を発行する場合に
証券会社がそれら有価証券を買い取る業務のこと
です。売れ残った有価証券は、証券会社が買い取ることが必要です。
証券会社がいったん買い取った有価証券を消化できない可能性があることから、こうしたアンダーライティング業務を行うことができる証券会社の数はおのずと限定されることになります。特にいわゆる大型IPOと言われる案件を引受ける場合は、該当する会社の有価証券をいったん買い取れる証券会社の数はさらに限定されます。
<主幹事証券会社の選別>
経営者は大手証券会社にIPOを受けてもらいたがる傾向にあります。結局は引受けられる有価証券の規模、すなわち調達する資金規模に応じて大手証券会社か、中小証券会社かに選別することが本筋ですので、この点は頭の片隅に置いておくとよいかもしれません。
<東京証券取引所の案内>
東京証券取引所では、主幹事証券会社の役割の解説、主幹事証券業務を行っている証券会社を公開していますので、こちらの内容も必読かと思われます。
上場関係者と役割 | 新規上場基本情報 | 日本取引所グループ
② J-adviser
<J-Adviserとは何者か>
J-adviserとは、TOKYO PRO Market市場への上場に向けて、東京証券取引所や主幹事証券会社に代わって上場準備のサポートや上場審査、上場後のモニタリングといった業務を一貫して行う企業にとってのパートナーに当たります。
証券会社だけではなく、コンサルティング会社やM&A仲介事業者などがJ-Adviser 資格を有しております。
東京証券取引所の説明によると、このJ-Adviser 制度は2008年の金融商品取引法改正によって可能となった制度であり、東京証券取引所は一定の資格要件を満たし、資格を認証したJ-Adviserに対して特定業務(上場又は上場廃止に関する基準又は上場適格性要件に適合するかどうかの調査など)を委託することになります。
<J-Adviserの資格要件>
J-Adviserの一定の資格要件として、下記のことが求められます。
コーポレート・ファイナンス助言業務に関する十分な経験があること
J-QSが3名以上いること
経営の体制が適切であること
財務の状況が健全であって、かつ、当該財務の状況がウェブサイトに公表されていること
つまり東京証券取引所が、「企業に対する経営支援の経験が豊富で、IPO(株式上場)に関わる深い知見を有している」と認めた企業(証券会社、コンサルティング会社、M&A仲介事業者など)にJ-Adviser資格を付与し、上場の審査・モニタリング業務を委託しています。
このため、J-Adviserは、担当する上場会社に対して、上場前の上場適格性の調査確認や上場後の適時開示の助言・指導、上場維持要件の適合状況の調査を実施することになります。
<JQSとは何者か>
なお資格要件にあがっているJ-QSとはJ-Adviserとしての業務を行うために十分な経験と高い知見を有する者とされており、東京証券取引所の審査部の面談を受けて判断されることになります。
わたしも面談を受けましたが、たまたま面接官が、LINE社の取引所審査の担当と同じ人でしたので、談笑になってしまいました。
<東京証券取引所の案内>
なお、東京証券取引所に制度概要とJ-Adviser 一覧の解説をしています。
J-Adviser制度 | 概要(TOKYO PRO Market) | 日本取引所グループ
(3)株式事務代行機関の選定
<株式事務代行機関とは何者か>
監査法人、主幹事証券(J-Adviser)のほかに、株式事務代行機関の選定が必要です。
この株式事務代行機関は、
株式関係事務の円滑化のため設置を求められている機関
です。株主名簿作成事務等の受託、議決権・配当等株主に付与される各種の権利の処理を行ってくれます。
株式事務代行機関は、規模・組織等において、投資者の信頼、利便を得られることが必要です。なお、東京証券取引所が承認している株式事務代行機関は以下の各社です。
株式事務代行機関一覧(有価証券上場規程施行規則第212条第7項)
こうした(1)~(3)は、会社の外部者の存在になりますが、これらの外部機関のカウンターパートとなる存在を会社内部で儲けることが必要になります。
(4)上場準備責任者の選定
上場を目指す企業にとって、経営管理体制の整備は最優先課題です。上場後には株主や投資家からの厳格な監視や説明責任が求められるため、組織全体の意思決定プロセスやリスク管理体制を強化する必要があります。
しかしながら、少し待ってください。
<社内体制の点検>
今上場を目指す企業において、すでに経営管理体制の整備がされているでしょうか。今ある状況として以下の点を確認してください。
組織全体の意思決定プロセスとして、取締役会や監査役会が置かれているか。
経営陣にガバナンス意識があるのか。
社内規程が整理され、運用されているのか。
決算の早期化が実現されているのか。
監査法人監査を受けられるのか。
主幹事証券会社の指導を受け止められるのか。
こうした点に対して誰が対応するのでしょうか。外部のコンサル会社に依頼しても常時会社の実務を担ってくれるわけではありません。また経営者自身も事業を拡大していくためにこうしたことを一人で行っていくことができません。
<上場準備責任者とは何者か>
最短でのIPOを目指す場合、できるだけ早い段階で社長以外からIPO準備のリーダーを決めて、主幹事証券会社や監査法人とのメインの窓口となる旗振り役、すなわち上場準備責任者を設けることが必要になります。
第2回で「上場できない会社」の事例を紹介したと思いますが、こうした上場準備責任者が定まらず、上場をとりやめてしまうという事例も存在します。
上場指導する立場で、上場準備責任者の選任を依頼したとしてもいつまでも定まらず、社長自らが対応するという事例があります。そのような会社は上場までに至りません。
この上場準備責任者は、いわゆるCFOもしくは管理部長、経理財務部長、経営企画部長との兼務で大丈夫ですが、
そもそもそうした人材がいない場合は採用を踏み切らなければ前に進まないため、「上場準備責任者」のポジションは極めて重要な役割を担う
ことになります。
IPOの求人を探す
■まとめ
以上が、IPO準備を開始した企業に求められる体制になります。
特に「登録上場会社等監査人」「主幹事証券会社」「J-Adviser 」「上場準備責任者」は、会社が上場を進めるにあたって必要不可欠なキーワードとして必ず理解しておく必要があります。
最近ではIPOの“監査難民”という言葉が生まれるほど、監査法人や主幹事証券会社との契約ができずにスタートからつまずく企業も少なくありません。
監査難民にならないためには、監査法人や主幹事証券会社の選定を迅速に進めることはもちろんのこと、上場準備責任者を定め、その上で経理や総務を揃え、構築すべき管理体制の準備を進めていくことがポイントとなります。
次回は、上記のような体制を設けたとしてもIPOすべきではない会社について事例をもって解説していきたいと思います。
IPO支援の依頼をする
関連リンク
このカテゴリーの他の記事を見る