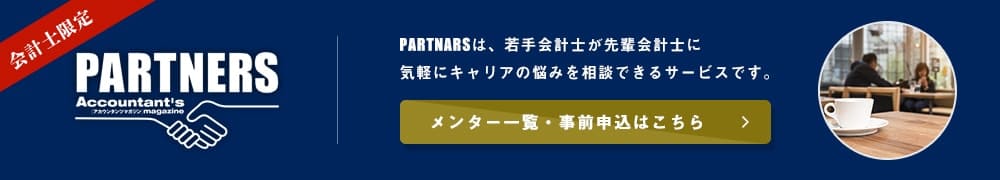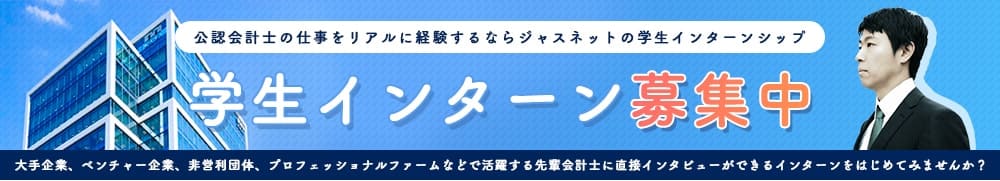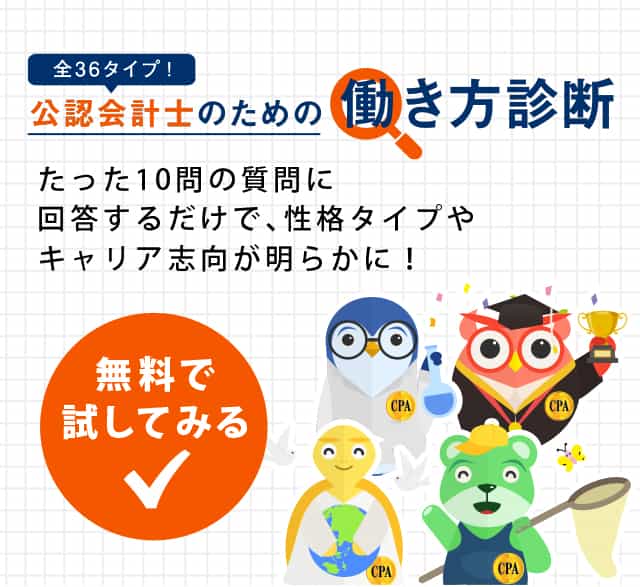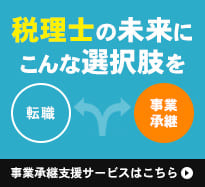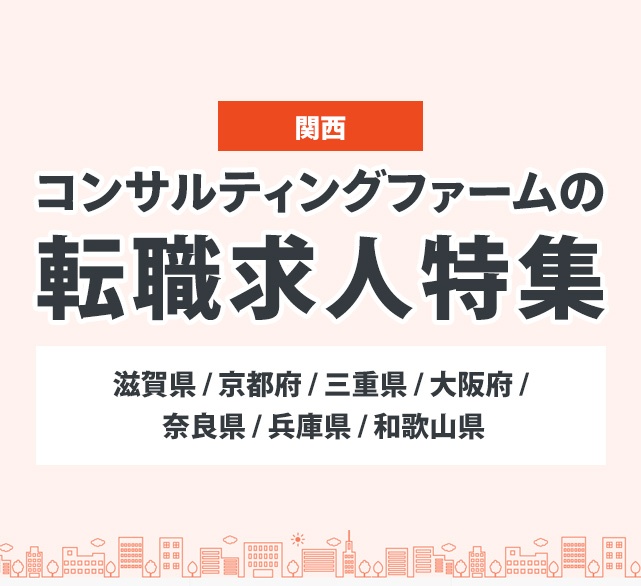公認会計士が語る TOKYO PRO Market(東京プロマーケット)とは?

2023年1月31日 新開 智之
目次
第1回 東京プロマーケットって、どうやってできたの?
■東京プロマーケットとは?
東京プロマーケット(TOKYO PRO Market)とは東京証券取引所(東証)の運営する株式市場の一つで、 プロ投資家(特定投資家)のみが取引を行うことができ、一般株式市場とは上場基準なども大きく異なる ものだ。
東証が運営する一般株式市場は2022年4月に市場区分が再編され、「プライム市場」「スタンダード市場」「グロース市場」の3つとなった。
この市場区分の再編に伴い、各株式市場への上場基準や上場維持基準は再編前と比べて厳格化され、これまでの上場基準を満たせない企業も出てきている。
また上場すれば、企業は株式市場を通じて投資家から幅広く資金調達できるようになるが、上場基準を満たすためには、膨大な準備期間と費用が必要である。さらに上場後は最低でも四半期に1回は決算の開示や監査法人による内部統制監査が必要になり、継続的な企業側の労務負担やコスト負担が必要となってくる。
しかし地方企業などの中には、上場によって知名度を上げて人材を確保したいなど、 上場の目的が資金調達ではない場合がある 。そうした企業が、必要以上に時間とお金をかけて一般市場に上場するのは、得策とはいえない。
東京プロマーケットは、 多様な企業ニーズの受け皿 となるために誕生した。上場や上場維持に株主数や株式の流通量などの数値基準が設けられておらず、一般株式市場と比較して上場のハードルが低くなっている。そのため上場を検討している一部の企業から関心を集めている市場なのだ。
具体的には 「一般株式市場上場のためのスタート台としてのマーケット」、「オーナーシップの維持と知名度・信用力向上の双方を手にしながら成長するためのマーケット」としての役割を期待されている のである。
また上場のハードルが低い反面、投資家の企業の将来性を見る力が一般市場以上に求められるため、市場へ参画できる者を金融商品(株式)に対する十分な知識、経験、資産および十分な危機管理能力があると認められる プロ投資家(特定投資家)に限定している ことも特徴である。
■東京プロマーケット市場にはモデル市場があった
東京プロマーケット市場のことを説明するにあたり、そもそもこの市場がどうやってできたのかについて説明しよう。
東京証券取引所は、2001年11月に株式会社化され、2007年8月東京証券取引所グループを設立して、新しい株式市場への模索が始まった。2009年6月1日には、ロンドン証券取引所との共同出資で、株式会社TOKYO AIM取引所を設立し、プロ投資家向けの株式市場「 TOKYO AIM 」を開設する。
この「TOKYO AIM」こそが「東京プロマーケット市場」の前身であり、「東京プロマーケット市場」を説明するためには、まず「TOKYO AIM」のことから説明しなければならない。
■「TOKYO AIM」とは?
「TOKYO AIM」は当時、東京証券取引所の社長であった斉藤惇氏がロンドン証券取引所と合弁で設立した市場だ。ロンドン証券取引所では、金融ビッグバンを成し遂げたところでもあり、「ロンドンAIM」という市場が1995年に新たに創設され、活況を呈するに至った。
| 西暦 | 英国内上場 | 英国外上場 | London AIM合計 |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 1,179社 | 220社 | 1,399社 |
| 2006年 | 1,330社 | 304社 | 1,634社 |
| 2007年 | 1,347社 | 347社 | 1,694社 |
| 2008年 | 1,233社 | 317社 | 1,550社 |
| 2009年 | 1,052社 | 241社 | 1,293社 |
| 2010年 | 967社 | 228社 | 1,195社 |
| 2011年 | 918社 | 225社 | 1,143社 |
| 2012年 | 870社 | 226社 | 1,096社 |
| 2013年 | 861社 | 226社 | 1,087社 |
| 2014年 | 885社 | 219社 | 1,104社 |
| 2015年 | 845社 | 199社 | 1,044社 |
| 2016年 | 809社 | 173社 | 982社 |
| 2017年 | 808社 | 152社 | 960社 |
| 2018年 | 781社 | 142社 | 923社 |
| 2019年 | 740社 | 123社 | 863社 |
| 2020年 | 707社 | 112社 | 819社 |
| 2021年 | 705社 | 111社 | 816社 |
ロンドン証券取引所の一市場である「ロンドンAIM」のAIMとは、Alternative Investment Marketの略称であり、 「世界で最も成功した新興市場」 と言われている。
「ロンドンAIM」は1995年に設立され、その後世界のあちらこちらの証券取引所で似たような成長企業向けの市場が創造られたが、 1000社近い上場企業が存在するのはロンドンAIMだけ である。
1995年の誕生以来、2021年現在の上場企業数は約816社で、2007年のピーク1694社からはかなり減っている。年間に約150社がAIMから本則市場に移行し、逆に300社が本則市場からAIMに「格下げ」されている。
図表は左端が西暦、順にイギリス国内からの上場企業数、海外からの上場企業数、右端がロンドンAIM上場企業数合計である。
■東京プロマーケット市場の成立
2009年6月に開設された「TOKYO AIM」は当時のリーマンショックのあおりをうけたこともあり、3年間新規上場がわずか2社であり、低迷を極めた。
そうこうしているうちにロンドン証券取引所は合弁から手を引き、東京証券取引所は単独で「TOKYO AIM」を引き受けることになり、2012年7月に株式会社TOKYO AIMを東京証券取引所に合併し、発展的に「東京プロマーケット市場」として名称変更し、市場そのものは継続し運営されている。
■東京プロマーケット市場の展望
2022年11月末現在では、 累計90社程度が上場し、市場では62社の上場企業数 になるまでに成長している。
今後は2022年同様、毎年20社以上が上場し、ロンドンAIMのように1,000社を超える中小中堅企業が全国から上場し、日本のスタートアップ企業の成長や老舗企業の事業承継を促進してくれると確信している。
300万を超える全国の中小中堅事業者が、東京プロマーケット市場の有用性に気付き、 「経営の高度化」や「信用力の向上」や「採用力の強化」 などを目指して、千社万社が東京プロマーケット市場に上場し、日本の証券取引市場や地方経済、もって日本経済を支えてくれることを願ってやまない。
第2回 東京プロマーケット(TPM)の上場基準は?
■形式基準、実質基準とは?
上場基準について説明する場合、 「形式基準」 と 「実質基準」 のことを説明しなければなりません。
「形式基準」とは、 株主数や流通株式割合や流通株式の時価総額などの数値の基準 のことをいいます。
「実質基準」とは、公開申請会社が、業種・業態・規模等に応じて機能していれば当然に足りるものであり、 画一的に要求される基準ではない基準の ことです(表1)。株式公開審査は、各市場により審査の進め方等に差はあるものの、審査の基本的な考え方に大きな差はないといえます。
なお、証券取引所への上場申請の場合における主な審査項目の概要は以下のとおりです。
| 表1 東京・名古屋・札幌・福岡の各証券取引所 |
|---|
| 企業の継続性及び収益性 ※1 |
| 企業経営の健全性 |
| 企業のコーポレートガバナンス及び内部管理体制の有効性 |
| 企業内容等の開示の適正性 |
| その他、公益または投資家保護の観点から証券取引所が必要と認める事項 ※2 |
※1 東証グロース市場では『高い成長性』、名証ネクスト市場では『着実な成長性』が求められます。
※2 TOKYO PRO Marketでは、指定アドバイザー(J-adviser)による審査が求められます。
上記のほか、公開会社の適格性の問題として以下のような実質的な審査が行われます。
①公開申請会社の事業内容等が社会的に批判を受けるもの、又はその恐れがあるものではないか。
②公開申請会社、役員に係る法令違反等の発生事実がないか。
③特定の者が不適切な利益を得ることを防止する等の観点から、公開申請会社の株式公開制度の利用目的に問題はないか。
■東京プロマーケットの上場基準は?
東京プロマーケットでは、株主数などの数値基準はありません。求められている形式基準としては、 上場直前期における1期分の監査証明 です。
通常の上場市場が、2期分の監査証明を求めている点からも短期間に上場できるというメリットがあります。
東京プロマーケットにおける実質基準は、先に述べた通りで、通常の市場と変わるところはありませんが、特に 「精度ある予算統制」「中期経営計画の適切性」「月次決算の早期化」「開示の適正性」「コンプライアンス遵守」 は、最低限もとめられるものといえます。
| 表2 TPM市場と通常市場の特徴について比較一覧 | ||
|---|---|---|
| TOKYO PRO Market | 通常の上場市場 | |
| 継続開示業務 | 「発行者情報」を東証に提出 | 「有価証券報告書」を財務局へ提出 |
| 監査法人の監査 | 必要(年2回、決算監査と中間監査) | 必要(年4回、但し3回は四半期レビュー)【2022年12月現在】 |
| 会計監査人設置 | 大会社(※)でなければ不要 | 義務あり |
| 監査役会設置 | 大会社(※)でなければ不要 | 義務あり |
| 四半期開示 | 義務なし | 義務あり |
| 内部統制監査(J-sox) | 義務なし | 義務あり |
| 決算短信 | 義務あり(60日以内)‐実質45日‐ | 義務あり(45日以内)‐実質30日‐ |
| 適時開示 | 東証の他市場と同じ基準 | 各市場の基準 |
(※)大会社とは、資本金の額が5億円以上または負債総額が200億円以上の会社をいいます。
第3回 東京プロマーケットの特徴 上場のメリット・デメリット
第4回 東京プロマーケットの上場にかかる費用
(文責 監査法人コスモス 統括代表社員 公認会計士 新開智之)
関連リンク
- 公認会計士試験の合格発表後、最初のつまずきは就職活動?4大・準大手の募集要項を徹底比較!
- AIは公認会計士監査をどう変える?その可能性と課題を徹底解説
- 監査法人から一般企業の経理に転職!年収アップの方法と新たなキャリアの作り方
- 【2026年版】公認会計士の就活完全ガイド!|超短期決戦を勝ち抜く戦略と内定獲得の秘訣
- 【2026年最新】公認会計士に合格しても就職できない?監査法人に落ちたその後の現実と対処法
- 【完全版】公認会計士試験合格後にやるべきこととは?試験終了からキャリア設計まで
- CFOになるには? 必要なスキル・資格・キャリアパスを徹底解説!
- 監査法人とは何かを徹底解説!仕事内容・年収・転職・求人情報まで
- 公認会計士が非常勤の仕事をずっと続けるためのコツ
- 公認会計士の就職・転職|17種類のキャリアパスを徹底解説!
- 執筆者プロフィール
-
新開 智之(しんかい ともゆき)
公認会計士、監査法人コスモス統括代表社員平成4年3月岐阜大学教育学部卒業、平成10年3月公認会計士試験第3次試験合格後、社員、代表社員を経て、令和元年6月監査法人コスモス統括代表社員就任。会計監査・IPO支援のほか、財務・会計・税務を中心とした業務に就いて、マネジメント・コンサルティング、企業再編コンサルティング、環境ISOの構築支援及び審査を経験してきた。現在では、中小・中堅企業の株式上場・IPO支援を積極的に実施しており、最近5年間で11社を東京プロマーケット市場へ上場支援し、特に東京プロマーケット市場から一般市場へのステップアップ上場への支援にも積極的に活動中。