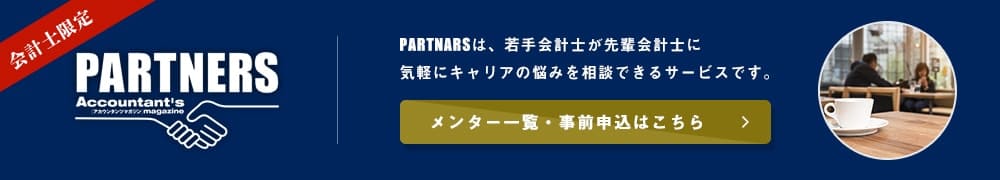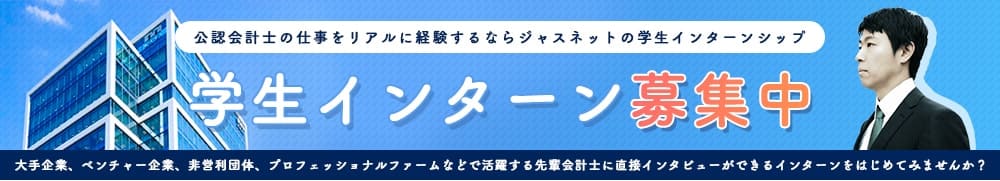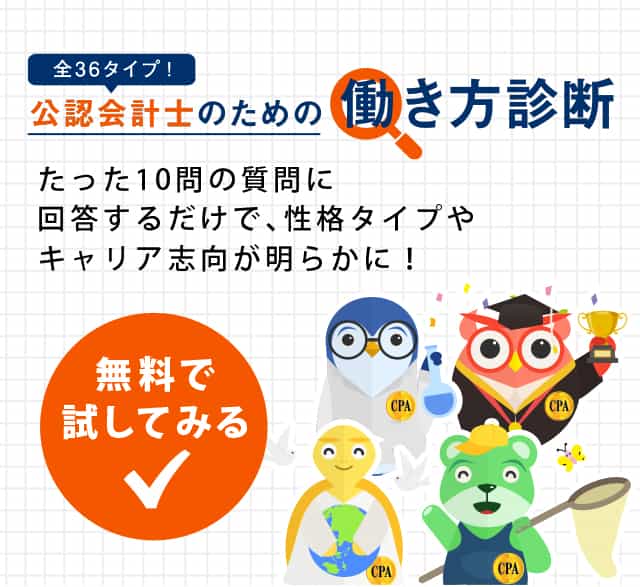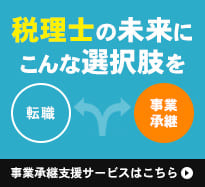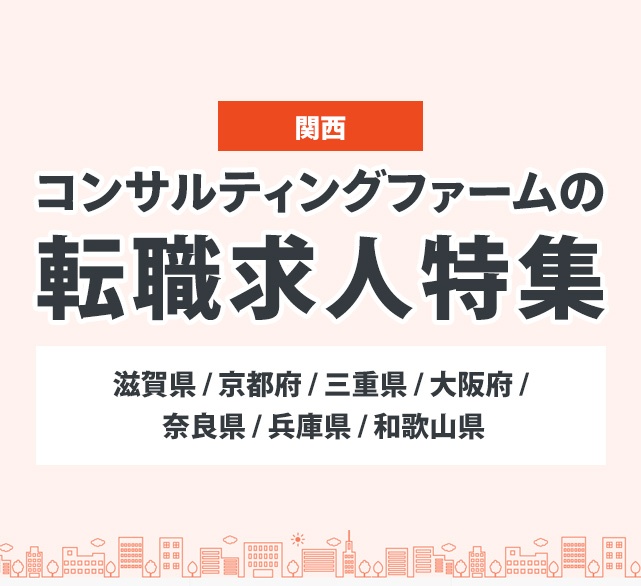公認会計士のための「実務家教員」の業務内容、仕事の魅力は?

2023年7月6日 三宅 博人
目次
■実務家教員に必要とされる志向性(どんな人に向いているか?)
会計監査やコンサルティング等、会計プロフェッショナルとしての専門知識や経験は前提として、 クライアントリレーションシップや監査チームの体制作り、スタッフの悩み相談などが得意なタイプの方が向いている と思います。要は人と話すのが好きということ。
学生は押しなべて、実例に基づいた生々しい話は大好きです。この点は、むしろプロパーな研究者よりも実務家の会計士の方にアドバンテージがあると考えてもよいでしょう。
わたしが申し上げるのも口幅ったいのですが、いろいろな人生経験をして、閑話休題、話題に深みのある人間の方が、学生受けは良いと思います。授業に笑いは大事ですね。
また弁護士と比較して公認会計士の場合、特に監査の現場では文章力が求められることはほぼ皆無ですが、学者の世界では、おのずから書く機会は増えるため、得意に越したことはないと思います。
■就職先として、どのような選択肢があるか
実務家教員は、ある意味で、その大学・大学院の顔になる訳ですから、選択肢というよりも、先方からお声がけいただくことが多いと思います。
会計監査としての実績なら、監査法人の重鎮クラスでないと声もかからないし、事務所側も快く兼任を認めることは難しいでしょう。
コンサルティング業務を売りにするなら、その分野で実務家としてきちんとした本を書いている、専門家として高く評価されているなどの評価が必要でしょう。スペシャリストである必要があります。
これまでの仕事の結果として、採用側からぜひこの人に教鞭をとって欲しいと声がかかりますので、これは 「実務家としての評価」を自分自身の努力であげていくしかない でしょう。
こちらから積極的にアピールするのであれば、専門サイトの閲覧をはじめ、意識的にアンテナを立てて教員募集の情報を入手し、各大学や大学院にアプライする場合が多いのではないでしょうか。
その場合は、自身も大学院の修士、あるいは博士課程を修了し、学生に論文指導できる立場であれば選択の幅は広がると思います。
若手の公認会計士で、特に教育方面にも興味があり、監査人としてではなく、会計分野の研究者としての道を選びたいという明確な意思を持っている場合は、 まずは大学院を卒業し、助手として地道に研究者の人生をスタートする位の覚悟が求められます 。急がば回れ、長い目で見ればその方が大成する道は近いでしょう。
また、選択肢という意味では、公認会計士受験予備校などで合格指導をする側に回るというのもひとつかもしれません。
■実務家教員の業務内容
あくまでわたしが担当していた会計専門職大学院での事例になります。
<担当科目>
(1)コーポレートガバナンス
わたしは公認会計士の二次試験合格以降、オリックスの宮内義彦氏らに師事し、日本コーポレート・ガバナンス・フォーラムの運営委員として、ガバナンス研究をライフワークとして取り組んできました。加えてその後のコーポレート・ガバナンスに関するアドバイザリーサービスの経験を織り込みました。
(2)監査事例研究
主に国内外の監査の失敗事例を公表データ(公認会計士監査審査会、第三者委員会報告書等)から読み解き、自身の経験を踏まえ、メリハリをつけて説明することを心掛けました。また、日本公認不正検査士協会評議員として得た知見も活用しました。
(3)GRC(ガバナンス・リスク・コンプライアンス)
わたしはガバナンスと同時に、CSR(企業の社会的責任)についての研究を経済人コー円卓会議日本委員会エグゼクティブ・アドバイザーや監事として取り組んできました。
また、監査法人時代、及び独立後のトヨタ自動車等への内部監査に関するアドバイザリーサービスの経験やリスクマネジメントに関するコンサルティング等が、授業にも生きることになりました。
*専任教員なのか、客員・非常勤教員なのかにもよると思いますが、ゼミの受け持ちや論文の指導・評価などの業務も発生する可能性があります。
■実務家教員の仕事のやりがいは?
わたしは 学生との人間的な触れ合い にやりがいを覚えました。
授業で思った通り冗談が受けて爆笑を取った瞬間、プライベートでの飲み会、人生・就職相談など。自身の失敗経験も踏まえ、それなりにバリューを発揮できたこともあったのではないでしょうか。もともと日本公認会計士協会会計士補会代表幹事・最高顧問をしていたのですが、若い人たちとワイワイやるのが好きなタイプなのだと思います。
■実務家教員の採用ニーズ
(1)求められるスキル、人材
どの科目を教えるかにもよりますが、
監査の場合:
すでに公認会計士は、基本的な監査論は勉強しており、主査(現場責任者)もしくはマネージャーレベルでも、最先端の実務経験を有するためスキルという意味では十分かもしれません。上述のとおり、そのような人材に声がかかるかというと、また別の問題です。
コンサルティングの場合:
特殊分野であればあるほど貴重な経験値を有するため、頭角を現せば声がかかる可能性はあります。一方で、そのようなテーマが科目として成立するのか否かは、別の問題となります。
(2)採用されるポイント
基幹科目(簿記、監査論、会計学等)を複数担当してもらう場合と、その他の科目(経営学等)をお願いする場合で、求められるタレントも変わってくると思います。
前者であれば手堅いオーソドックスなタイプ、後者であればユニークで面白いタイプ でしょう。
もちろん、採用側の大学・大学院の考え次第であり、強力な人間関係の絆などの太いパイプがあれば有利となります。わたしの場合は、監査論や職業倫理、コーポレート・ガバナンスの権威、八田進二先生とのご縁が大きかったと思います。
(3)転職で気を付けるポイントや難易度
本気でアカデミズムの世界へ転身し、プロフェッサーを目指すのであれば、少なくともマスター(修士課程)、できればドクター(博士課程)を修了すべきです。というよりも現在は、マスターを出ていなければ客員教授や非常勤講師になる道はかなり狭き門になるのではないでしょうか。
■実務家教員の仕事の年収はどのくらい?
客員教授や非常勤講師の場合、恐らく 半期1コマを持つ場合、1回(90分)数万円×15回 が基本ではないでしょうか。これに科目数を乗じた金額が総収入となります。
そもそもが、監査法人に勤務していたり、自身の事務所を経営していたりすることが前提の報酬体系ですので、複数の大学・大学院などで相当数の掛け持ちをしない限り、これだけで生活していくのは厳しいでしょう。
実務家教員でも特任教授、専任教員となれば、数百万円は保証されるでしょう。
■実務家教員の経験を活かしたその後のキャリアパスは?
繰り返しになってしまいますが、アカデミズムの世界でステップアップを図るのなら、修士、博士課程を修了し、関連する学会に入会し、いわゆる雑巾がけからはじめ、継続的に研究活動を続けることによって、 学者として一角の人物になることを目指すべき だと思います。自身の専門分野について愚直かつ誠実に人生をかけてコツコツと取り組む粘り強さが必要でしょう。要は、研究者を目指すなら一度自分は公認会計士であることを忘れて退路を断って臨むということです。
わたしも現在は学会には所属(日本監査研究学会、日本ガバナンス研究学会)していますが、特段直接の学会における活動は行っていません。しかしながら、実務家教員や学会における研究活動を通して得られた知見は公益財団法人日本内部監査研究所における研究活動を実施する上でも大変役に立っていますし、人材紹介等に係る様々なコンテンツの配信を行う上でも昔の教え子や仲間からの情報は財産となっており、むしろ教えを乞う場合すらあります。
数年ではありましたが得難い経験をしました。また、いつか機会があればチャレンジしてみたいと思っています。
皆様の研究者としてのご成功を祈念しています。
関連リンク
- 公認会計士による上場企業CFO&CSOの業務内容、仕事の魅力は?
- 公認会計士によるCAOの業務内容、仕事の魅力は?
- 公認会計士による「証券会社における引受審査業務」という仕事の魅力、その業務内容とは?
- 公認会計士のための「国会議員政策担当秘書」仕事の魅力、業務内容は?
- 公認会計士が監査法人で『非常勤』として働く!そのメリットは?
- 「大手企業での内部監査部門」の業務内容、仕事の魅力は?
- 「社外CFO」の業務内容、仕事の魅力は?
- 独立系財務・会計コンサルティングファームの業務内容~事業再生業務編~
- 「ベンチャー企業CFO」の業務内容と仕事のやりがいは?
- 「資産税コンサル」の業務内容、仕事の魅力は?
- 執筆者プロフィール
-
三宅 博人(みやけ ひろと)
【現職】
公認会計士
公益財団法人日本内部監査研究所 研究員
経済人コー円卓会議日本委員会 監事
日本コーポレートガバナンス・ネットワーク 企画委員
【専門分野】
会計監査、コーポレート・ガバナンス、内部監査、リスクマネジメント、CSR(企業の社会的責任)、サステナビリティ 等【経歴】(関連諸団体のみ)
青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 客員教授
日本公認会計士協会 会計士補会・代表幹事/最高顧問、国際委員会・委員(国際監査基準担当)、東京会・広報担当幹事
日本公認不正検査士協会 評議員
日本内部統制研究学会(現・日本ガバナンス研究学会)監事
日本コーポレート・ガバナンス・フォーラム運営委員
等【著書】(共著)
『業種別アカウンティングシリーズ』(全10冊 中央経済社)
『内部監査ハンドブック』(東洋経済新報社)
『コーポレート・ガバナンスと経営監査』(東洋経済新報社)
『会計プロフェッションの職業倫理』(同文館出版)
『会計倫理の基礎と実践』(同文館出版)
『監査人の職業的懐疑心』(同文館出版)
『初級者のための経理実務Q&A』(税務務経理協会)
他その他、執筆・講演等多数