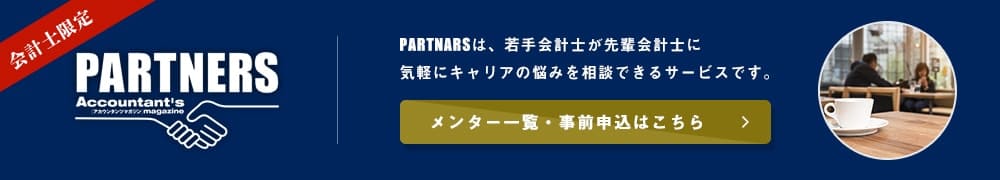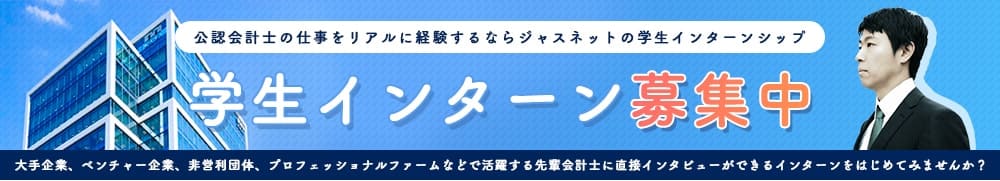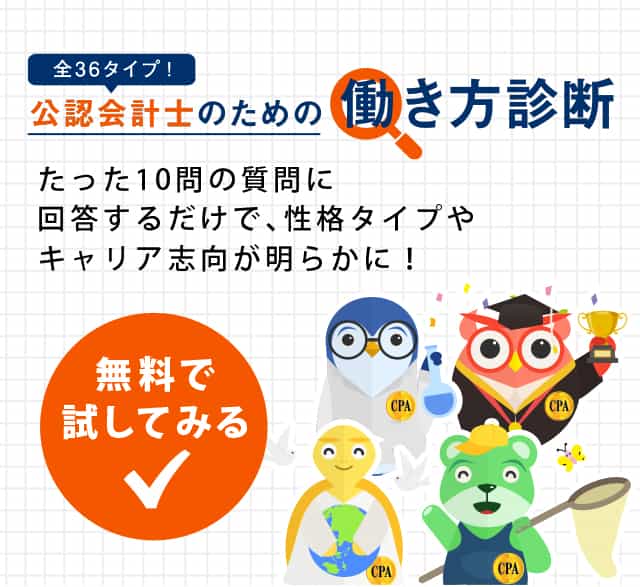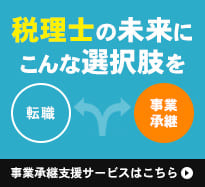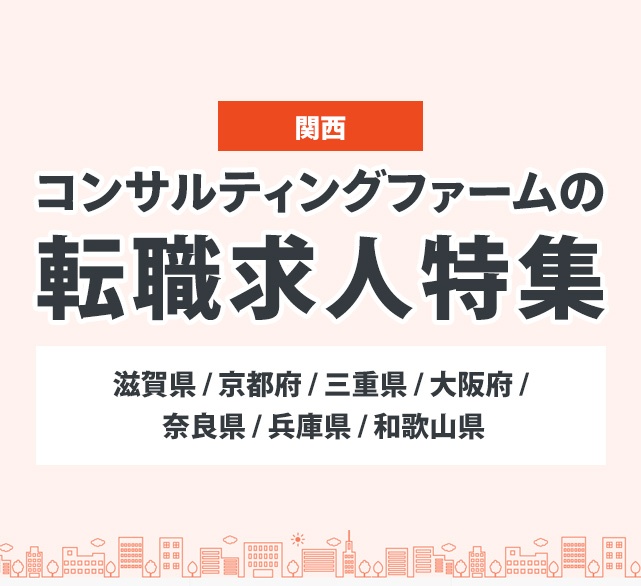■公認会計士監査の目的とAI
公認会計士が行う会計監査業務の目的を改めて振り返ってみると、その目的は企業が作成した財務諸表が企業を取り巻く利害関係者にとって信頼できるか否かを第三者である公認会計士がその信頼性を担保することにあります。
つまり、監査業務にAIを使うということは、
公認会計士がAIを使うことで企業が作成した財務諸表が信頼できると担保することが、より効果的にできるのであれば、公認会計士業務にAIを導入する意義がある
ということになります。
特に、公認会計士には会計不正を防止・発見することに対する社会からの期待は大きく、AIを利用することでこうした会計不正を防止・発見することができるのであればAIを大いに活用すべきということができるでしょう。
監査実務の現場では、現実にAIが導入されるようになっており、監査におけるAIの開発・導入が進むにつれ、監査への導入が適している領域とそうでない領域が明らかになりつつある段階のようです。
■AIに関する基礎知識
それではAIとは何ぞやといった定義づけから確認したいと思います。
(1)強いAI、弱いAIとは?
日本公認会計士協会(テクノロジー委員会)「テクノロジー委員会研究文書第11号
「監査におけるAIの利用に関する研究文書」
」(以下、「研究文書」)によると、AIに関しては確立された定義はないようです。
そしてその「研究文書」では、AIを「強いAI」と「弱いAI」を以下に分けています。
強いAI:
人間と同等の知能や感情を有するAI
弱いAI:
知能があるように見える機械やソフトウェア、すなわち、特定の領域やタスクに特化したAI
今回のテーマで定義されるAIは、監査人による監査手続等を行うことに特化したAIであり、いわゆる「弱いAI」に該当するものを前提に話は進められます。
公認会計士の仕事にとって代わるという話は、いわゆる「強いAI」の話であり、第三者による保証という業務そのものが、AIにとって代わることがない限り、この「強いAI」は、当面は登場することがなさそうです。
AIと従来ソフトウェアとの違いは、ソフトウェアが事前に組み込まれたプログラムに従って一定の処理を行うのに対し、AIは、学習したデータを基にどのような処理を行うかのモデル(AIモデル)が作成されることになります。
ちなみに、ソフトウェアは、ISO(国際標準化機構)によると「コンピュータシステムで使用されるプログラムと関連するデータ」と定義されています。単純化するとソフトウェアはプログラムと同義語ということができます。
AI総合研究所のWEBページをのぞくとAIとプログラムの違いを下記のように解説していました。
図表1 AIとプログラムの違い
|
特徴
|
AI(人工知能)
|
プログラム(≒ソフトウェア)
|
|
基本概念
|
学習して成長することができる技術
|
明確な指示に基づいて動作する手順の集合体
|
|
技術
|
機械学習や深層学習を用いてデータから学習し、アルゴリズムを進化させ、継続的にパフォーマンスを向上させる
|
事前に定義された命令や手順に基づいて動作し、設計内でのみ機能。学習や自己進化の能力はない
|
|
概念
|
人間のように思考し、判断を下す能力を目指し、問題解決や意思決定を自律的に行い、経験を蓄積
|
与えられたタスクを実行するツールとして機能し、動作は完全にプログラマーの指示に依存
|
|
提供価値
|
柔軟性と進化の可能性
|
確実性と安定性
|
参考:
AIとプログラムの違いとは?それぞれの特徴をわかりやすく解説|AI総合研究所
この違いから、プログラムは、設計にのみで目的を達成するツールであるのに対し、
AIは、継続的な学習により、自らのパフォーマンスを向上させていくことができます。
そのため、AIを活用しながらプログラムを作成させるというようなこともできますし、現にプログラムをAIによって書かせるような活用により、ソフトウェア作成の効率化は図られているようです。
(2)AIが対処する課題
「研究文書」でも紹介されている人工知能学会によるAIマップでは、AIが対処する課題を以下のように分類しています。
図表2 AIが対処する課題分類
|
課題分類
|
課題例(抜粋)
|
説明
|
応用分野
|
|
予測・制御系
|
数値予測、確率予測、予測候補提示
|
-
短期・中長期の将来の状態を予測
-
予測に基づいて機器などを制御
|
主として産業部門(製造、インフラ、物流、エネルギー、情報・通信)で活用。卸売り・小売り、イベント運営などでも活用
|
|
認識・推定系
|
異常検知、状態推定、認証
|
|
セキュリティ、医療や産業部門で活用
|
|
生成・対話系
|
音声対話、知識整理、 アドバイス、メディア生成
|
-
人の話を聞いて答えを返す
-
新しく画像やデータ 、文を生成
|
サービス産業、メディア・アート産業で活用
|
|
分析・要約系
|
数値データ分析、言語データ分析、要約
|
|
オフィス業務、監視・保全業務などで活用
|
|
設計・デザイン系
|
スケジューリング、 配置・設計、パーソナライズ
|
|
サービス産業、製造・設計、上流工程などで活用
|
|
協働・信頼形成系
|
順番付け・選択、調停・参謀
|
|
スクリーニング、投票、トーナメント、選定、合意形成など社会的活動で活用
|
参考:
AIマップβ2.0(PDF)
こうした分類のベースに「研究文書」では
、
監査における具体的な用途については、『「異常検知」や「数値データ分析」といった観点から、監査へ応用を行うことが考えられる』
としています。
また、実際の監査業務で生成AIによって文書のドラフトを作成し、その後監査人が監査調書として仕上げるといった利用を想定していました。そのほかに監査や会計に関する基準等を学習させることにより、監査人による監査基準や会計基準に関する質問に対し、生成AIが該当する基準を提示する、という利用も想定されており、すでに監査現場での導入が開始、または検討されています。
(3)生成AIとは
このように生成AIの監査への活用が具体的に見込まれるため、この生成AIの仕組みについては、もう少し深堀りしたいと思います。
生成AIは以下のように説明されます。
生成AI:
AIの一種で、洗練されたモデルを使用して入力プロンプトに応じた新しいコンテンツを生成する。生成モデルは、生成AIの実行を円滑化するためのデータとアルゴリズムを採用したコンピューター・プログラムである。生成モデルでは学習データのパターンや分布を特定し、その知見を利用者のインプットに基づく新しいデータの生成に適用することで機能する。
つまり、生成AIは入力されたデータを学習データとしてその特徴を結合し、確率分布を認識するよう学習していきます。
その後、学習したことを基に、学習データと類似した新しいデータサンプルを作成していきます。
生成AIは以下の仕組みをもって、新しいデータを作成していくことになります。
-
確率モデル
次にくる単語や画像の要素を、学習した確率分布から予測して生成
-
自己回帰型モデル
1語ずつ順番に生成していくことで、文脈に沿った自然な文章を構築
GPT(Generative Pre-trained Transformer)
-
ファインチューニング
特定のタスク向けに追加学習して精度を高める
-
強化学習による微調整
人間のフィードバックを取り入れて、より望ましい出力を学習
RLHF(Reinforcement Learning from Human Feedback)
こうした生成AIが、監査実務では、文書のドラフトを作成し、その後監査人が監査調書として仕上げるといった利用や監査実務者が監査基準や会計基準に関する質問を行い、生成AIが該当する基準を提示するといったことを可能とします。
■監査におけるAIの利用
(1)AIを利用した監査手法
「研究文書」で監査におけるAIの特徴として、監査に関連する大量のデータを活用した高度な分析や、自動化による監査人の工数を削減することが可能となる点を挙げています。監査業務において
今後AIの利用が進むと考えられる領域は、単純作業、または補助的な役割であると考えられます。
監査の各フェーズで必要とされる以下の手続においてAIの利用が進むと想定しています。
図表3 監査においてAIの利用が進むと想定されるところ
|
フェーズ
|
手続
|
概要
|
|
監査計画
|
企業及び企業環境の理解
|
産業、規制等の外部要因や企業の業績を評価するために企業内外で使用される測定指標等を理解する。
|
|
リスク評価
|
不正か誤謬かを問わず、重要な虚偽表示リスクを識別・評価する。
|
|
内部統制の評価
|
整備状況の評価
|
承認書類への押印の有無、事後承認の有無確認等、ルールへの準拠性を確認する。
|
|
実証手続
|
証憑突合
|
証憑と関連する帳簿残高を突き合わせ、記録の正確性を確かめる。
|
|
立会
|
在庫などの現物のカウント。
|
|
確認
|
紙媒体、電子媒体又はその他の媒体により、監査人が確認の相手先である第三者(確認回答者)から文書による回答を直接入手する。
|
|
分析的手続
|
財務データ相互間又は財務データと非財務データとの間に存在すると推定される関係を分析・検討することにより、財務情報を評価する。
|
|
仕訳テスト
|
監査人が検討したリスクシナリオに基づいて抽出条件を設定し、条件に該当した仕訳をテストする。
|
|
開示検証
|
財務諸表が会計基準に基づき適切に作成されているか、計算チェックや根拠資料との照合等により検証する。
|
|
監査意見表明段階
|
総括的検証
|
監査意見を表明するための十分な根拠が得られたかどうかの確認
|
(2)監査における生成AIの利用例
「研究文書」では、監査業務における生成AIの利用例として以下のようなものが想定しています。
図表4 監査におけるAIの利用例
|
区分
|
利用例
|
|
監査調書作成補助 (監査調書のドラフトの作成)
|
実施した監査手続とその結果について、端的な情報を入力することで、監査調書の様式に当てはめる形で文章を生成する。また、関連する監査基準や会計基準を自動的に調書内に挿入する等により監査調書作成の補助を行う。
|
|
監査調書査閲補助 (監査調書間の矛盾点の抽出)
|
計画した監査手続と監査結果の内容を読み込み、それぞれ要約を行い、記載内容に矛盾があれば該当箇所の抽出を行う。また、特定の勘定科目に関する複数の監査調書を読み込み、同様に矛盾点の抽出を行う。
|
|
監査手続実施補助 (監査手続の提案)
|
監査基準や各監査事務所のガイダンスを学習した生成AIを用いて、特定の勘定科目について要求される監査手続の提示を行う。また、被監査会社が属する業界や財務状況を入力することにより、想定される監査手続を列挙する。
|
|
情報収集補助 (業界情報、開示情報等の収集支援)
|
監査計画段階において、被監査会社のプレスリリースや業界情報等を収集し、その要約を提示する。また、有価証券報告書の特定の注記等について、同業他社の開示情報を収集し、列挙する。
|
|
資料作成 (議事録、フローチャートの作成)
|
経営者とのディスカッションや監査チーム内の討議等において、音声データを元に議事録のドラフトを自動生成する。被監査会社の業務記述書や、質問を元に監査人が作成した業務フローの情報からフローチャートを自動生成する。
|
これらのいずれも、監査業務に生成AIを持ち込み、直接的に利用する例を示しています。
ただ、
どのフェーズにおいても、どのような監査手続を実施すべきかの判断や、調書作成の最終的な責任は監査人にあります。
またAIの生成する情報には誤りが含まれる可能性があり、あくまでこれらの利用は補助的な用途にとどめるべきと考えられます。そのため、生成AIの利用が拡大したとしても、会計及び監査に関する監査人としての専門知識は依然として求められます。
(3)AIを利用した監査手続
監査業務の効率化・高度化に資する技術として監査手続で活用されるものの代表的なものは以下の通りです。
①データ分析(Data Analytics)
全件検査:
従来はサンプリングによる検証が中心であったものが、AI・機械学習を用いることで大量の仕訳や取引を全件検証することが可能になります。
異常検知:
仕訳データを、AIを組み込んだ監査ツールなどに読み込ませることで通常パターンとは異なる取引(例:金額の偏り、期末付近の異常仕訳、承認フローの逸脱など)を自動的に抽出することができます。
②自然言語処理(NLP)の活用
契約書・議事録のレビュー:
AIが文章を解析し、収益認識や債務条件に関連するリスクを抽出します。
開示情報チェック:
有価証券報告書・注記情報の不整合や記載漏れの検出をします。
③画像認識の活用
証憑突合:
領収書・請求書などのスキャン画像と会計データを突合し、改ざんや架空計上のリスクを把握します。
④継続的監査(Continuous Auditing)
ERPシステムやクラウド会計システムと連動し、取引をリアルタイムに監視します。
AIが異常を検知すると監査人にアラートを発信する仕組みです。
■監査におけるAI利用に伴う課題
こうしたAIを利用した監査手法により、公認会計士事務所の目的を達成することができそうですが、監査において、AI利用を行うが故の課題があります。その課題について説明します。
(1)そもそものAIの限界
AIを利用することができても、監査的には、そもそも以下の限界が存在します。
①説明しづらい
機械学習モデルの中身はプログラマーでも説明できないことが多く、その判断プロセスそのものを外部に説明できないということが考えられます。
②一定の割合で間違える
機械学習の精度は100%にならない、特定のタスクには強いが、異なる文脈や状況ではうまく機能しないと言われています。
③学習が難しい
学習データに偏りがあると出力も偏ります。学習データに過度に適応すると、未知のデータに対して性能が低下します。大量・高品質なデータが必要で、データが不十分・不正確だと精度が下がります。また学習済みモデルは新たな知識を自動的には学習しません。
(2)AIの精度・信頼性や説明可能性(ブラックボックス問題)
AIの判断根拠が「ブラックボックス」化しやすく、監査証拠としての判断根拠を説明できず、その妥当性が問われます。公認会計士が最終的に合理的説明責任を負うため、
AIの分析結果をそのまま採用できない
という課題が生じます。
(3)被監査会社のデジタル化の限界
AI分析には大量の企業データが必要ですが、機密情報の提供範囲や被監査会社から提供されるデータの粒度にバラつきがあることが想定されます。監査人のアクセス権限が制約となり、満足な結果を得ることができないなどのケースが考えられます。
(4)監査基準等の要求事項への適合性
現行の監査基準等において、監査においてAI監査ツールを活用した場合の取扱いは明確に定められていません。このため、監査の各過程にAI監査ツールを活用した場合にどのようにすれば監査基準等の要求事項に適合していると言えるか明確でないという課題があります。
このためAI監査ツールを活用しながらも、監査人は監査基準等の要求事項を満たすために従来からの手続も並行して実施する必要が生じ、かえって非効率になってしまう可能性があります。
(5)情報セキュリティに関するリスク
AI監査ツールの開発や利用には大量の被監査会社の情報を扱うこととなります。このため、以下のような情報セキュリティリスクが存在することになります。
-
AI監査ツールに機密情報や個人情報を情報セキュリティに配慮せず入力してしまう
-
入力データが生成AIの学習データに利用されてしまう
-
生成AIの回答に他社の機密情報が含まれていて、それに気づかない
情報セキュリティの課題は、インサイダー取引や個人情報流出、会社の機密情報の流出など、後々に大問題に発展する可能性があるため、特に生成AIの利用などにおいては厳重な取り扱いを行うことを要します。
これらのリスクを理解した上で、監査人は以下のような低減策を講じる必要があります。
-
不適切なAI利活用を禁止するガイドラインやマニュアルの策定
-
AI利活用に対する教育(AIリテラシー)
-
AI利用のモニタリング
-
AI法規制の遵守
情報漏洩リスクへのより具体的な対応策
としては、さらに以下の対応が考えられます。
①オンプレミス・閉域環境での利用
機密性が高いデータは、クラウド外に出さず、監査法人内サーバーまたはセキュアな閉域ネットワークでAI分析を行うことが必要となります。
②データ匿名化・マスキング
個人情報や取引先名などを匿名化したうえで、AIに入力するなどの対処が必要です。
③利用規約・契約の確認
AIベンダーがデータを学習利用しないことを契約で担保する、データ保管先(国内/国外)の明示をお互いに確認するなどの対応が必要になります。
④監査法人内のガバナンス体制
AI利用に関するガイドラインを法人内で策定。利用ログの保存、アクセス権限の最小化を徹底。
⑤クライアントへの説明責任
また、監査においてAIを利用する場合は、
その手続きと情報管理体制についてクライアントに事前説明し、同意を得る
ことが望ましいといえます。
こうしたことから、AIの利用においては、監査の利便性と情報セキュリティリスクのバランスをとった適切な利活用が求められることになります。
■AI利用による今後の可能性
こうした監査手法に様々な影響を及ぼすAIですが、働き方にも変化をもたらします。
(1)業務の効率化と集約
ルールベースの作業がAIにより高速かつ正確になり、監査業務の単純・定型作業の削減が見込まれます。
サンプリング、仕訳確認、証憑突合といった繰り返し作業がAIにより自動化されることが期待されます。
AIにより大量の取引データ・証憑データを処理できるようになり、
従来はサンプルベースだった監査が全件調査ベースに近づくなどデータ処理量の飛躍的拡大が見込まれます。
その結果、公認会計士のタスクは、「分析・判断」「リスクの特定」といった領域に時間を割けるようになります。
(2)監査時期の平準化
継続的監査(Continuous Auditing)が普及すれば、決算期末に業務が集中する従来型の働き方が緩和されることが期待されます。
通年でモニタリングできるため、繁忙期の負荷軽減が期待できるようになります。監査に「繁忙期」という言葉がなくなる日が来るかもしれません。
(3)リモート監査・デジタル監査の拡大
クラウド会計やAI分析ツールの活用により、被監査会社への常駐や大量の紙証憑確認の必要性が減少することが考えられます。
監査ツールやクラウドの発展により、在宅でも業務が完結可能になり、フレックスタイムや時短勤務制度の活用が容易になります。さらに地方在住・海外在住の監査人とも連携は容易になり、公認会計士が地方に在住するという道も開かれるかもしれません。
(4)「AIを使う人間」の重要性の増大
人間による分析・判断へ監査資源が集中することが想定されます。
つまり、業務自動化によって生まれた時間を、リスクの高い領域の深掘りや会計上の判断業務に充てることが可能になります。また
AIが検出した異常取引に対し、監査人が背景や文脈を読み取り、企業実態との整合性を見極める役割が強まります。
それゆえ、会計基準の適用判断や業界特有の会計処理の理解など、専門的知識をもとに判断する能力がより重視されるのではないかと思います。
また監査における独立性・公正性・職業的懐疑心など、人間の倫理観と職業的判断はAIに代替できません。つまり、AIにより見えてくる情報は増えることになりますが、最終判断は人間が行うという点がより強調されることになります。
このため、監査人にはAIが検出しなかったリスクを見抜く力、分析結果を監査全体に位置づける力が求められることになります。
■AI時代における今後の公認会計士の役割
AIを利用する監査が当たり前になる時代では、公認会計士は以下の能力が求められることになります。
①説明責任を果たす際の説得力と信頼構築
クライアントや利害関係者に納得感を与え、判断の根拠を説明する能力
②倫理的・法的判断が絡む意思決定の担い手
職業倫理に基づき、AIの提案を鵜呑みにせず正しい方向性を選ぶ責任
③監査戦略の策定や重点領域の選定における判断力
限られたリソースを有効に活用するための優先順位付けやリスク評価
結局、AIは「監査証拠の網羅性・効率性」を飛躍的に高め得る可能性があります。他方で、以下の点で明らかに課題があります。
-
説明責任の確保
-
データアクセスの制約の克服
-
基準の未整備
-
誤検知リスクへの対処、判断基準が不明確
-
取り扱う情報のセキュリティ確保
したがって、
公認会計士がAIに向き合うには、「AIに依存せず、専門的職業的懐疑心を補強するツール」として位置づける
ことが実務的に重要となります。
こうしたAI利用に伴う可能性と課題に向き合いながら、公認会計士監査実務を発展させる必要があるということで今回の説明は終わりたいと思います。
関連リンク