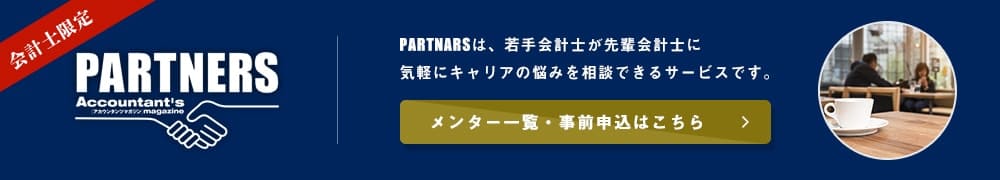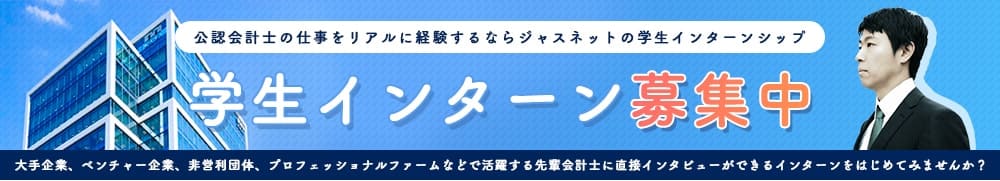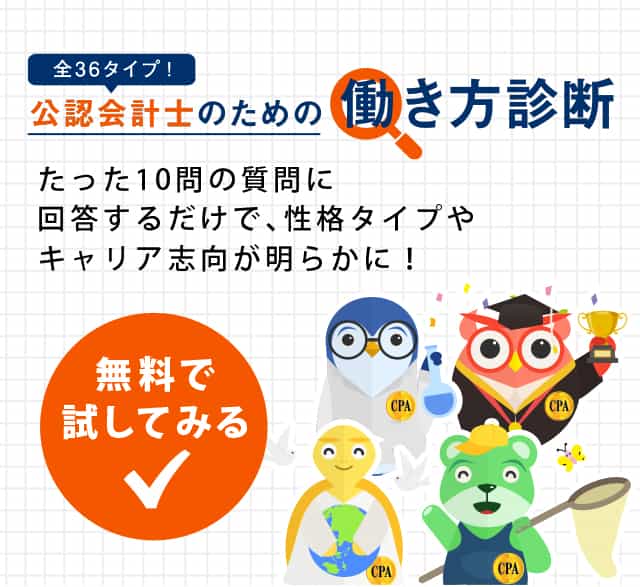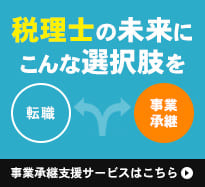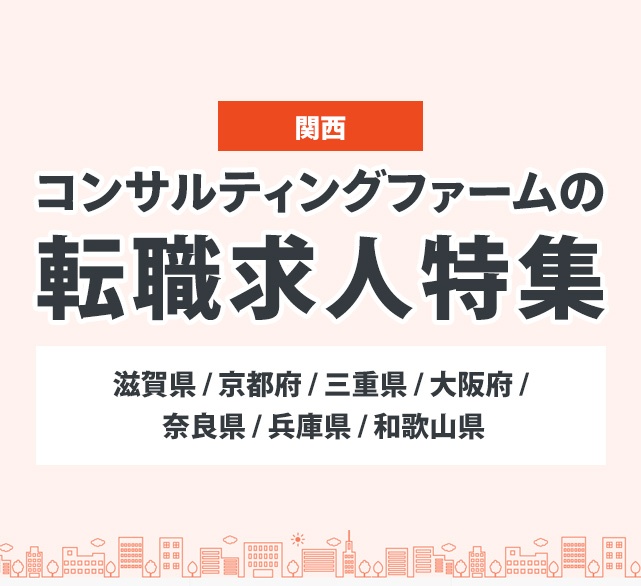■公認会計士制度の全体像と基本情報
(1)公認会計士とは何か
公認会計士は
企業の財務諸表が適正に作成されているかを第三者の立場から監査し、その結果について意見を表明する監査証明業務を独占的に行える唯一の国家資格保持者
です。
監査業務以外にも、資格を活かして活躍することができ、税務、コンサルティング、財務アドバイザリーなど幅広い分野で活躍しています。公認会計士法では公認会計士の業務を以下のように定めております。
(公認会計士の業務)
第二条 公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、
財務書類の監査又は証明をすることを業
とする。
2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する
相談に応ずることを業とすることができる。
ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
*太字は筆者
この第2条2項の業務を「
2項業務
」と言いますが、この業務はコンサルティング業務と言って差し支えないかと思います。
その他に税理士業務を行っている公認会計士がいますが、これは、公認会計士が税理士資格を保持して業務を行うことに該当し、税理士法にその根拠条文があります。
(税理士の資格)
第3条 次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。
四 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
2 公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第1項の規定により同法第2条に規定する業務を行うことができる者は、この法律の規定の適用については、公認会計士とみなす。
3 第1項第4号に掲げる公認会計士は、公認会計士法第16条第1項に規定する実務補習団体等が実施する研修のうち、財務省令で定める税法に関する研修を修了した公認会計士とする。
このように公認会計士には、監査業務、コンサルティング業務、税務業務などを行うことが法的に認められており、実社会でも活躍しています。ではどのように公認会計士になっていくのか。そのプロセスを見ていきましょう。
(2)公認会計士になるまでのプロセス概要
公認会計士になるためには以下の段階を踏む必要があります。
① 公認会計士試験(短答式試験・論文式試験)に合格すること
② その後、3年以上の実務経験と実務補習の修了すること
③ 公認会計士協会が主催する修了考査に合格すること
これらの要件をすべて満たした後、日本公認会計士協会に登録申請を行うことで、正式に公認会計士として名乗ることができます。
なお、実務経験の時期は、公認会計士試験合格の前後を問いません。そのため、実際は少数派と思いますが、公認会計士になるために必要な実務経験を積み、その後試験に挑戦することは可能です。
こうした柔軟性のある制度設計により、様々なライフスタイルに対応した資格取得が可能となっています。
(3)公認会計士の社会的地位と価値
公認会計士は社会的に非常に高い信頼と評価を得ている職業です。特に上場企業の財務情報の信頼性を担保する専門家として、経済社会において不可欠な存在となっています。
また、国際的にも通用する資格であり、グローバルなビジネス環境においても活躍の場が広がっています。
一部の資料によると公認会計士の平均年収は746.6万円とされており、一般的な職業と比較して高水準の収入が期待できます。さらに、経験を積むことで監査法人のパートナーや独立開業、企業の財務担当役員など、より高いポジションへのキャリアアップも可能です。年収1,000万円を超える公認会計士は珍しくありません。
■公認会計士試験の制度と内容
(1)試験制度の仕組みと特徴
最初で最大の難関とされる公認会計士試験は、
短答式試験と論文式試験の2段階で構成される国家試験
です。
①短答式試験とは?
短答式試験は、マークシート方式で解答する試験で、
財務会計論、管理会計論、監査論、企業法の全4科目
が出題されます。この試験は毎年12月と5月の年2回実施されるため、受験者は自分の学習進度に合わせて受験時期を選択できます。
②論文式試験とは?
短答式試験に合格すると、論文式試験を受験する資格を得られます。論文式試験は年1回、8月中旬に実施され、
会計学、監査論、企業法、租税法と選択科目1つの計5科目
で構成されます。すべて記述式での解答が求められ、思考力、判断力、応用能力、論述力等が総合的に評価されます。
③短答式試験の免除について
短答式試験に合格した受験者は、その後
2年間は短答式試験の受験が免除
されます。そのため、短答式試験に合格した年の論文式試験に落ちてしまったとしても、翌年と翌々年は論文式試験にのみ集中して受験可能です。この制度により、受験者の負担軽減と効率的な学習を可能とすることを目的としています。
(2)合格率と難易度の実態
公認会計士試験の合格率は、ここ数年で変動が見られます。試験全体の合格率は、令和2年以前まで10%~11%程で推移していましたが、直近4年は10%を切る状況となっています。これは受験者数の増加に対して、合格者数の伸びが追いついていないことが主な要因です。
令和6年の願書提出者数は増加し、令和6(2024)年度における公認会計士試験全体の出願者は21,573名(前年は20,317名)となり過去10年で最多となりましたが、合格率は低下し、7.4%となり過去10年で最低となりました。
つまり
公認会計士試験を目指す人が増加していることから、願書提出者数は増加しているにもかかわらず、論文式試験の合格者数は、1,603人(前年は1,544人)と合格率は低下するという傾向
が続いています。
なお、2025年1月17日に発表された令和7年第I回短答式試験の結果では、願書提出数が15,990人、答案提出数が12,336人、合格者数が1,383人となりました。願書提出者数は
過去7年間で最多
を更新しており、公認会計士への関心の高まりがうかがえます。
短答式試験の合格率は12.0%と低く、狭き門となっているように見えますが、論文式試験を受験する資格を有するという点で見ると4,000名前後で推移しています。合格のための得点率も毎回大幅な乖離はないことから、
難易度が大きく変わったということはなく、一定レベル以上に達すれば、短答式試験は合格できる
のではないかと思います。
(4)短答式試験科目と出題内容の詳細
短答式試験の各科目について詳しく見てみましょう。まず、短答式試験は、「基本的な問題を幅広く出題することにより、論文式試験を受験するために必要な知識を体系的に理解しているか否か」を判定する試験です。
①財務会計論の出題内容とは?
財務会計論は、企業会計の基準や実務について幅広い知識が問われます。計算問題と理論問題の両方が出題され、特に計算問題では正確性とスピードが要求されます。問題は、与えられた4つの文章の中から、正しい内容の文章の組み合わせを6つの選択肢から選ぶ形式が主となります。
②管理会計論の出題内容とは?
管理会計論では、理論問題と計算問題の両方が出題されます。特に、計算問題はスピードが重視され、計算が苦手だと時間切れになってしまいます。計算問題は1問1問のボリュームは小さいので、いかに全てを早く正確に解くかが合否の分かれ道になります。計算問題の選択肢は基本的に数値になりますので、選択肢がヒントになることもあります。
③監査論の出題内容とは?
監査論は、監査の基本的な考え方から具体的な監査手続きまで幅広い内容が出題されます。
④企業法の出題内容とは?
企業法では、会社法を中心とした法律知識が問われ、条文の理解と適用能力が重要となります。
⑤短答式試験の配点
現在の短答式試験において、計算問題のある科目(財務会計論及び管理会計論)では、問題数が少なく1問あたりの配点が高くなっています。一方で、理論問題のみの科目 (監査論及び企業法)では、問題数に対して試験時間に余裕がある状況となっています。このため、令和8年公認会計士試験から、各科目の配点(合計点)や問題の難易度など現在の短答式試験の基本的な形は維持しつつ、1問あたりの配点、問題数及び試験時間等の調整が行われることになります。
(5)論文式試験科目と出題内容の詳細
①論文式試験の傾向
論文式試験では、短答式試験とは大きく異なり、記述式での解答が求められます。応用力が問われ、会計基準や監査基準、会社法にそのまま記載してある内容が問われることは基本的にありません。
論文式試験は短答式試験と比べ、詳細な知識だけでなく、それを具体的に適用する力や論理的に説明する力を求められます。
このため、この試験で合格点を取るには、単なる暗記を超えた深い理解が必要です。
金融庁の公認会計士・監査審査会のホームページを確認すれば、各科目の範囲、出題の趣旨、解答を入手することができます。公認会計士を目指される方は、こうした情報に定期的に触れ、情報をアップデートすることは必須かと思います。
論文式試験では解答内容の正確性だけでなく、論理展開や問題への理解度が評価対象となります。
②
会計学の出題内容とは?
会計学は、最も試験時間が長く、試験範囲も広範囲及びます。最低限、試験頻出分野の理解が必要です。会計学の問題は細かい理論から計算問題まで幅広く出題されるため、取り組むべき分野の優先順位を付けることが重要です。頻出分野は「収益認識」「減価償却」「連結会計」といった基礎的かつ試験で多くの配点が振り分けられるようです。
③
監査論の出題内容とは?
監査論は、監査報告書や監査手続に関して、最新の制度や実務事例をふまえた論述力が重要となります。理論的な知識だけでなく、実務的な視点と問題に対する応用力が求められます。試験では特に実務を意識した事例分析問題が頻出で、具体的なシチュエーションを読み解いて適切な監査判断を求められる問題に注目する必要があります。
④
企業法の出題内容とは?
企業法の攻略には、まず試験範囲である会社法や商法の条文に精通することです。特に「株主総会」「取締役会」などの機関の問題は試験で頻出のテーマに注目することです。出題形式が「論点の説明」や「具体的な事例解釈」である場合が多いです。
⑤租税法の出題内容とは?
法人税、所得税、消費税など多様な税目の実践的計算と理論が問われる傾向です。条文の理解と問題演習を通じて広範囲な内容をカバーし、理解を深めていく必要があります。まず基本となる租税法の条文を正確に理解し、条文の構造や趣旨を掴むことで、問題演習を効果的に進めることができると思われます。
⑥選択科目の出題内容とは?
経営学や経済学などでは基本理論と説明力を磨いていく必要があります。
専門学校の選択により合格水準に達する講座を受けられるかが、合格を左右する可能性がある
ため入念な情報収集が必要です。
なお、試験中は法規集が配布されますので、そもそも論文式試験においては法規集の内容を暗記すること自体がさほど重要ではなくなるといわれています。一方で
学習に当たっては常に原文に触れ、当たる都度読み返すことをお勧めします。
実務では必要な動作となるため、こうした習慣を試験勉強を通じて身につけていくことが公認会計士として身を立てていく上では必須の所作と考えます。
この記事の著者に相談をする
■学生が公認会計士を目指す場合のメリットと戦略
(1)学生の圧倒的なメリット
大学生が公認会計士を目指す最大のメリットは、
圧倒的な時間の確保のしやすさ
です。授業を受ける必要はあるものの、社会人と比較すると圧倒的に勉強時間を確保することができます。公認会計士になるには、1日8時間以上の学習時間を確保することが必要ですが、その時間確保も学生であれば現実に確保可能であり、集中的な学習が自身を短期間での合格を可能にします。
合格者には大学在学中の学生が多くなる傾向にあります。実際、公認会計士試験合格者の約4割は大学生が占めており、時間的余裕が合格に直結していることがわかります。
特に、いわゆる偏差値の高い「上位大学」の学生の方は、多くの場合、大学受験という受験経験があり「学習をする」という癖がすでに身についています。その経験を活かして、公認会計士試験対策の学習を淡々と進めている傾向にあります。
就職活動においても、公認会計士の資格は大きなアドバンテージとなります。
公認会計士の資格があるからこそ就職できる法人もあります。
大手監査法人への就職では学歴よりも試験合格の事実が重視されるため、出身大学に関係なく有名法人への道が開かれます。また面接においても社会が求めるスキルをきちんと把握できればインプット情報は十分なので、面接の場でうまく表現することで会社にとって自分がいかに有用かを売り込むことができます。こうしたことは、他の資格では得られない大きなメリットです。
(2)学生の効果的な学習戦略
学生が公認会計士試験に取り組む場合、受験専念の方は1年~1.5年、大学生の方は1.5年~2年での受験プランが一般的なようです。大学の授業と並行しながらでも、計画的に学習を進めることで合格を目指せます。
学習時間の配分については、
平日は授業の合間や放課後に4~6時間、休日は8~10時間程度の学習時間を確保することが理想的
です。大学の長期休暇期間を活用すれば、集中的な学習により大幅な学習進度の向上が期待できます。
資格スクールの活用は重要な戦略です。公認会計士試験合格に向けて重要な学習環境として、
受験を考えるほぼ全ての大学生が資格スクールを活用
しています。専門的な指導と体系的なカリキュラムにより、独学よりも効率的な学習が可能となります。
学習計画については、入門・基礎期では基本的な概念の理解に重点を置き、上級期では過去問演習と応用問題への対応力向上を図る必要があります。特に論文式試験については、記述力の向上が重要であり、定期的な答案作成練習が不可欠です。
(3)学生特有の注意点と対策
一方で、大学生活との両立には課題もあります。サークル活動や友人との時間、アルバイトなどとの兼ね合いを考える必要があります。特に、大学生活の醍醐味とされる様々な経験と資格勉強のバランスを取ることは、精神的な負担となります。
就職活動の時期と試験時期が重なる場合もあるため、スケジュール管理が重要になります。特に、12月の短答式試験の時期は就職活動の準備期間と重なるようです。多くの学生は、公認会計士試験合格を優先し、その後の就職活動で監査法人を目指すパターンを選択します。
経済的な負担も考慮すべき点です。公認会計士の資格取得には、試験対策として専門の予備校や講座を受講することが一般的で、その費用は初学者で70万円から80万円程度、繰り返しで30万円~40万円程度が相場となっています。学生や若手社会人にとっては大きな経済的負担となるため、奨学金制度や教育ローンの活用、アルバイトとの両立などを検討する必要があります。
また、学習のモチベーション維持も重要な課題です。公認会計士試験はほぼ間違いなく長期戦となるため、途中で挫折する学生も少なくありません。
同じ目標を持つ仲間との情報交換や、定期的な進捗確認により、継続的な学習を支援する仕組みづくりが重要です。
ジャスネットに登録してエージェントに相談する(無料)
■社会人が公認会計士を目指す場合のメリットと戦略
(1)社会人受験者の増加傾向とメリット
①社会人受験者の傾向
近年、公認会計士資格の人気が高まり、全体的に出願者数が増加しています。直近の2023年試験では、出願者20,317名の内、24.2%にあたる4,918名(会社員3,223名、公務員647名、会計事務所員838名、会計士補49名、税理士45名、教員45名、教育・学習支援者71名)が社会人でした。
2024年試験では、出願者21,573名の内、24.3%にあたる5,245名(会社員3,485名、公務員717名、会計事務所員848名、会計士補46名、税理士44名、教員36名、教育・学習支援者69名)が社会人。また、基本的に短答式試験合格者が受験する論文式試験の受験者数も、社会人受験生は2016年度の772名から2023年度には883名、2024年には873名にまで伸びており、社会人受験者は着実に増加傾向にあります。
出典:金融庁 公認会計士・監査審査会(CPAAOB)の公式「合格者調(統計)」PDFより
② 社会人ならではの強み
社会人の強みとして、
効率性やタスク管理の能力、実社会における実務経験
といった点は、学生にはない社会人ならではの強みがあります。限られた時間の中で成果を出すためのスキルが既に身についているため、学習計画の立案と実行においては学生よりもアドバンテージがあると言えるでしょう。また、お仕事で会計や監査、コンサルティング関連の業務をしている方は、
実務経験が活きて学習イメージがつきやすい
という利点もあります。
社会人受験者のモチベーションは非常に高く、明確なキャリアアップの目標を持って挑戦する方が多いのも特徴です。現在の仕事に対する不満や将来への不安から、より専門性の高い職業への転身を図りたいという強い動機を持っています。このような内発的なモチベーションは、長期間にわたる学習継続において大きな力となります。
(2)社会人の学習戦略と時間管理
社会人の方は
2年~3年で受験プランを設定するのが一般的
です。働きながらの学習では、通勤時間や休憩時間などの細切れの時間を有効活用することで、受験専念型の方との「学習時間の差」を埋めていることが重要です。
具体的な学習時間の確保方法として、平日の朝1~2時間の早朝学習、通勤電車での理論学習、昼休みの問題演習、帰宅後2~3時間の学習といったパターンなど様々です。休日には6~8時間程度の学習時間を確保し、平日の学習内容の復習と応用問題への取り組みを行います。
近年は在宅ワークで働く方も増え、社会人の方でも会計士試験の学習に必要な学習時間を確保できる方も増えているようです。通勤時間の削減により、その分を学習時間に充てることができ、働き方改革の恩恵を受けて挑戦しやすい環境が整いつつあります。
効率的な学習方法として、スマートフォンアプリやタブレットを活用した学習も有効です。移動時間や待ち時間を活用した学習により、年間で相当な学習時間を確保することが可能となりました。
(3)社会人特有の課題と解決策
公認会計士試験の難しさは、学習内容の難解さはさることながら、膨大な学習量にこそという点があります。そのため、比較的時間にゆとりのある学生や学習専念者をライバルとした場合、時間的に社会人の方が不利にならざるを得ないのは確かです。特に、計算科目については継続的な練習が必要であり、時間の制約がある社会人にとって大きな課題となります。
しかし、多忙で全く学習時間がとれない方であれば話は別ですが、通勤時間、帰宅後や休日を使って学習できる方であれば、合格までの学習プランを練ることは可能です。重要なのは現実的な学習計画の立案と継続的な実行です。
社会人受験者の中には、学習の途中で会社を辞めて受験専念に切り替える方もいます。この判断については、
経済的な状況、家族の理解、学習の進捗状況
などを総合的に考慮して行う必要があります。特に、短答式試験に合格した後、論文式試験に専念するために退職するパターンもあるようです。
配偶者や子供がいる場合は、学習時間の確保には家族の理解と協力が不可欠となります。学習計画について家族と十分に話し合い、理解を得ることで、安心して学習に専念できる環境を整えることができます。
(4)異業種からのキャリアチェンジ戦略
会計とは関係のない業界で働いている社会人の方も多く公認会計士を目指しています。異業種からのキャリアチェンジの場合、会計・監査の基礎知識がないため、学習開始時のハードルが高くなる傾向があります。しかし、社会人としての経験は公認会計士になってからも必ず活きます。
各人がそれぞれの職業で培った能力が監査やコンサルティングなどの公認会計士業務を行う上において価値を発揮します。多様なバックグラウンドを持つ公認会計士の需要は高まっており、資格取得後の差別化要素になります。
異業種からの転身の場合、まず会計・簿記の基礎から学習を開始し、段階的に専門知識を身につけていく必要があります。日商簿記2級・1級の取得から始めて、公認会計士試験へとステップアップしていく方法がよいでしょう。
(参考)
遅すぎる? 社会人で公認会計士を目指しても大丈夫? |公認会計士の転職ならジャスネットキャリア
■公認会計士試験合格後の道のり
(1)実務経験の要件と詳細
公認会計士の登録をするためには、3年以上の実務経験(業務補助等)が必要です。
通常は、監査法人で経験を積みますが、一定の条件を満たしていれば、会計事務所やコンサルティングファーム、金融機関、事業会社、公的機関なども対象となります。
実務経験には「業務補助」と「実務従事」の2種類があり、業務補助と実務従事の両方を経験している場合は、両方の期間を通算することが可能です。
業務補助とは、監査証明業務に関して公認会計士又は監査法人を補助することを指します。具体的には、監査法人の監査チームの一員として監査手続きを実施し、監査調書の作成、クライアントとの連絡調整、監査結果の取りまとめなどの業務を行います。業務補助は、原則として、1年につき2以上の法人の監査証明業務を対象として行わなければなりません。金融商品取引法の規定により監査証明を受けなければならない法人や資本金額が1億円を超える会社法上の会計監査人設置会社である場合には、1年につき1以上の法人で足ります。
実務従事とは、監査証明業務以外で、財務に関する監査、分析その他の実務に従事することを指します。単純な経理事務や記帳業務では認められず、特定の要件を満たした業務のみを実務期間として換算します。具体的には、一般企業の経理・財務部門での業務、金融機関における融資審査や企業分析業務、コンサルティングファームでの財務アドバイザリー業務などが該当するようです。
(2)監査法人以外での実務経験
監査法人以外での実務経験についても詳しく見てみましょう。一般企業においては、経理・財務部門での業務が実務従事として認められます。具体的には、決算業務、予算管理、資金管理、財務分析、内部統制の整備・運用などの業務が該当します。ただし、単純な記帳業務や伝票整理などの定型的な事務作業は実務経験として認められません。
金融機関においては、法人融資業務、投資審査業務、企業格付業務、資産運用業務などが実務従事として認められます。銀行における法人融資の業務、保険会社における資産運用のための各企業の財務内容調査の業務、保険会社における投融資審査、社内格付付与、業界レポート作成などが具体例として挙げられます。
国または地方公共団体においても、実務従事に該当する業務があります。国税局における税務調査の業務、県庁における市町村の財務監査や地方交付税に関する検査の業務、市役所における地方公営企業に係る決算書類作成業務や財務諸表の分析に関する業務などが該当します。注意点として、法人の税務申告は実務従事とは認められませんが、税務調査は実務従事に該当します。
(3)実務補習制度の詳細
実務補習は、公認会計士としての実務経験を積む中で、さらに高度な知識やスキルを習得するための研修プログラムです。この実務補習は、
公認会計士試験に合格した後、日本公認会計士協会が実施する形式で行われ、主に座学を通じて進められます。
目的は、理論と実務の架け橋を構築し、将来的にプロフェッショナルな公認会計士として自立できる能力を養うことにあります。
実務補習の修業年限は3年間となっており、実務補習所への通学やeラーニングなどで講義を受け、必修単位を取得します。実務補習所は東京・東海・近畿・九州の4地域で実施されており、平日の夜や土日に実務補習所及びeラーニング等で講義を受けます。一部では土曜クラスも設けられていますので、平日に受講できない人も受講可能です。
実務補習の内容は多岐にわたり以下の6分野について学習します。
-
会計に関する理論及び実務
-
監査に関する理論及び実務
-
経営に関する理論及び実務
-
税に関する理論及び実務
-
コンピュータに関する理論及び実務
-
公認会計士の業務に関する法規及び職業倫理
単位数等については、実務補習講義として1学年(J1):180単位以上、2学年(J2):40単位以上、3学年(J):20単位以上、ディスカッション・ゼミナールで30単位以上、かつ3年間で270単位以上の取得が必要です。おおよそ70%が1年目に行われています。
また考査(修了考査とは異なる考査)として、3年間で10回実施される考査全てを受験し、合計60単位以上かつ各考査で40%以上、監査総合グループ・税務グループごとに当該グループに属する考査の成績の合計点が、当該考査の満点の合計点の60%以上を修得する必要があります。
(4)修了考査の詳細と対策
修了考査は、公認会計士としての最終段階に位置付けられる試験です。この試験に合格することで、日本公認会計士協会に登録が可能となり、正式に公認会計士として活動できるようになります。
修了考査を受験するためには、実務補習を規定の内容と期間修了していることが必要
です。
①修了考査で出題される内容とは?
修了考査の内容は、
実務補習で勉強する内容の「監査」「会計」「税務」「経営・IT」「法規・職業倫理」の5つの科目を2日間に渡って受験する
試験です。試験時間は1~3時間の合計12時間となり、論文式試験と同じくらいのハードな日程となります。通常は12月第2週目の土日に実施されます。
合格基準は基本的に総点数の60%とされていますが、1科目でも総点数の40%未満だった場合は不合格となります。修了考査の合格率は、近年ではおよそ70%程度%となっています。
②修了考査を合格するには?
修了考査は、公認会計士実務に根差した難易度の高い問題が出題されます。無難に課題をこなして単位を取得しているだけでは合格できません。確実な合格を目指すならば、早いうちから学習に取り組むことが必要です。なお、こちらに、修了考査に受からない人の特徴を解説していますので、どこかのタイミングでご一読することをお勧めします。
(参考)
修了考査とは?受からない人の5つ特徴と、その対策3選 |公認会計士の転職ならジャスネットキャリア
修了考査に不合格だった場合は公認会計士の登録ができません。しかし次回以降の再受験は可能です。受験回数や年齢の制限もありません。
ただし再受験の回数が増えるほど合格率は下がると言われ、試験自体は年1回しか実施されないため、資格取得への意志が固いうちに合格することが必要です。
■効果的な学習方法と時間管理
(1)必要な学習時間と計画の立て方
公認会計士試験の勉強時間は、3,500時間が一つの目安です。最短合格を狙う場合でも、最低2,500時間の勉強時間が必要となります。
公認会計士試験は、1次試験「短答式試験」と2次試験「論文式試験」の2段階試験となっているため、2回目・3回目の試験で段階的に合格する人も多くいます。よって受験に費やす年数によって、勉強時間に大きな幅が生じます。
効果的な学習計画を立てるためには、まず自分の生活パターンを把握し、確実に確保できる学習時間を算出することが重要です。その上で、各科目の特性を理解し、バランスよく学習時間を配分する必要があります。計算科目は継続的な練習が必要であり、理論科目は理解に時間をかけた後、暗記作業に入るという流れが一般的です。
(2)予備校活用の重要性と選択基準
独学で公認会計士試験に合格することは不可能ではありませんが、初学者が独学で公認会計士試験に合格するのはかなり稀です。現に多くの受験生が何かしらの予備校や資格対策講座を受講して試験対策をしています。
予備校や講座を利用するメリットは、
効率的に学習できるカリキュラム、モチベーション維持、試験のプロによる試験分析、法改正への対策
などが挙げられます。特に、公認会計士試験は毎年のように会計基準や監査基準の改正があるため、最新情報の入手は独学では困難です。
公認会計士の資格取得には、試験対策として専門の予備校や講座を受講することが一般的ですが、高額な投資となるため、予備校選択は慎重に行う必要があります。
予備校選択の基準としては、
合格実績、講師の質、教材の充実度、サポート体制、通学・通信の利便性、費用対効果
などが挙げられます。
自分の学習スタイルに合った予備校を選ぶことも重要です。集団授業が得意な人、少数の指導を好む人、通信教育で自分のペースで学習したい人など、それぞれに適した予備校があります。
(3)科目別学習戦略
各科目の特性を理解した学習戦略が合格への近道です。財務会計論は計算と理論の両方が出題されるため、基本的な仕訳から複雑な連結会計まで段階的に理解を深める必要があります。計算問題では正確性とスピードが要求されるため、反復練習により解答パターンを身につけることが重要です。
管理会計論も計算と理論の両方が出題されますが、特に計算問題の比重が高い科目です。原価計算の基本から始まり、予算管理、業績評価、意思決定会計など幅広い分野をカバーします。計算スピードの向上が合否を左右するため、毎日の計算練習が欠かせません。
監査論は理論科目の代表格で、監査の基本的な考え方から具体的な監査手続きまで幅広い内容が出題されます。監査基準や監査基準委員会報告書の内容理解が基本となりますが、単純な暗記ではなく、監査の目的や手続きの意味を理解することが重要です。
企業法は会社法を中心とした法律科目で、条文の理解と適用能力が問われます。法律特有の表現や論理構造に慣れることが必要で、時には判例の理解も重要な要素となります。
租税法は法人税法、所得税法、消費税法が出題範囲で、税法特有の計算技術と理論の理解が必要です。理論では、法令基準集が配付されますので暗記しなくても良いということではなく学習時には、条文を普段から引いて、本番での法令基準集の取り扱い方を理解しておくことが必要となります。
(4)継続的な学習のコツとモチベーション管理
公認会計士試験は長期戦となるため、モチベーションの維持が最も重要な要素の一つです。学習を継続するためには、現実的な目標設定と定期的な進捗確認が重要です。特に社会人の場合は、無理のない学習計画を立て、短期間での詰め込み学習よりも継続的な学習習慣の確立が成功の鍵となります。
目標設定については、最終的な試験合格という長期目標に加えて、月次・週次の短期目標を設定することが有効です。例えば、「今月中に財務会計論のテキストを1周させる」「今週は過去問を10問解く」といった具体的で測定可能な目標を設定します。
学習環境の整備も重要です。自宅での学習が難しい場合は、図書館や自習室の利用、カフェでの学習など、自分に合った学習場所を見つけることが大切です。また、学習仲間の存在もモチベーション維持に大きく貢献します。
定期的な模擬試験の受験により、現在の実力を客観的に把握し、学習方針の修正を行うことも重要です。最初は模擬試験の結果が散々だったとしても、そのようなものだと割り切って一喜一憂するのではなく、弱点の発見と改善のツールとして活用しましょう。
■就職活動と監査法人への道
(1)試験合格後の就職活動プロセス
公認会計士論文式試験の結果は、11月中旬に発表されますが、
監査法人の就活はそこから2~3週間程の超短期決戦
で行われます。公認会計士試験の合格発表の当日から説明会の予約やエントリーシートの受付が始まり、12月初旬には内定が出ます。この短期間での就職活動は、他の業界とは大きく異なる特徴です。
就職活動の準備は、8月の論文式試験後から始めることが重要です。試験勉強で疲弊した状態でも、就職活動への準備を怠ると希望する監査法人への就職が困難になる可能性があります。下記の記事も参考にしてください。
(参考)
【2025年版】公認会計士の就活完全ガイド!|超短期決戦を勝ち抜く戦略と内定獲得の秘訣 |公認会計士の転職ならジャスネットキャリア
この期間を活用して、各監査法人の説明会への参加、企業研究、面接対策などを進める必要があります。
監査法人の採用では、試験の成績よりも人物重視の傾向が強まっています。きちんと質問に対する回答を正面から行うコミュニケーション能力、チームワーク、学習意欲、将来のビジョンなどが評価の対象となります。
(2)Big4監査法人と中小監査法人の選択
監査法人は大きくBig4監査法人と中小監査法人に分かれます。それぞれに特徴があり、自分のキャリア目標に応じて選択する必要があります。
Big4監査法人のメリットは、
大規模な上場企業の監査に携わることができ、国際的な業務経験を積める
点です。給与水準も高く、充実した研修制度により専門性を高めることができます。一方で、業務量が多く、激務になりがちという面もあります。
中小監査法人のメリットは、
幅広い業務に携わることができ、クライアントとの距離が近い
点です。また、個人の裁量が大きく、早期からマネジメント業務に関わることができます。給与水準はBig4と比較すると低めですが、ワークライフバランスは取りやすい傾向にあります。
ただこうした監査法人への就職という選択肢は、多数派ゆえ、
公認会計士間での差別化が困難になるという、中長期的な課題にぶつかる
ことになります。また監査法人と一般事業会社は文化が異なっているため、監査法人勤務の後に転職を考えるときそれなりの苦労が待ち受けています。こうした点も踏まえて監査法人への就職を選択すべきです。
(3)監査法人以外のキャリア選択
公認会計士試験合格者の就職先は監査法人だけではありません。一般企業の経理・財務部門、コンサルティングファーム、金融機関、税理士法人など多様な選択肢があります。
一般企業への就職では、IPO準備企業や上場企業の財務部門での需要は常にあります。公認会計士の専門知識を活かした財務分析、内部統制の整備、投資家向けの情報開示などの業務に携わることが期待されています。
コンサルティングファームでは、財務アドバイザリー、事業再生、M&Aアドバイザリーなどの業務があります。監査法人とは異なる視点から企業の財務問題解決に関わることができ、より経営に近い業務の経験が期待できます。
ただ、
公認会計士資格が活きるのはやはり「監査スキルに尽きる」というのことを多くの公認会計士が口をそろえて言います。
こうした声も耳に傾けながら将来の道を選択することが必要です。
■キャリアパスと将来性
(1)公認会計士のキャリアパスの多様性
公認会計士資格取得後のキャリアパスは非常に多様です。監査法人での監査業務をスタートとして、その後一般企業の財務・経理部門、コンサルティングファーム、独立開業など様々な選択肢があります。また、海外での活躍の機会も豊富で、グローバルなキャリア形成も可能です。
監査法人でのキャリアパスとしては、スタッフ→シニア→マネージャー→シニアマネージャー→パートナーという階層があります。パートナーになると監査法人の経営にも参画し、年収2000万円以上を得ることも可能です。また、監査法人内でも監査部門以外に、アドバイザリー部門、税務部門などでの専門性を高めることもできます。
一般企業への転職では、上場企業やIPO準備企業の財務・経理部門でのニーズが高まっています。CFO(最高財務責任者)や財務担当取締役といった経営陣への道も開かれています。監査法人での経験を活かした内部統制の整備、財務報告の高度化、投資家向けIRなどの業務で活躍できます。
独立開業では、税理士業務、会計業務、経営コンサルティング業務などを組み合わせて事業を展開できます。特に中小企業向けのサービスでは、公認会計士の信頼性と専門性が大きな武器となります。
(2)収入面での魅力と将来性
令和5年の厚生労働省の賃金構造基本統計調査によると、公認会計士の平均年収は922万円、男女別にみると、男性が989万円、女性が728万円という結果だそうです。これは、一般的な職業と比較して高水準の収入が期待できます。また、経験を積むことで更なる収入向上も見込めます。
監査法人での初年度年収は500万円程度からスタートし、経験年数に応じて昇給していきます。マネージャークラスでは800万円~1200万円、シニアマネージャーでは1000万円~1500万円、パートナーでは2000万円以上の年収を得るといわれています。
さらに、一般企業への転職では、財務部長クラスで1000万円~1500万円、CFOクラスでは1500万円~3000万円の年収も期待できます。特に成長企業やグローバル企業では高い報酬を得ることが可能です。
独立開業の場合は、顧客基盤の構築により大きく収入が左右されますが、成功すれば年収数千万円を得ることも可能です。特に、法定監査業務や税理士業務と組み合わせることで安定的な収入基盤を確保できます。
(3)グローバルキャリアの可能性
公認会計士資格は国際的にも通用する資格であり、海外での活躍の機会も豊富です。Big4監査法人では海外赴任の機会があり、アジア、ヨーロッパ、アメリカなど世界各地で監査業務に携わることができます。
日本企業の海外展開に伴い、国際税務や海外子会社管理などの専門性を持つ公認会計士の需要は高まっています。
多国籍企業の財務部門では、世界各地の子会社の財務管理、連結決算、国際税務などの業務に携わることができます。これらの経験は、将来的にグローバル企業の経営陣への道を開くことにもつながります。
(参考)
公認会計士とは?経済社会を支えるプロフェッショナルの仕事観とキャリアに迫る |公認会計士の転職ならジャスネットキャリア
■まとめ:あなたに最適な公認会計士への道筋
(1)学生・社会人それぞれの最適戦略
公認会計士になるための道のりは決して平坦ではありませんが、学生・社会人それぞれに異なるメリットと戦略があります。学生であれば時間的余裕を活かした集中的な学習が可能であり、1.5年~2年での合格を目指すことができます。一方、社会人であれば実務経験や効率的な学習管理能力を武器に、2年~3年の計画で挑戦すべきです。
学生の場合は、大学生活との両立を図りながら、就職活動も含めた総合的な人生設計の中で公認会計士を位置づけることが重要です。
たった一度の人生ですので、アルバイトやサークル活動を制限してでも資格取得を優先するかどうかの判断はご自身に求められます。
他方で、自身のライバルとなる人たちは学生時代をなげうって資格所得に励んでいる人もいます。選択したとしても、決して中途半端にならないようにしてください。
社会人の場合は、
現在の仕事を続けながらの学習か、退職して受験専念にするかの選択が重要な分岐点
となります。家族の理解と経済的な準備、キャリアブランクのリスクなどを含めて、総合的な判断が必要です。
(2)成功のための重要ポイント
成功のための重要ポイントとして、3つあります。まず
①現実的で継続可能な学習計画の立てられるか
が挙げられます。理想と現実のバランスを取り、無理のない範囲で継続することこそが、最大限の効果を得られると信じて、計画を立てることが重要です。
次に、
②適切な学習環境の整備
です。予備校の選択、学習場所の確保、学習仲間との情報交換など、学習を支える環境づくりが成功の鍵となります。
③モチベーションの維持も重要な要素
です。長期戦となる公認会計士試験では、挫折しそうになる時期もありますが、明確な目標と強い意志を持ち続けることが合格への道筋となります。
(3)公認会計士としての社会貢献
公認会計士は、企業の財務情報の信頼性を担保し、投資家や債権者などのステークホルダーに対して重要な情報を提供する役割を担っています。これは、資本市場の健全性と透明性を支える重要な社会的責務です。
また、中小企業の経営支援、事業承継のアドバイス、非営利組織の会計監査など、幅広い分野で社会に貢献することができます。公認会計士の専門知識と社会的信用は、様々な場面で社会の発展に寄与します。
(4)最終メッセージ
重要なのは
自分の置かれた環境を正しく認識し、それに適した学習計画を立てること
です。試験合格はゴールではなく、公認会計士としてのキャリアのスタートラインに立つための第一歩です。実務経験、実務補習、修了考査を経て、真の公認会計士として社会に貢献できる専門家になるための長期的な視点を持って取り組むことが成功への道筋となるでしょう。
公認会計士という職業は、高い専門性と社会的責任を伴う一方で、やりがいと将来性に満ちた魅力的な職業です。困難な道のりではありますが、明確な目標と適切な戦略により、必ず達成可能な目標です。あなたの公認会計士への挑戦を心から応援しています。
ジャスネットに登録してキャリア相談する
公認会計士になるまでの流れ図
この図は、公認会計士を目指す受験生が最終的に公認会計士として活動開始するまでの全体的な流れを示しています。試験合格から実際に公認会計士として働けるようになるまでには、通常3年から4年程度の期間が必要となることを理解しておきましょう。
【受験生時代】
〇 公認会計士試験(短答式試験)
-
12月・5月年2回実施
-
財務会計論、管理会計論、監査論、企業法
-
マークシート方式
↓(合格・2年間免除)
〇 公認会計士試験(論文式試験)
-
8月年1回実施
-
会計学、監査論、企業法、租税法、選択科目
-
記述式
(合格)
【試験合格者】
〇 監査法人等への就職活動
-
11月合格発表~12月内定(超短期決戦)
-
Big4監査法人 vs 中小監査法人
-
一般企業・コンサル等の選択肢も有
〇 実務経験(3年以上)+実務補習(3年間)
-
実務経験:監査法人、一般企業、金融機関等
-
実務補習:東京・東海・近畿・九州の補習所
-
270単位取得が必要
〇 修了考査受験・合格
-
年1回12月実施
-
5科目、2日間、計12時間
-
合格率約70%
〇 日本公認会計士協会への登録申請
↓
【公認会計士として活動開始】
-
監査業務、税務業務、コンサルティング
-
国際的なキャリアも可能
関連リンク