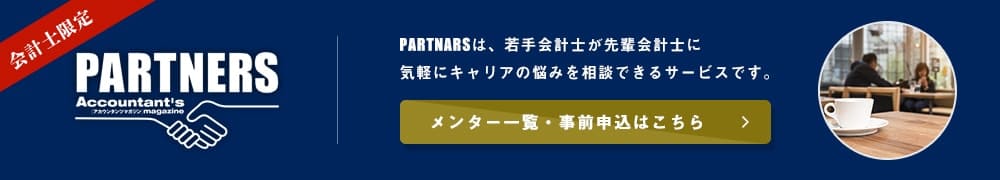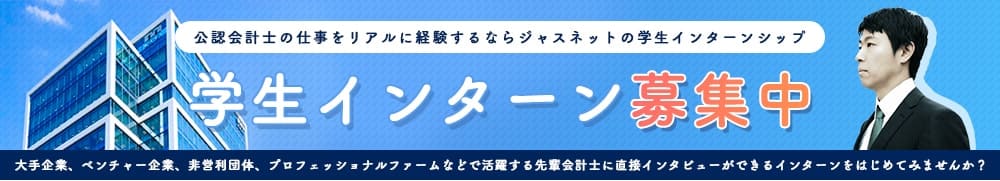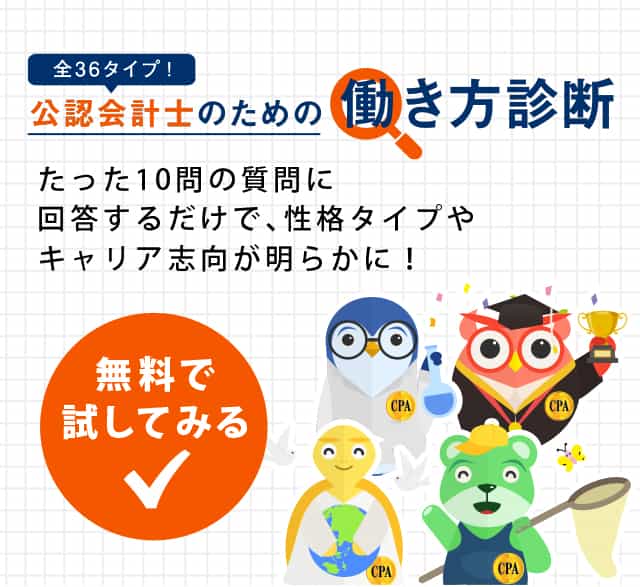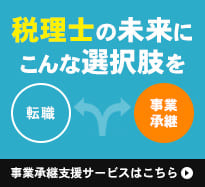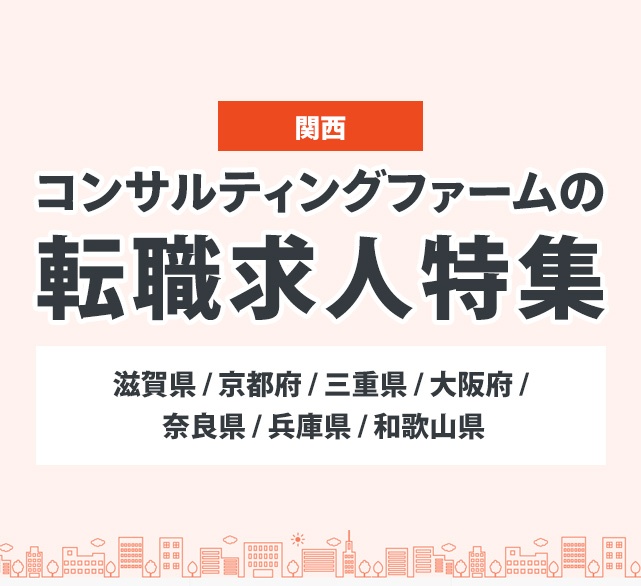新規株式公開(IPO)の価格を決める実務を見直す議論について

2021年12月15日 新開 智之
目次
IPOするときの上場株価について、一般的にどのように決まっているのかについて、ご存知の方はそんなに多くないと思います。
1. 現在の株価形成の主流はブックビルディング方式
ルール上、機関投資家など専門家からの評価をうけて、それらの評価結果を積み上げて ブックビルディング方式 (注1) という算定方法で計算され、需要状況を積み上げて価格決定されます。
1997年8月までは、株価形成の方式として、 入札方式 により新規公開株式の時価を算定していました。入札方式によると、新規公開時の株価形成が高くなりがちであり、株式上場後の円滑な流通に支障を来す等の課題が指摘され、現在ではブックビルディング方式による株価形成が主流となっています。入札方式は制度としては残っているようで、株価形成については選択的に利用できることになっているようです。
今回の日経新聞の記事によると、現在主流のブックビルディング方式による価格形成、価格決定について見直す方向性が改めて示されました。
2. ブックビルディング方式は、株価が低めに設定される傾向
個人的には、 IPO時のブックビルディング方式による株価形成は、結果的に低めに設定される傾向にある と感じています。
公開株価の計算方式の目安として、公開会社の成長性を加味してPER(株価収益率)という基準にもとづいて株価の目安とすることがあります。
目安として株価決定に用いられるPERは業種によっても異なりますが、高い成長性はそれほど見込めないと判断されると、純利益の8倍とか10倍程度で公開株価が決定されます。東京証券取引所の平均的なPERが20倍を超え、新興市場のPERが平均40倍程度となっているなかで、PER10倍程度で算定された公開価格について皆さんはどう思いますか。
3. 望まれるバランスの取れた価格形成
公開株価が低く形成されれば、公募・売り出しによる流動株式数を一定水準で維持しようとすると、資金調達額は低くなるし、資金調達額を優先すれば、必要以上に株主が増加してしまうことになります。
新規公開会社である資金調達サイドからみると、現在のIPOの価格決定プロセスについて、資金調達額が想像より多くならないことに不満が生じやすいという状況が常態といえます。
他方で、新規上場時の資金調達における課題解消のために、日本でも ダイレクトリスティング (注2) といった手法を取り入れていくことも検討されているようです。
株式の買い手にも売り手にも、また証券会社にも株式の発行体や世間にも、バランスのとれた価格形成により、適正で公正な資本市場の活用が望まれます。
(注1)
ブックビルディング方式とは、一般的に「需要積み上げ方式」と呼ばれ、IPOにおいて引受証券会社が、以下のプロセスに基づいて、IPO予定の会社の公募・売り出しに係る公開価格(=発行価格)を決定する方式のことです。
(1) 株価算定能力が高いと思われる機関投資家等の意見をもとに仮条件を決定する。
(2) その仮条件を投資家に提示し、投資家の需要状況を把握することによって、マーケット動向に即した公開価格を決定する。
1997年9月以降に公募等に係る取締役会決議をおこなう新規上場申請会社は、新規公開についてブックビルディング方式が採用されています。
(注2)
ダイレクトリスティングとは、「直接上場」のことで、資金調達を行わない上場方式をいいます。アメリカでは中小企業の上場に多く利用されてきた歴史があるようです。
日本の一般市場では、株式の流動性基準もあり、一般市場でダイレクトリスティングを利用する場合には、流動性基準を満たすだけの既存株式の売出しを実施する必要がありますが、現在はダイレクトリスティングの制度は一般市場にはありません。
現在、流動性基準がない市場で、既存株式の売出しも不要な市場として「東京証券取引所の東京プロマーケット市場」が注目を集めています。
関連リンク
- 公認会計士試験の合格発表後、最初のつまずきは就職活動?4大・準大手の募集要項を徹底比較!
- AIは公認会計士監査をどう変える?その可能性と課題を徹底解説
- 監査法人から一般企業の経理に転職!年収アップの方法と新たなキャリアの作り方
- 【2026年版】公認会計士の就活完全ガイド!|超短期決戦を勝ち抜く戦略と内定獲得の秘訣
- 【2026年最新】公認会計士に合格しても就職できない?監査法人に落ちたその後の現実と対処法
- 【完全版】公認会計士試験合格後にやるべきこととは?試験終了からキャリア設計まで
- CFOになるには? 必要なスキル・資格・キャリアパスを徹底解説!
- 監査法人とは何かを徹底解説!仕事内容・年収・転職・求人情報まで
- 公認会計士が非常勤の仕事をずっと続けるためのコツ
- 公認会計士の就職・転職|17種類のキャリアパスを徹底解説!
- 執筆者プロフィール
-
新開 智之(しんかい ともゆき)
公認会計士、監査法人コスモス統括代表社員平成4年3月岐阜大学教育学部卒業、平成10年3月公認会計士試験第3次試験合格後、社員、代表社員を経て、令和元年6月監査法人コスモス統括代表社員就任。会計監査・IPO支援のほか、財務・会計・税務を中心とした業務に就いて、マネジメント・コンサルティング、企業再編コンサルティング、環境ISOの構築支援及び審査を経験してきた。現在では、中小・中堅企業の株式上場・IPO支援を積極的に実施しており、最近5年間で11社を東京プロマーケット市場へ上場支援し、特に東京プロマーケット市場から一般市場へのステップアップ上場への支援にも積極的に活動中。