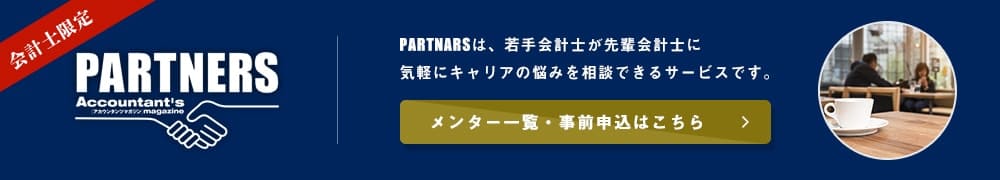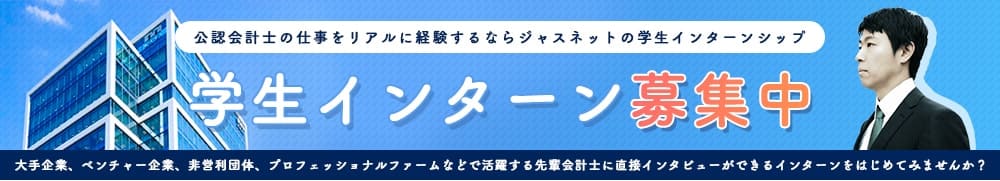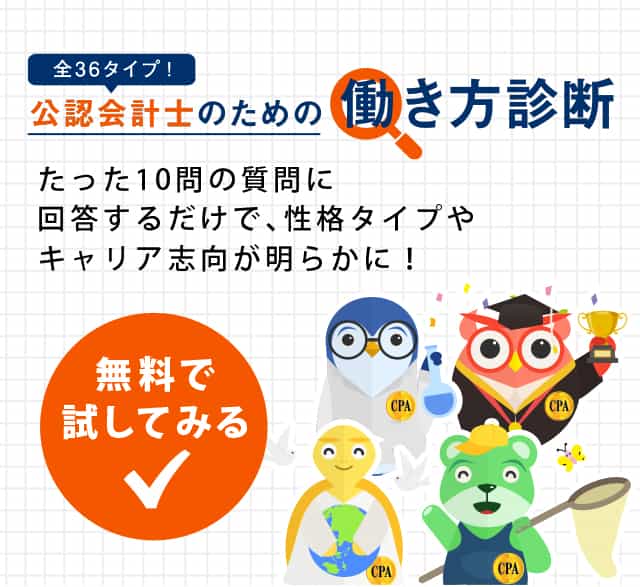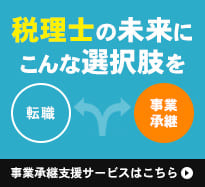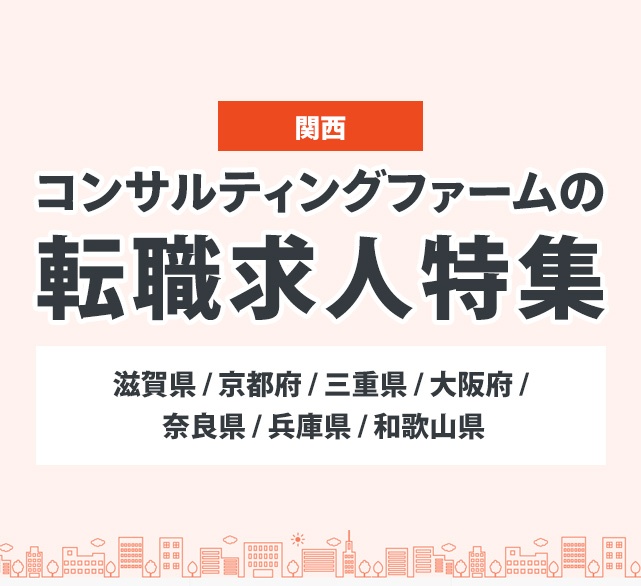ここでは、これから公認会計士試験の受験を考えるみなさんに、公認会計士の「
継続的能力開発制度(CPD)
」の概要をお伝えします。
従来「継続的専門研修制度(CPE)」と言われていたものを、2020年に判明した不適切な受講等を契機に新たなプロジェクトチームを立ち上げて検討を加え、欧米の制度も参考にして、2023年4月より新たな制度として生まれ変わりました。
基本的な考え方はCPEと変わりありませんが、今後、会員足る公認会計士がより自主的かつ能動的に能力開発を行うために充実強化を図ることを目的として名称が変更されています。
ここでは、いったいどのくらいの単位を取らなければならないのか、その単位数から、取得の方法の例までを、独立開業している公認会計士の筆者がご紹介します。
■CPDとは?
CPDとは、公認会計士としての資質の維持・能力の向上を図るために、日本公認会計士協会が実施している「継続的専門能力開発制度」のことをいいます。
Continuing Professional Development
の頭文字をとって、CPDといわれています。
公認会計士法の第1条の2に「公認会計士は、常に品位を保持し、その知識及び技能の修得に努め、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。」とあり、その「知識及び技能の修得に努め」という部分を制度的に担保するのが、CPDです。
■単位取得の具体的な方法は?
具体的には、
公認会計士協会の開催する集合研修会への参加や、自己学習、著書の執筆、セミナー講師を行うこと
により、CPDの単位を取得します。
平成14年4月から、すべての公認会計士が「継続的専門研修」を履修し、「必要な単位数」以上を履修することが義務付けられました。
ちなみに、税理士については、従来からCPE制度があり、年間36時間の研修を受けなければなりません。こちらは平成27年度から義務化されています。
■CPDに必要な単位数は?
(1)直近3年間で、合計120単位必要
公認会計士は、
当該事業年度(4/1~3/31)を含む直前3事業年度で合計120単位以上のCPD単位を履修しなければなりません
。つまり、直近3年間で、合計120単位を取得しなければなりません。
年間では、最低1年20単位以上の単位取得が必要
です。
また、すこし細かいのですが、必須研修科目として、「職業倫理」 2単位及び「税務」 2単位、加えて法定監査に業務従事する者においては、「監査の品質及び不正リスク対応」6単位(うち2単位以上は不正事例に該当する研修とする)の単位取得が義務づけられています。
CPDの事業年度は、4月1日から3月31日です。そして、取得単位は、CPD ONLINE(
https://www.cpd.jicpa.or.jp/
)の会計士自身のマイページを通じて報告することになります。
(2)組織内会計士、準会員の取得単位は?
企業内で働く組織内会計士には、企業で働きながら単位を取得することは企業の制約、時間等の関係で、困難をともなうため「公認会計士」の手放してしまう方もいるようです。このため組織内会計士を対象に、取得単位数の規定を緩める動きはあるようです。
また、準会員の方については、まだ、公認会計士として協会に登録されていないので、CPDの取得義務はありません。
■CPDを取るには?
(1)CPDの取得方法
監査法人に所属している公認会計士は、
法人内の研修や e-learningを受講することにより、単位取得は比較的容易
です(法人研修やe-learnigは、CPDの単位に認められます)。しかも、費用は無料になります。
独立開業をされた方や、それらの研修を実施していない監査法人等に勤務されている方は自らの判断で研修を受講したり、自己学習したりして、単位を取得する必要があります。
具体的なメニューは、先にも書きましたが、
公認会計士協会の開催する集合研修会への参加(無料のものから費用のかかるものがあります)、それを収録したDVDやe-leanigの受講、自己学習(CPDの指定記事、専門書の読書等)、著書の執筆、研修会やセミナー講師を行う
、などがあります。
(2)CPDの単位が取れなかった場合は?
ちなみに、単位が取得できず、義務不履行者となった場合は、第1段階の措置として、履修に関し「指示」を受け、その旨「公示」されます。そして、「指示」を受けた会計士がその指示に従わず、翌事業年度についても義務不履行者となったときは、第2段階の措置として、当該指示に違反した旨を「公表」されることになります。結構、厄介なことになります。
ちなみに公認会計士法の改正に伴い
2023年度以降は3年連続0単位だと登録抹消の対象
となります。
■CPD取得方法の例
独立開業しているわたしは、下記の方法でCPDを取得しています。
①日本公認会計士協会東京会の研修を受ける。
②日本公認会計士協会税務業務部会の研修を受ける。
日本公認会計士協会から、研修の案内が届きますので、必要と思われる研修を、受講します。
③ジャスネットコミュニケーションズ株式会社など、企業が開催する勉強会や講演会に出席する。
日本公認会計士協会が主催する研修以外にも、CPD認定される民間の研修がありますので、それに出席して、単位を取得します。
④自己学習する。
公認会計士協会が発行する「会計・監査ジャーナル」には、CPD指定記事があり、それを読み、概要説明、研修成果、感想を書くことで、単位が取得できます。
この方法は、費用がかからないですし、時間も自由に使えるので、わたしは、自己学習で大半の必要単位を取得しています(ただし、自己学習のみは、年40単位まで)。
さらに詳細な変更点については、下記(『CPDレター』2023年4月号)を参考にしてください。
https://pro-cpeo-s3-sharedstorage-01.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/guide/2023_001-007.pdf
■まとめ
公認会計士として業務を行なっていくには、その公認会計士としての資質の維持・能力の向上を図り、経済環境、監査環境の変化へ即座に対応していくことが必要になります。それを能力面から担保する為に、このCPD制度があります。原則として、公認会計士として登録しているうちは、ずっと単位を取得し続けなければなりません。
大変なことだとは思いますが、CPD制度を利用し、会計士業界の信頼性の維持、公認会計士個人としての信頼性の維持に繋げていっていただけたらと思います。
関連リンク