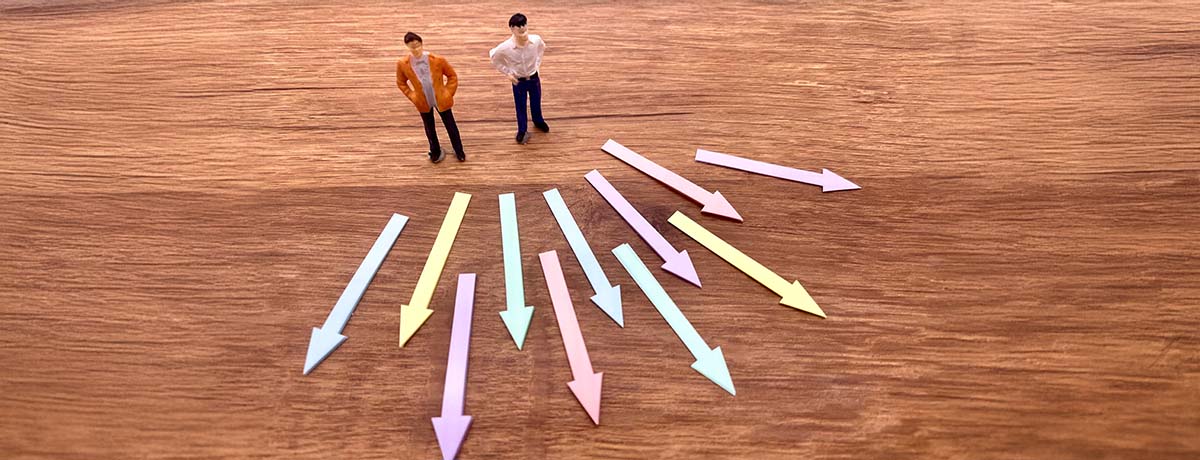■なぜ「税理士法人」での勤務が最も王道のキャリアとされるのか
税理士としてのキャリアをスタートする際、多くの人が選択するのが税理士法人や会計事務所での勤務です。これが王道とされるのには明確な理由があります。
(1)税理士登録のための実務要件を満たす
まず実務要件の充足です。
税理士登録には税理士試験合格だけでなく、租税または会計に関する実務経験が通算2年以上必要となります
。(在職証明書等 ※詳細は日本税理士会連合会の登録手引きを参照してください)
税理士法人での勤務はこの要件を満たす最も確実な方法であり、多くの税理士が一度は経験する道となっています。
【参照】
日本税理士会連合会「税理士登録の手引」
https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/doc/cpta/system/entry/howto/entrymanualR7.pdf
(2)法人税務の基本から応用までを学べる
また、税理士法人では法人税務の基本から応用まで、体系的に学ぶことができます。
記帳代行や月次決算といった会計業務からスタートし、年次決算、法人税申告書の作成へと段階的にスキルを積み上げていきます。この過程で、
中小企業から大企業まで、様々な規模や業種のクライアントに触れることができ、税理士としての基礎体力が養われる
のです。
(3)規模によって様々な経験を積める
税理士法人の規模によって得られる経験も大きく異なります。
BIG4税理士法人では国際税務やM&A、組織再編といった高度な案件に携わる機会があり、グローバルな視点を養えます。
一方、中小規模の事務所では経営者と直接対話する機会が多く、クライアントとの密接な関係構築や経営相談のスキルを磨けます。
(4)業界内でのネットワーク
税理士法人での勤務を通じて得られるもう一つの大きな財産は、業界内でのネットワークです。
同僚や上司、クライアントとの関係は、将来独立する際の顧客基盤となったり、転職時の人脈となったりします
。税理士業界は意外と狭い世界であり、こうした人間関係が後のキャリアに大きく影響することも少なくありません。
さらに、税理士法人での経験は、その後どのような道に進むにしても必ず役立ちます。企業内税理士に転職する場合も、コンサルティングファームに移る場合も、独立開業する場合も、税理士法人での実務経験は評価される重要な要素となるのです。
■一般企業で税理士資格を活かせる「企業内税理士」とは
企業内税理士という働き方は、近年注目を集めているキャリアパスです。一般企業に社員として所属しながら、税理士としての専門性を発揮する道です。
(1)主な配属先は経理部門や財務部門
企業内税理士の主な配属先は経理部門や財務部門となります。そこでの業務は税務申告書の作成だけでなく、日常的な経理業務、四半期決算や年次決算の実施、連結決算への対応など多岐にわたります。
大企業であれば税務部門が独立しているケースもあり、そこでは税務戦略の立案や税務リスクの管理、移転価格税制への対応など、より専門的な業務に従事することになります。
(2)一つの企業に深く関わることができる
企業内税理士の特徴は、
一つの企業に深く関わることができる点
です。税理士法人では複数のクライアントを担当するため、それぞれの企業への関わりは限定的になりがちです。
しかし企業内税理士は自社の経営戦略や事業計画に深く関与し、M&Aや組織再編といった重要な意思決定の場面で税務面からのアドバイスを提供します。経営層との距離も近く、場合によってはCFOなど経営幹部へのキャリアパスも開かれています。
(3)給与は税理士法人と比べて安定性が高い
給与体系は勤務する企業の制度に準じるため、税理士法人と比べて安定性が高いのが特徴です。年功序列や役職に応じた昇給があり、将来の見通しが立てやすくなります。
平均年収は600万円から1000万円程度
で、大企業や管理職になればそれ以上も可能です。また、福利厚生も充実している企業が多く、住宅手当や育児支援制度など、ワークライフバランスを重視した働き方ができる環境が整っています。
(4)どのような人が向いているのか
この職種に向いているのは、
一つの組織に腰を据えて、長期的な視点で企業経営に貢献したいと考える人
です。複数のクライアントを相手にするよりも、一つの企業を深く理解し、内部から支えることに魅力を感じる人には最適な選択肢でしょう。また、マネジメント経験を積みたい人や、税務だけでなく経理や財務など幅広い業務に携わりたい人にも適しています。
ただし注意点もあります。税理士としての専門性を深めるという観点では、税理士法人ほど多様な案件に触れる機会は少なくなります。また、企業の方針によっては税理士登録を維持する必要がないケースもあり、登録料や会費を自己負担する場合もあります。こうした点を理解した上で選択することが重要です。
■大規模な「国際税務」案件に携わる税理士になるためには
グローバル経済が進展する現代において、国際税務の需要は年々高まっています。
大規模な国際税務案件に携わりたいと考える税理士にとって、最も確実な道はBIG4税理士法人への就職です
。
(1)BIG4税理士法人とは
BIG4税理士法人とは、
EY税理士法人、KPMG税理士法人、デロイト トーマツ税理士法人、PwC税理士法人
の4つを指します。これらは世界的な会計ファームのネットワークに属し、グローバル企業の税務業務の多くを担っています。そのため、海外子会社との取引に関する移転価格税制の対応や、国際的な組織再編、クロスボーダーM&Aといった高度な案件に携わる機会が豊富にあります。
(2)どのようなスキルが求められるのか
国際税務の仕事では、日本の税法だけでなく、取引相手国の税制や租税条約についての知識が求められます。各国の税務当局との折衝や、二重課税の回避策の立案など、高度な専門性が必要とされる分野です。そのため、
中級から上級の英語力は必須
となります。契約書や税務文書を英語で読み書きし、海外の税務専門家とコミュニケーションを取る場面も日常的です。
(3)BIG4税理士法人での働き方
BIG4では部門ごとに専門性が分かれており、国際税務に特化したチームが存在します。そこでは日本企業の海外進出を支援するアウトバウンド業務と、外資系企業の日本進出を支援するインバウンド業務の両方を経験できます。キャリアとしては、アソシエイトからスタートし、シニアアソシエイト、マネージャー、シニアマネージャー、そしてパートナーへと段階的に昇進していく道が用意されています。
年収水準も高く設定されており、
入社時で500万円から700万円程度、マネージャークラスになれば1000万円を超えることも珍しくありません
。ただし、その分求められる水準も高く、長時間労働になりがちな点は覚悟が必要です。プロジェクトベースで動くことが多く、繁忙期には深夜までの残業や休日出勤も発生します。
(4)どのような人が向いているのか
この分野に向いているのは、
グローバルな環境で自分の専門性を高めたい人、英語を使った仕事に興味がある人、高度な税務知識を追求したい人
です。また、将来的に独立して国際税務に特化した事務所を開業したいと考えている人にとっても、BIG4での経験は大きな財産となります。
■なぜ「コンサルティングファーム」が税理士にとって魅力的なのか
税理士資格を持ちながら、経営コンサルタントとして活躍する道も開かれています
。
コンサルティングファームでは、税務の専門知識に加えて、経営全般に関する助言を提供することが求められ
、税務の仕事以外にも幅を広げたいという志向の方に魅力的な選択肢です。
(1)親和性が高い財務系コンサルティングファーム
税理士と親和性が高いのは財務系コンサルティングファーム、特に
FAS(Financial Advisory Service)と呼ばれる分野
です。BIG4系列のFASには、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー、KPMG FAS、PwCアドバイザリー、EYストラテジー・アンド・コンサルティングなどがあります。
これらのファームでは、
M&A支援、企業再生、事業承継、財務デューデリジェンスなど、財務と税務が深く関わる領域でのコンサルティングを提供しています
。
M&A案件では、買収対象企業の税務リスクを調査する税務デューデリジェンスや、最適な組織再編スキームの立案などで税理士の専門性が発揮されます。買収金額が数億円から数百億円規模になることも多く、税務の判断一つで大きな金額が動くため、責任も大きいですがやりがいも格別です。
(2)税理士法人の子会社として設立されたコンサルティング会社も
また、税理士法人の子会社として設立されたコンサルティング会社も増えています。これらの会社では、税務顧問業務の延長線上に経営コンサルティングを位置づけており、税理士としてのバックグラウンドを活かしやすい環境です。
中小企業向けに経営計画の策定支援や資金調達支援、事業再生支援などを提供し、税務だけでなく経営全般にわたるサポートを行います
。
(3)一般的な税理士法人よりも高収入
コンサルティングファームでの年収は、
一般的な税理士法人での勤務と比べて100万円から300万円程度高く設定されています
。プロジェクトの規模や成果に応じたインセンティブもあり、マネージャークラスになれば年収1000万円を超えることも珍しくありません。
ただし、求められるスキルも高度です。税務知識だけでなく、クライアントの経営課題を的確に把握するヒアリング力、データ分析に基づいた論理的な提案力、経営層を納得させるプレゼンテーション力など、総合的なコンサルティングスキルが必要とされます。
(4)どのような人が向いているのか
この分野に向いているのは、
税務だけでなく経営全般に興味があり、企業の成長や課題解決に深く関わりたい人
です。また、高い報酬を得ながら専門性を高めたい人、将来的にコンサルタントとして独立を考えている人にも適しています。ただし、プロジェクトベースの働き方になるため、不規則な勤務時間や出張が多くなることは覚悟が必要です。
■どのように「金融機関」で税理士資格を活用できるのか
金融機関も税理士が活躍できる重要なフィールドです。
銀行や証券会社、信託銀行などでは、税理士の専門知識を活かした業務が数多く存在します
。
(1)金融機関での税理士の役割
金融機関での税理士の役割は大きく二つに分かれます。一つは
自社の税務業務を担当する企業内税理士としての立場
です。大手金融機関では複雑な金融商品の税務処理や、海外拠点との取引に関する国際税務など、高度な専門知識が求められます。
もう一つは、
顧客向けのコンサルティング業務
です。特に富裕層向けのプライベートバンキング部門や相続関連部門では、税理士資格を持つアドバイザーの需要が高まっています。相続税の節税対策、生前贈与のスキーム設計、不動産の有効活用による資産承継など、税務の専門知識を活かした提案が求められます。
金融機関での年収は、企業規模や職種によって幅がありますが、
大手金融機関であれば600万円から1000万円程度が一般的
です。管理職になればそれ以上の収入も期待できます。また、福利厚生が充実しており、安定した雇用環境が魅力です。
(2)信託銀行の場合
信託銀行では遺言信託や遺産整理業務を扱っており、税理士としての知識が直接活かせます。相続財産の評価、相続税の試算、納税資金の準備といった業務では、税理士の専門性が不可欠です。また、事業承継を検討している経営者に対して、自社株の評価や株式の移転方法、事業承継税制の活用など、包括的なアドバイスを提供する場面もあります。
(3)証券会社の場合
証券会社では、金融商品の販売に際して税務面でのアドバイスを提供します。株式や投資信託の譲渡益にかかる税金、NISAやiDeCoといった税制優遇制度の活用方法など、顧客の資産運用を税務面からサポートします。
(4)どのような人が向いているのか
この分野に向いているのは、数字に強く、金融商品や資産運用に興味がある人です。また、顧客対応が中心となるため、コミュニケーション能力が高く、信頼関係を構築することが得意な人に適しています。
相続や事業承継といった人生の重要な局面で顧客に寄り添い、サポートすることにやりがいを感じられる人には最適な職種でしょう
。
■「相続・資産税の専門家」として差別化するには
税理士の業務の中でも、相続税や贈与税を中心とした資産税の分野は高い専門性が求められる領域です。この分野に特化することで、他の税理士との差別化を図り、独自のポジションを確立できます。
(1)相続・資産税の専門家とは
相続税は人の死亡という避けられない事象に伴って発生するため、景気に左右されにくく安定した需要があります。2015年の相続税改正により基礎控除額が引き下げられたことで、相続税の申告が必要な人の数は大幅に増加しました。今後も高齢化社会の進展に伴い、この傾向は続くと予想されています。
資産税専門の税理士法人では、財産評価から相続税申告、遺産分割協議のサポート、二次相続を見据えた対策まで、トータルでサービスを提供します。
特に不動産の評価は専門的な知識が必要で、土地の形状や立地条件、利用状況などを細かく分析し、適正な評価額を算出します。この評価額次第で相続税額が大きく変わるため、高度なスキルが求められます。
生前対策のコンサルティングも重要な業務です。生前贈与の活用、不動産の組み替え、生命保険の活用、家族信託の設計など、相続税を軽減しながら円滑な資産承継を実現するための提案を行います。こうした業務では、税務の知識だけでなく、民法や信託法、不動産に関する知識も必要となります。
(2)資産税専門の代表的な税理士法人
資産税専門の税理士法人の代表的なものとして、
税理士法人レガシィやランドマーク税理士法人
などがあります。これらの法人では相続案件を年間数百件から千件以上扱っており、豊富な経験とノウハウを蓄積しています。そこで働くことで、様々なケースに触れ、専門性を高めることができます。
報酬体系も特徴的で、相続税申告の報酬は相続財産の額に応じて設定されることが多く、数十万円から数百万円、時には千万円を超える案件もあります。
そのため、専門性を高めることで高い収入を得ることが可能です。
(3)どのような人が向いているのか
この分野に向いているのは、一つの分野を深く掘り下げることに興味がある人、
不動産や民法など税務以外の知識も学ぶ意欲がある人
です。また、相続という人生の重要な場面で家族に寄り添い、時には感情的な対立を調整しながら問題を解決していく、人間力が求められる仕事でもあります。コミュニケーション能力が高く、相談者の気持ちに共感できる人に向いているでしょう。
■なぜ「独立開業」には計画的な準備が必要なのか
独立開業は多くの税理士が目指すゴールの一つです。自分の裁量で仕事を選び、報酬を設定し、自由な働き方を実現できる魅力があります。しかし、成功するためには十分な準備と明確な戦略が必要です。
(1)独立のタイミング
独立のタイミングは人それぞれですが、一般的には
税理士法人で10年程度の経験を積んでから
という人が多いです。この期間に、税務実務のスキルはもちろん、顧客対応力、営業力、そして何より人脈を築くことが重要です。実際、独立後の最初の顧客は前職での関係者であることが多く、
勤務時代にどれだけ信頼関係を構築できたかが独立後の成否を分けます。
(2)最大の課題は顧客開拓
独立開業の最大の課題は顧客開拓です。知名度のない個人事務所が新規顧客を獲得するのは容易ではありません。
セミナーの開催、ホームページやSNSでの情報発信、異業種交流会への参加など、様々な営業活動が必要になります。
安定した収入を得られるまでの期間を考え、最低でも1年分の生活費は確保してから独立することが賢明です。
(3)事務所の方向性を明確に
事務所の方向性を明確にすることも重要です。中小企業の法人税務を中心とするのか、相続税に特化するのか、特定の業種に強みを持つのか。専門性を明確にすることで、他の事務所との差別化が図れます。また、最近ではクラウド会計の導入支援やオンライン対応など、ITを活用した効率的なサービス提供も求められています。
(4)独立開業後の収入
独立開業の収入は個人差が大きいのが特徴です。業務内容などでも大きく変わりますが、
一人事務所の場合、売上高は1,000万円から2,000万円程度が一般的
とされています。そこから経費を差し引いた金額が収入となります。顧客数を増やし、従業員を雇用して事務所を拡大していけば、年収数千万円も可能ですが、その分経営者としての責任も重くなります。
逆に、少数の優良顧客に絞り、高単価のサービスを提供する戦略もあります。この場合、顧客数は少なくても一社あたりの報酬を高く設定することで、効率的に収入を得られます。ワークライフバランスを重視し、自由な時間を確保しながら働くことも可能になります。
(5)どのような人が向いているのか
独立開業に向いているのは、
自分で事業を経営することに情熱を持てる人、リスクを取ることを恐れない人、営業活動に積極的に取り組める人
です。また、税務の専門家であると同時に経営者でもあるため、従業員の採用や教育、事務所のマーケティング戦略など、経営全般の知識とスキルも必要になります。
独立は決して楽な道ではありませんが、成功すれば大きな達成感と自由を手に入れることができます。勤務税理士として経験を積みながら、将来の独立に向けて着実に準備を進めることが成功への鍵となります。
■どのように自分に合ったキャリアパスを選択すべきか
ここまで税理士資格を活かした様々な職種とキャリアパスを見てきました。最後に、自分に合った道をどのように選択すべきか考えてみましょう。
まず自分の価値観を明確にすることが大切です。収入を最優先するのか、ワークライフバランスを重視するのか、専門性を追求したいのか、幅広い経験を積みたいのか。こうした優先順位は人によって異なり、正解はありません。
安定を求めるなら企業内税理士や大手税理士法人での勤務
が適しています。給与体系が明確で、福利厚生も充実しており、将来の見通しが立てやすいのが特徴です。一方、
高い収入を目指すなら、コンサルティングファームでの経験を積むか、将来的に独立開業を視野に入れる
ことになります。
専門性を深めたいなら、国際税務や資産税など特定分野に特化した税理士法人を選ぶ
とよいでしょう。一つの分野を極めることで、その領域でのエキスパートとして認められ、高い報酬を得ることができます。逆に
幅広い経験を積みたいなら、中小規模の税理士法人で様々な業種のクライアントを担当したり、企業内税理士として税務以外の経理財務業務にも携わったりする
ことが有効です。
グローバルな環境で働きたい、英語を使いたいという希望があるなら、BIG4税理士法人が最適です。
国際税務の案件に携わることで、世界基準のスキルを身につけることができます。
■まとめ
キャリアは一直線である必要はありません。最初は税理士法人で基礎を固め、その後企業内税理士に転職して企業経営の視点を学び、最終的に独立開業するという道もあります。あるいは、税理士法人からコンサルティングファームに移り、高度なコンサルティングスキルを身につけてから専門性を活かした独立をする人もいます。
重要なのは、それぞれの段階で何を学び、次のステップに向けてどのような準備をするかです。目的意識を持って経験を積むことで、キャリアの選択肢は広がり続けます。
税理士資格は生涯有効な強力な武器です。この資格を活かして、自分らしいキャリアを築いていくことができます。独立開業だけが正解ではなく、様々な形で社会に貢献し、充実したキャリアを歩むことができるのです。自分の適性と希望をよく見極め、最適な道を選択していただければと思います。
税理士の転職なら経理・会計専門のジャスネットに相談
関連リンク
- 執筆者プロフィール
-
ジャスネットキャリア編集部
WEBサイト『ジャスネットキャリア』に掲載する記事制作を行う。
会計士、税理士、経理パーソンを対象とした、コラム系読み物、転職事例、転職QAの制作など。
編集部メンバーは企業での経理経験者で構成され、「経理・会計分野で働く方々のキャリアに寄り添う」をテーマにしたコンテンツ作りを心がけていてる。