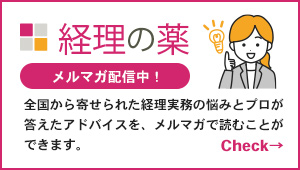目次
この記事では、監査法人勤務の後、地元の山形県で税理士事務所を開業され、直実に規模を拡大している税理士・会計士の井上哲寿さんに税理士が独立・開業前に知っておくべきポイント、メリットやデメリット、かかる費用についておうかがいしました。
■税理士が独立することのメリットは?
やはり独立することの一番のメリットは、自分の裁量ですべてが決められるということではないでしょうか。自分のやりたい仕事を選ぶことができますし、ポリシーに反する仕事は受けないという自由もあります。
また頑張れば頑張っただけ収入に結びつくため、やりがいもあると思います。
しかし、独立には向き不向きがあります。税理士という税務の専門家でありながら、経営者としてのスキルも求められるため、コミュニケーション能力も必要です。
専門家として黙々とひとつの道を究めたいというタイプではなく、様々な関係を広げながら仕事をしたいという人の方が向いているといえるでしょう。
■税理士が独立することのデメリット、リスクは?
独立したあと、「思っていたより仕事がとれない」「順調に売り上げが伸びない」ということは、往々にしてあると思います。わたしの場合もそうだったのですが、最初の1、2年は赤字の可能性もありますので、そこは自分を信じて頑張ってみましょう。
わたしの場合、最初の2年は収入がなくてもやっていけるだけの貯蓄をした上で、独立に踏み切りました。
実は独立したものの経営が上手くいかず、税理士事務所に再就職する人も意外と多いですし、一からの独立ではなく、後継者のいない税理士事務所の跡を継ぐような形で独立する方もいます。
また、あまり多くはないですが、仕事上でミスを犯したときに訴訟となる可能性もゼロではないため、そのリスクを負うということも頭に入れておいた方がいいでしょう。
■独立するタイミングの判断
わたしは生まれ育った山形で様々な企業のお手伝いをすることで、地元に貢献したいという想いがあったので、それを実現できるのが税理士として独立という手段でした。
当初は公認会計士として監査業務に従事していたため、税務の経験はもちろんありません。本来ならば、2年程度は税理士事務所で実務経験を積んでから独立した方がよいでしょう。
わたしは、なるべく早く独立して経営を軌道にのせたいという想いがあったので、35歳の時に独立開業し、税務の知識と経験は働きながら身につけました。
独立を急いだのは、なるべく若い頃のほうが変化にも柔軟に対応でき、フットワークも軽いだろうと思っていたからです。
もし今の税理士事務所の仕事がきついから、給料に不満があるから、などの消極的な理由だけで独立を決めると、必ずしもうまくはいかないのではないかと思います。収入面だけで言えば、税理士法人のパートナーを目指した方が高いかもしれません。
自分が何をやりたいのかを考え、ひとつポリシーを持つことで、独立開業後に起こる様々な問題にも対応することができると思います。
■税理士が独立開業するまでにやるべきことは?
・2年間の実務経験
わたしの場合は先に述べた通り、独立後に働きながら税務に関する知識を身につけましたが、できれば税理士事務所で2年間程度は働き、実務経験を積んでからの方がスムーズに独立開業できると思います。
・税理士登録申請
税理士登録申請には2か月ほど必要で、最初の年は入会金と年会費で費用が25万円程度かかります。その後、毎年10万円ほどの年会費を払っています。
わたしは個人の公認会計士としても登録したので、そちらも同程度の費用がかかりました。
・開業資金をためる
あくまで目安ですが、わたしは2年間全く仕事がなくても大丈夫なようにと、自己資金で300万円用意しました。月々の固定コストを2年間払えるくらいの金額です。銀行などから借りる税理士さんもいらっしゃいます。
■開業に向けた具体的な準備とは?
(1)立地の選定と物件の探し方
わたしの場合、最初は実家を事務所として登録しました。その後、レンタルオフィスに移り、スタッフが増えるにつれて少しずつ事務所を大きくしていき、今は山形市の中心部にオフィスを構えています。便利な場所を選んだのは、働く人が集めやすいという理由からです。
東京などの都心部ですと、事務所の賃料も高いと思いますが、駅から近いところなど、やはり便利な場所に借りた方がよいと思います。
(2)税理士会への登録
上記でも述べた通り、税理士登録には時間がかかります。前もって事務所開業に間に合うようスケジュールを組んでおきましょう。
(3)人の採用等
先輩からは10社くらいお客さんを持つようになってきたら、人を採用した方がよいとアドバイスされていました。コストはかかりますが、なるべく早い段階で人を雇い、仕事を覚えてもらうことで、事務所の業務がスムーズにまわるようになります。
(4)経営理念
わたしも独立し、数年してからきちんとまとめたのですが、やはり事務所を経営する上で、「こういった理念があります」と明言することは必要だと思います。
自分自身の軸にもなりますし、仕事を紹介していただく際も、自分の仕事のスタンスを理解していいただくことができます。
(5)その他
開業した事務所でどの会計ソフトを使うかの判断も必要です。
また事務所の案内の仕方(ホームページの作成、SNS告知など)、顧客へのアプローチもどのようにするか考えなくてはなりません。わたしの場合は、独立した際には顧客ゼロだったので、そのあたりもきちんと考えてから独立しました。
■開業にかかる費用、資金は?
(1)賃貸契約等の初期費用
わたしは最初に借りたのがレンタルオフィスだったため、月のレンタル料にプラスして敷金2か月分の費用がかかりました。場所によっても家賃の相場は違いますので、賃料の数か月分はやはり準備が必要だと思います。
(2)税理士登録費用
こちらは前に述べた通り、入会金と年会費で最初の年は25万程度かかります。公認会計士としての登録も同様の費用がかかります。
(3)PC、机、コピー機などの費用
自分ひとりの場合、これらの費用はそこまで高額にはならないと思います。
わたしはパソコン代として15万円くらいでした。コピー機も安価なものを購入したのですが、プレゼン資料などを作る機会も多いため、これはきちんとしたものをリースした方がよいと思います。
(4)会計ソフト代
税務申告までできるようなメジャーなものは、月に数万円かかります。わたしは最初、TKCを月4~5万円で使用していました。
しかし税理士業界は毎年、細かい税制改正や別表のフォーマットが変更されたりするので、コストがかかったとしても、ここはきちんとしたものを使用した方がよいでしょう。
現在は3種類の会計ソフトを使い、お客様に対応できるようにしています。
(5)その他
税理士の場合は、デメリットの項でも触れた通り、訴訟に備える保険などに入ることも必須です。
また地元の青年会、商工会などにも登録すると、年間10万~程度のコストがかかります。
あとは挨拶まわりや、様々な繋がりを作るための交際費なども、どの程度重視するかで費用は変わってくると思います。